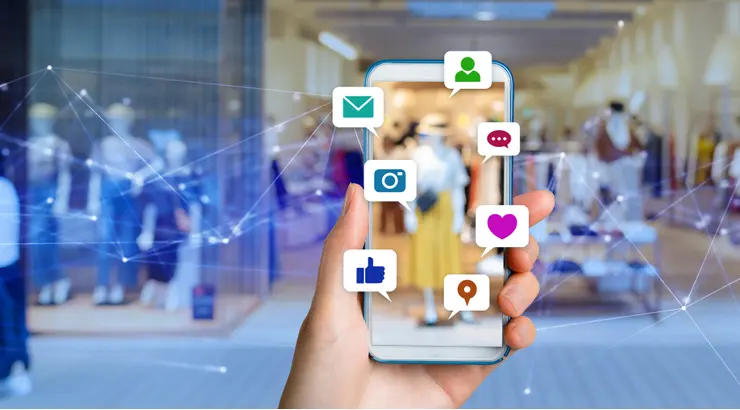
社内SNSを導入しようとしているものの、導入することでどんなメリットとデメリットがあるのか、気にしてる方もいるのではないでしょうか。社内SNSを導入することで、コミュニケーションを活性化させたり、業務を効率化させたりできます。一方、コミュニケーション疲れや公私混同を招くことがあります。今回は、社内SNSを導入するメリットとデメリットを詳しく解説します。
目次
社内SNSを導入する5つのメリット
社内コミュニケーションを活性化できる
社内SNSを導入することで得られる代表的なメリットとして、社内コミュニケーションを活性化できることが挙げられます。 社内SNSでは写真やテキストを使って業務の報告をするため、ほかの人がどんな業務をしているのかを知ることができます。
また、その投稿に対してスタンプを押したりコメントしたりすることで、コミュニケーションを取ることができます。 日頃、仕事をしているなかで、「近くにいるけど何の仕事をしているかわからないから話すきっかけがない」ということがあるでしょう。社内SNSでお互いの業務内容を知ることで、コミュニケーションのきっかけをつくることができます。
ノウハウを共有しやすくなる
社内SNSで業務内容を共有することで、誰がどんな仕事をしているのかがわかるようになります。これにより、何か知りたいことがあったときに誰に聞くと良いかがわかりやすくなります。 このように、社内SNSを利用することでほかの社員の業務内容を知ることでその人の専門性がわかり、欲しいノウハウを誰が持っているのかがわかりやすくなります。
動画や画像も簡単に共有できる
社内SNSでは、動画や画像も簡単に共有することができます。 普段の業務で、ビジネスチャットを利用している方は多いでしょう。しかし、ビジネスチャットはSNSではないため、画像や動画を共有したときはファイルとして共有することになります。 社内SNSはタイムラインとして投稿できるため、動画や画像も簡単に共有することができます。
外出先でも簡単にやり取りできる
多くの社内SNSはスマホでも利用できるため、外出先でのちょっとした空き時間での利用することができます。 メールや電話でやり取りをしている場合、メールを作成するのに時間がかかったり、電話がつながらなかったりすることがあります。
しかし、社内SNSはタイムラインに投稿したりチャットで連絡したりするため、外出先でのちょっとした空き時間でも連絡することができます。 これにより、時間を有効活用できるようになります。
メンバーの業務進捗を確認できる
社内SNSではタイムラインで業務の報告をするため、メンバーの業務進捗を確認することができます。 メンバーをマネジメントする立場にいる方は、部下が予定通りに業務を進めているのかわからないと感じたことがあるのではないでしょうか。社内SNSは写真付きで業務の報告ができるため、上司から確認しなくてもシステム上で業務進捗を確認することができます。
社内SNSを導入する3つのデメリット
これまで、社内SNSを導入することで得られるメリットを紹介してきました。ここでは、社内SNSを導入することで生じるデメリットを紹介します。デメリットもしっかりと抑えたうえで、導入を検討してみてください。
コミュニケーション疲れになることがある
社内SNSは気軽にコミュニケーションを取れる反面、それが疲れの原因になってしまうことがあります。 社員のなかには、「SNSで仕事の人とつながりたくない」「常に連絡を取っていることが苦手」と考える人もいるでしょう。そう考える人にとって、社内SNSを利用することが負担になってしまうことがあります。
公私混同してしまう恐れがある
社内SNSは仕事で利用するものではあるものの、比較的気軽に使えます。それゆえに、公私混同してしまうことがあります。 業務の報告をする投稿のコメント欄で会話が盛り上がることで、肝心な業務が進まないということも起こり得ます。そのような公私混同を招くリスクがあることを押さえておきましょう。
情報漏えいのリスクがある
社内SNSは業務に関する情報をやり取りするもので、そのなかには機密情報もあるでしょう。社内SNSの取り扱いについてしっかりと教育できていなかった場合、情報漏えいを起こしてしまうリスクがあることを押さえておきましょう。
社内SNSの導入を成功させる秘訣
これまで、社内SNSを導入するメリットとデメリットを紹介してきました。最後に、社内SNSの導入を成功させる秘訣を紹介します。
社内SNSを利用するうえでのルールを決める
社内SNSを導入するときは、利用するうえでのルールを決めるようにしましょう。 社内SNSを導入しても、社員の間で浸透しなかったり、公私混同してしまったりすることがあります。そのような問題を未然に防ぐために、業務報告を必ず何時におこなう、これまで使っていた業務報告ツールの利用を停止する、プライベートな発信はしないなどのルールを決めておきましょう。
社員が利用するメリットをつくる
社内SNSを導入するときは、社員が利用するメリットをつくるようにしましょう。 社内SNSは、導入しても社員から受け入れられず、思ったように運用できないということが起こり得ます。目的を持って導入を決めたにも関わらず利用されないのでは、費用の無駄遣いになってしまいます。
社内SNSは社員にとって、日頃の業務をアピールできる場になります。社内SNS上での活動を人事評価の対象にしたりすることで、社員が利用するメリットをつくっておきましょう。
少人数からスタートする
社内SNSは、導入しても思ったように運用されないことが多いツールです。 その背景には、「仕事の人とSNSでつながりたくない」「SNSの使い方がよくわからない」という社員がいることが挙げられます。 そのような人でも社内SNSを無理なく利用できるよう、まずは少人数で導入してみて、起こり得る問題点を解消してから本格的に導入すると良いでしょう。
社内SNSを導入してコミュニケーションを活性化しよう!
いかがでしたか。 社内SNSを導入してコミュニケーションを活性化することで、社内で新たなアイデアが生まれたり、ノウハウが共有されたりといったさまざまなメリットがあります。 社内SNSを導入するメリットとデメリットを押さえたうえで、実際の導入を検討していってください。







