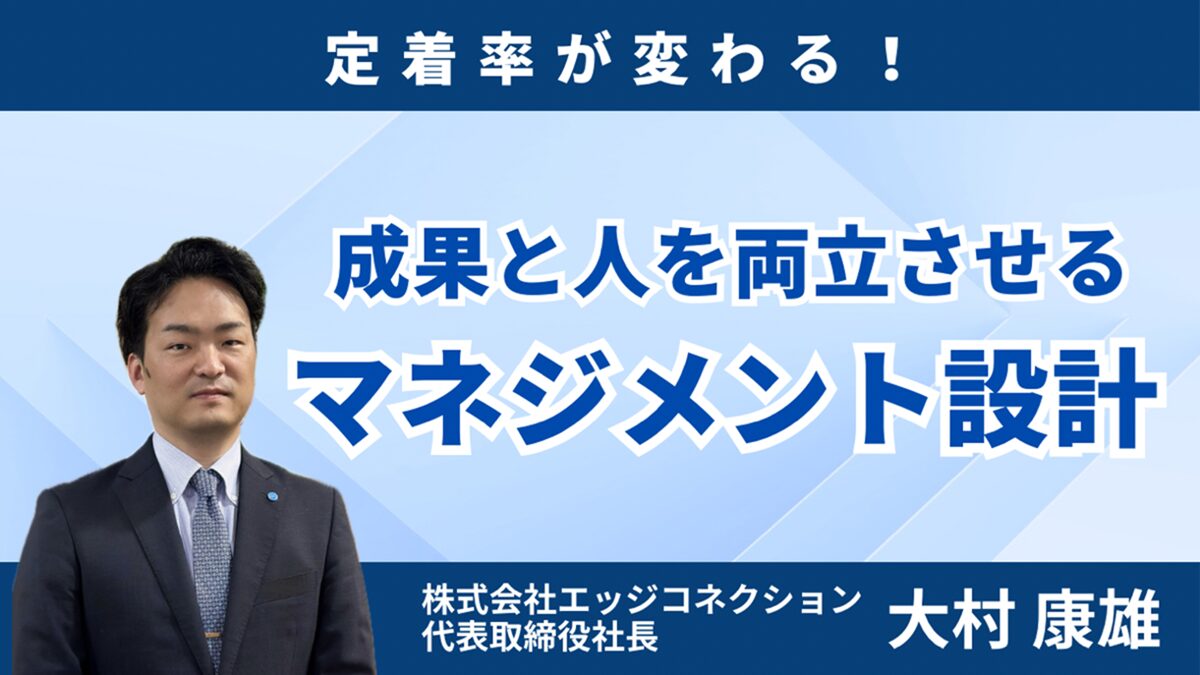
近年、多くの企業で「人材の定着」は経営課題のひとつとしてクローズアップされています。特に、少子高齢化が進む日本では採用そのものが難しくなり、せっかく入社した人材が短期間で離職することのダメージは計り知れません。
現場からは「また採用からやり直し」「戦力化するまでの教育コストが回収できない」といった声があがり、経営層は「育たない・残らない組織では成果も上がらない」と頭を抱えます。
また、リモートワークの浸透や価値観の多様化によって、働く人々の「会社に求めるもの」も変化しました。給与や肩書きだけで引き留められる時代は終わり、心理的安全性や成長実感、仲間とのつながりといった、目に見えない価値が定着のカギとなっています。経営者やマネージャーは、いかにしてこうした要素を設計・運用できるかが問われているのです。

寄稿者大村 康雄氏株式会社エッジコネクション 代表取締役社長
慶應義塾大学経済学部経済学科卒業後、シティバンク銀行(現SMBC信託銀行)入行。2007年、株式会社エッジコネクション創業。営業支援業を軸に、人事・財務課題にも対応するコンサルティング企業として展開。これまでに1700社以上を支援し、継続顧客割合は75%を超える。2024年7月には「24歳での創業から19期 8期連続増収 13期連続黒字を達成した黒字持続化経営の仕組み」を出版。
人が辞める理由は“成果”の有無ではない?
よく誤解されがちですが、「成果を出せないから辞める人」は実は少数派です。むしろ、成果が出ていても辞める人は珍しくなく、逆に成果が出せなくても組織に残る人もいます。では、辞める理由はどこにあるのでしょうか。
当社が面談やアンケートを通じて見えてきたのは、以下のような声です。
・評価が何を基準に決まっているのかわからない
・頑張っても頑張らなくても扱いが変わらない
・話を聞いてもらえない、相談できない
つまり、成果の有無そのものではなく、「自分がどんな状態で、どんな評価を受けているのか」「組織からどんな期待をされているのか」が不透明な状況が離職につながりやすいのです。成果はあくまで一つの指標であり、それ以上に重要なのは、成果を出すための環境がどれだけ整っているかということです。
その基盤となるものは心理的安全性です。成果を出せるか出せないかにかかわらず、「ここで失敗しても大丈夫」「相談できる」「挑戦できる」という安心感がないと、人は疲弊していきます。とくに成果主義が強調される組織では、「成果を出していない自分はダメな人間だ」「相談したら迷惑をかける」と孤立を深め、最終的に離職を選ぶケースが少なくありません。
さらに、周囲との比較も心理的安全性に影響します。例えば同じような成果を出しているのに、Aさんは上司から高く評価され、Bさんはそうでもないという状況が続くと、評価基準への不信感が生まれます。本人は「自分は頑張っているのに評価されない」と感じ、いわゆる「理不尽さ」へのストレスが退職の引き金となります。
一方で、成果が出せなくても組織に残る人には特徴があります。それは「成長の余地が見えている」「周囲との関係性が良好」「挑戦が許されている」という状態です。本人も周囲も、「今はまだ発展途上だが、ここでなら伸びていける」という期待感を持っている場合、人は粘り強く居続けます。
結局のところ、成果の有無そのものは表層的な問題であり、その裏側にある「組織との関係性」「自分の状態の理解」「将来への期待感」が離職か定着かを分けているのです。この構造を理解せず、成果管理だけに注力すると、かえって定着率は下がりやすくなるため注意が必要です。
エッジコネクションの定着アプローチ
エッジコネクションのマネジメント運用の基本にあるのは、「人は成長を実感できる環境では、自然とモチベーション高く働ける」という考え方です。ただ単に成果を追い求めるのではなく、個人が自分の成長を感じ、前向きに努力できる仕組みを組織全体で用意しています。
その中核となっているのがKPI(主要業績評価指標)の見える化と評価の仕組みです。一つ一つの仕事や役割に対して具体的な成果指標を設定し、進捗や達成度を可視化します。これにより、社員は「自分が何を達成できていて、どこが課題なのか」を理解でき、成長の実感を得やすくなります。
しかし、KPIを示すだけで放置すれば、結局は「やれと言われたからやる」という義務感に変わりかねません。そこで当社では、2週間に1回の上司との1on1面談、そして3ヶ月に1回の人事レビューを設けています。
これらは単なる進捗確認の場ではなく、目指すべき方向性がずれていないか、課題や不安が放置されていないかを対話する大事な機会です。相談や軌道修正の場が定期的にあることで、個人が孤立せず、前向きにチャレンジし続けられるようにしています。
また、KPIの数値面だけに偏ると、いわゆる数字至上主義に陥りがちです。そのリスクを防ぐために、当社では行動指針を基準にした定性評価も行っています。例えば、仲間との協力姿勢や学習意欲、誠実さといった内面的な成長の部分も上司がフィードバックし、バランスのとれた成長を支援します。
さらに、誕生日にプレゼントを渡す、毎月3,000円のレクリエーション費用を支給して社員同士の親睦を深めるといった、内面的なフォローにも力を入れています。成長支援は厳しさや負荷を伴う側面があるため、「頑張るための土台としての安心感」も同時に提供することを心がけています。
とはいえ、成長を促される環境であることは間違いなく、それに伴う一定のストレスが発生するのも事実です。そのため、採用段階の会社説明では、「成長を強く求められる会社である」という点をしっかりと伝え、ミスマッチを防ぐようにしています。これにより、入社後に「思っていたのと違った」と感じて辞めてしまうリスクを減らし、より定着しやすい環境を作っています。
小さな組織でもできる今から抑えるべきマネジメント設計のポイント
「うちは小さな会社だから」「人数が少ないから仕組み化は難しい」という声をよく耳にします。しかし、実際には少人数だからこそ効果を発揮するマネジメント設計のポイントがあります。むしろ、人数が少ない分、風通しがよく、設計の浸透が早いため、小規模組織こそ実践しやすいのです。
まず大事なのは、1on1面談の徹底です。大規模組織では制度化しなければ個別対話の機会は生まれにくいですが、少人数組織ならむしろ上司や経営者が直接、週1回または隔週で短い1on1を実施できます。ここでは「何ができたか」「何が課題か」だけでなく、「困っていることはないか」「次に挑戦したいことは何か」といった内面の部分にも耳を傾けることが重要です。
次に、役割と期待の明文化です。少人数ゆえに「あうんの呼吸」で回ってしまう組織も多いですが、それでは誤解や負担の偏りが生じます。「あなたには何を期待していて、どう成長してほしいか」を言語化して共有することで、成長方向のミスマッチを防ぎます。
さらに、数字と行動のバランスを見る意識も欠かせません。KPI管理は有効ですが、それだけでは「結果だけで評価される」と感じさせ、疲弊を生みます。普段の働き方、協力姿勢、チャレンジする姿勢といった行動面のフィードバックを加えることで、成長を前向きにとらえる土壌を作れます。
最後に、心理的な安心感の醸成です。誕生日のお祝い、ちょっとしたレクリエーション補助、雑談の時間。これらは一見業務と関係ないようで、組織の一体感を生み、「ここで頑張ろう」という気持ちを支えるのです。リソースに限りがあるからこそ、コストをかけずにできる工夫を積極的に取り入れましょう。
まとめ:制度だけに頼らない、人が辞めない仕組みとは
最終的に、定着率を左右するのは制度そのものではなく、「制度をどう運用し、人と向き合うか」にかかっています。評価制度やKPI、1on1といった仕組みは確かに重要です。しかし、それを支える日々のコミュニケーション、方向性の共有、内面的なフォローがなければ、制度は形骸化し、逆に不信や不満の温床となってしまいます。
エッジコネクションでは、制度と運用の両輪を回し続けることで、成果と人材定着の両立を目指してきました。成長実感を持てる環境は人を動かし、挑戦を許される土壌は組織の活力を生みます。ただし、その分、成長の痛みやストレスも伴うため、採用段階での丁寧な説明や、入社後のフォロー体制も欠かせません。
企業規模や業種に関係なく、人の成長と組織の成果を両立させるカギは、「人を人として見るマネジメント」にあります。制度だけに頼らず、日々の対話と関わりの中で、期待と安心のバランスをどう作っていくか。それこそが、これからのマネジメント設計の核心だと、私たちは考えています。







