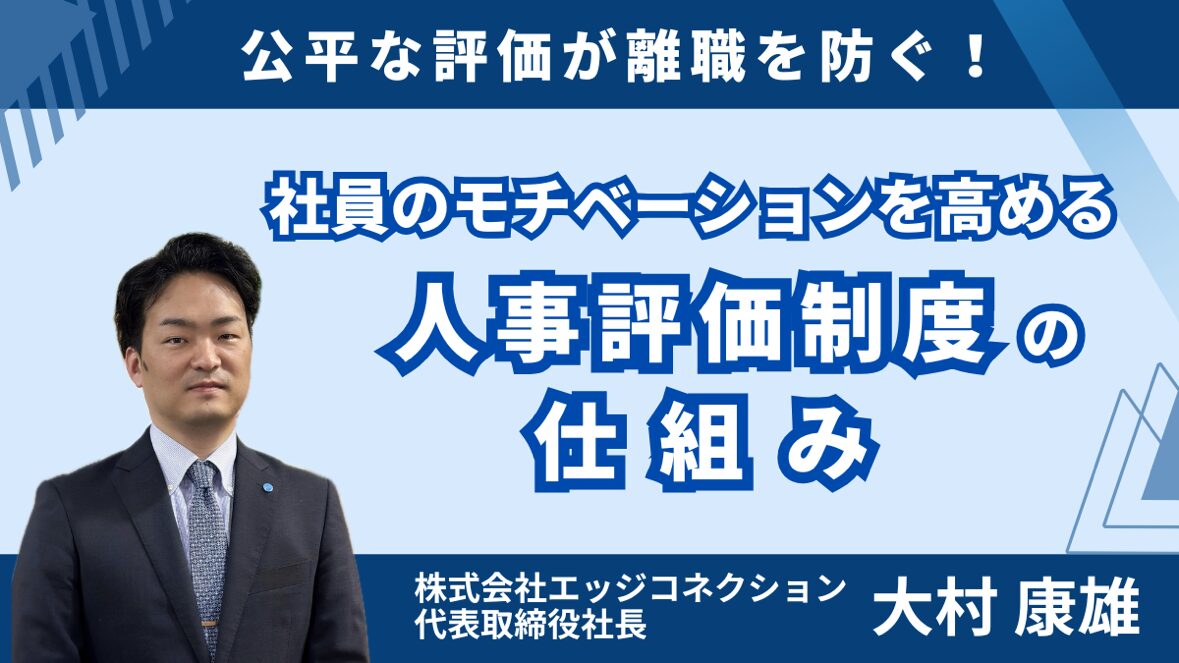
優秀な社員が辞めてしまう理由の一つとして、評価に対する不満が挙げられます。
どれだけ努力しても正しく評価されないと感じれば、モチベーションは下がり、やがて離職へとつながってしまいます。逆に、公正で納得感のある評価制度があれば、社員のやる気を引き出し、組織へのエンゲージメントを高めることができます。
今回は、離職を防ぎ、社員のパフォーマンスを最大限に引き出す「公正な人事評価制度」の仕組みについて、具体的なポイントを交えて解説します。

寄稿者大村 康雄氏株式会社エッジコネクション 代表取締役社長
慶應義塾大学経済学部経済学科卒業後、シティバンク銀行(現SMBC信託銀行)入行。2007年、株式会社エッジコネクション創業。営業支援業を軸に、人事・財務課題にも対応するコンサルティング企業として展開。これまでに1600社以上を支援し、継続顧客割合は75%を超える。2024年7月には「24歳での創業から19期 8期連続増収 13期連続黒字を達成した黒字持続化経営の仕組み」を出版。
目次
1. 評価制度が機能しないと何が起こるか?

企業において、評価制度は社員のパフォーマンスを正しく評価し、適切な報酬を提供するために不可欠な仕組みです。
しかし、この評価制度がうまく機能しないと、社員に多大な不満を生じさせ、その結果、離職率が上昇し、組織全体の成長が停滞するという悪循環に陥ります。
社員の不満
評価制度が公平でない、または透明性が欠けている場合、社員は「自分が正当に評価されていない」と感じます。特に、目に見える成果を上げている社員が十分な評価を受けない場合、次第にモチベーションが低下し、仕事への意欲が失われていきます。
逆に、成果を出していない社員が過度に評価される場合も、周囲の不満を引き起こします。社員の不満は、組織内の雰囲気に影響を与え、チームの士気を低下させる要因になります。
離職率の上昇
社員が自分の努力が報われないと感じると、転職を考えるようになります。
特に、成長意欲が高い社員ほど、キャリアの進展を実感できない環境には耐えられません。その結果、優秀な人材が離職し、組織内に人材の流動が生じます。
離職率が高いと、採用活動や育成のコストがかさみ、組織の安定性が損なわれます。さらに、離職によって知識や経験を持った人材が流出すると、新たに採用した社員が業務を理解し、戦力化するまでに時間がかかります。
このプロセスが繰り返されると、企業の成長に大きな支障をきたします。
組織成長の停滞
社員のモチベーションが低下し、離職が続く中で、企業は新しい人材の確保や育成に注力しなければならなくなります。
このように、評価制度が機能しないと、組織は安定した成長を遂げることができません。優秀な社員が離職していくことで、企業の競争力が低下し、最終的には市場での位置を維持することが難しくなります。
結果として、組織全体のパフォーマンスも停滞し、業績にも悪影響を及ぼします。
2. 公正な評価の仕組み

公正な評価制度は、社員のモチベーションを高めるための基本です。
そして、社員が自分のパフォーマンスに見合った評価を受けていると感じることが、モチベーションを維持するために重要になります。
このセクションでは、評価制度がどのように機能するべきか、特に定量評価と定性評価のバランスについて詳述します。
定量評価と定性評価のバランス
評価制度の中でも、定量評価と定性評価は大きな役割を果たします。それぞれが持つ特徴を理解し、バランスを取ることが公正な評価のカギとなります。
定量評価
定量評価は、数値や成果に基づく評価です。売上や業績など、具体的な数字で成果を示すことができるため、客観的な評価が可能です。
例えば、営業職であれば、月間の売上目標を達成したかどうか、製造業であれば生産量や品質基準の達成度などが定量評価に該当します。定量評価は、社員にとって自分の成果が一目で分かるため、やりがいを感じやすく、モチベーション向上に寄与します。
しかし、定量評価だけでは社員の全体的なパフォーマンスを評価するには限界があります。定量的な成果が良好であっても、チームワークや顧客対応、イノベーションなどの側面は測りきれません。
このため、定量評価だけでは公正な評価が難しくなることがあります。
定性評価
定性評価は、定量的なデータでは測りきれない部分を評価するものです。例えば、社員の態度、リーダーシップ、創造性、協調性などがこれに当たります。
定性評価は、社員がどのように業務に取り組んでいるか、またその過程での行動や態度を重視します。これにより、業績が悪い社員でも、その理由が外部環境やチーム内の協力などの要因である場合に、個々の状況に応じた適切な評価が可能になります。
3. 社員のモチベーション維持の工夫
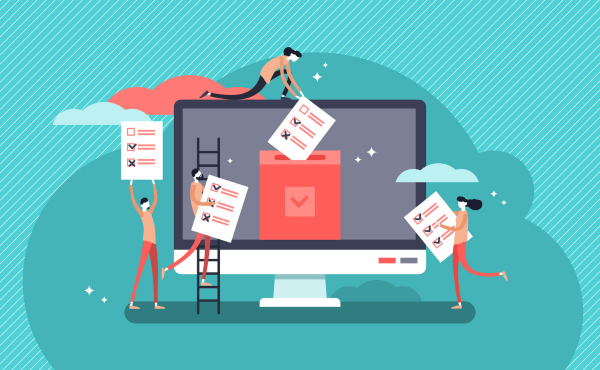
社員のモチベーションを高め、維持するためには、公正な評価に加えて、継続的なフィードバックや目標設定の透明性が重要です。これらの工夫により、社員は自分の成長を実感し、組織に対する忠誠心を高めることができます。
フィードバック制度の重要性
定期的なフィードバックは、社員が自分の仕事に対する理解を深めるために不可欠です。ポジティブなフィードバックを与えることによって、社員は自分の強みを再確認し、さらに努力しようという意欲が高まります。
また、建設的なフィードバックを通じて、改善点や次のステップを明確に伝えることができます。フィードバックは単なる評価の一環ではなく、社員の成長を促進する重要なツールです。
フィードバックは、定期的に行うことが効果的です。年に一度の評価だけでは、社員が改善すべき点や成功のポイントを実感しにくいため、こまめにフィードバックを行う仕組みを導入することが求められます。
また、フィードバックは双方向であることが重要です。上司からの一方的なフィードバックではなく、社員自身からも意見を聞くことで、双方の信頼関係が深まります。
目標設定の透明性
社員のモチベーションを維持するためには、目標設定の透明性が欠かせません。
社員が何を達成すべきか、どのような基準で評価されるのかを明確に示すことが、目標達成に向けた意欲を高めます。透明な目標設定を行うことで、社員は自己評価ができるようになり、目標に向けて努力するための指針を得ることができます。
目標設定には、SMARTの法則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)が有効です。これは、明確で達成可能な目標を設定するためのフレームワークで、以下の5つの要素から成り立っています。
2. Measurable(測定可能):目標を達成しているかどうか測定可能であること
3. Achievable(達成可能):現実的に達成可能であること
4. Relevant(関連性がある):目標と現業の関連があること
5. Time-bound(期限がある):期限が決められていること
SMARTの法則を使うことで、社員が達成に向けた具体的な行動が取りやすく、自分の進捗も確認しやすくなります。また、目標が達成された際には、その成果を適切に評価し、フィードバックを通じて次の目標に向けての意欲を引き出すことができます。
4. 導入企業の事例

人事制度導入前
株式会社A(IT関連企業)では、社員のパフォーマンス評価が非常に曖昧であり、評価基準が一貫していませんでした。
上司の個人的な感情や偏見が評価に影響を与えていたため、社員からの不満が絶えませんでした。特に、営業職の社員が「売上は達成したが、評価が低かった」と感じる場面が多く、業務に対するモチベーションが低下していました。評価が公平でないと感じる社員が多く、優秀な社員の離職率が高かったのです。
さらに、評価基準が定量的ではなく、定性評価だけに頼っていたため、成果を具体的に示すことが難しく、評価の透明性に欠けていました。このような状態では、社員のやる気や組織の成長が停滞し、業績にも悪影響を与えていました。
人事制度導入後
株式会社Aは、評価基準を「SMARTの法則」に基づいて再構築し、定量評価と定性評価のバランスを取ることにしました。
具体的には、売上や成果の達成度を定量的に測定し、社員の行動や態度、協調性などは定性的に評価する形に変更しました。目標設定もSMARTの法則を用い、社員一人一人に具体的で測定可能な目標を設定するようになりました。
さらに、評価は四半期ごとに行い、上司と社員が定期的にフィードバックセッションを設け、評価結果を基に今後の改善点や次の目標を明確にしました。これにより、社員は自分の進捗を把握しやすくなり、達成感を得られるようになりました。
この新しい人事制度の導入により、社員からのフィードバックも改善され、「自分の努力が報われている」と感じる社員が増えたのです。
特に営業部門では、売上目標の達成度が可視化されるようになり、営業スタッフのモチベーションが飛躍的に向上しました。社員の満足度が向上し、離職率も減少しました。
そして、この公正な評価制度は、社員のキャリア成長に対する信頼感を高め、組織全体の業績が改善。人事制度導入前に比べて、社員のパフォーマンスが明確に評価されるようになり、組織の成長が加速しました。
5. 組織拡大にも対応できる運用フロー

組織が拡大していく中で、評価制度を効果的に運用するためのポイントは、標準化と柔軟性のバランスを取ることです。
評価基準やフィードバックの仕組みが統一されていないと、組織全体で公平な評価が行われませんが、同時に各部署の特徴に合わせた柔軟な運用が求められます。
まず、評価基準を標準化することで、全社員が公平に評価される基盤を作ります。
しかし、部署や役職ごとに求められるスキルや成果が異なるため、その特性に合わせた柔軟な評価も必要です。評価フローにおいては、定期的に運用の見直しを行い、改善点を反映させていくことが重要です。
また、システムを活用して評価結果を一元管理することにより、スムーズな運用が可能になります。特に、組織が拡大するにつれて、評価結果をデータとして部署をまたいで活用することが重要です。データを元にした評価によって、より精緻で公正な評価が行え、社員の納得感を高めることができます。
6. まとめ
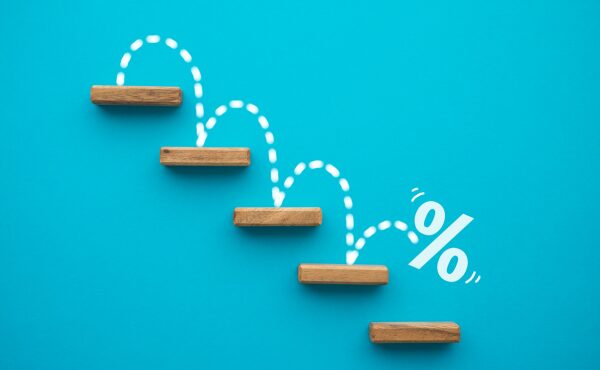
公正な評価制度は、社員のモチベーションを高め、離職を防ぐために不可欠です。
- 定量評価と定性評価のバランスを取ることが、公正な評価のカギ
- 継続的なフィードバックと透明な目標設定が、社員の成長意欲を高める
- 評価制度を標準化しつつ、柔軟な運用を取り入れることで、組織の成長を支える
適切な評価制度を整えることで、社員の働きがいを向上させ、組織全体の成長を促すことが可能になります。自社の評価制度を見直し、持続的な成長を目指しましょう。







