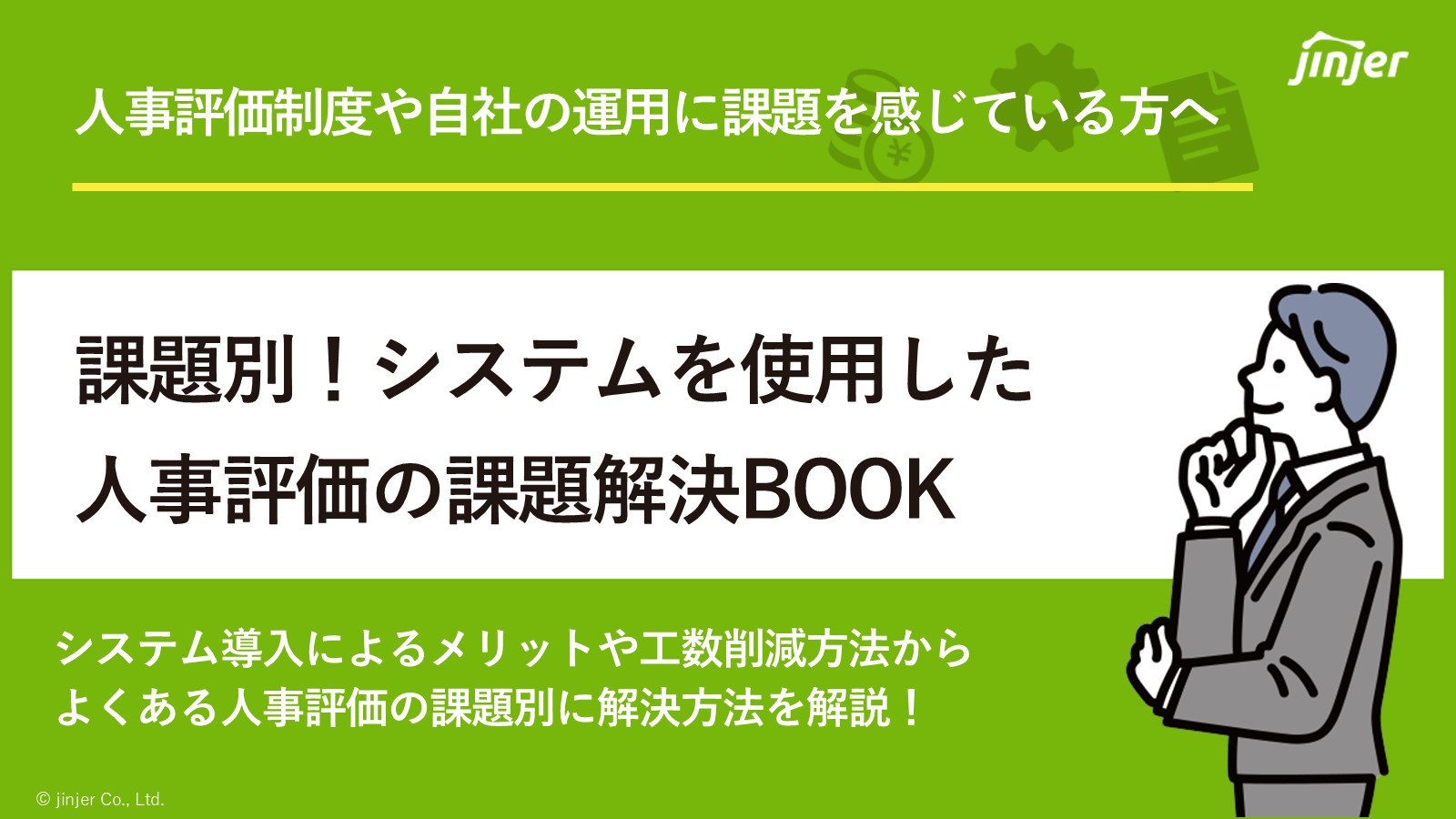「意識改革の重要性は?」
「意識改革を効率的におこないたい」
上記のような疑問や悩みを抱えていないでしょうか。意識改革とは、企業が目標を達成するために価値観や考え方を変え、実際に行動に移すことです。
意識改革は、企業全体で取り組むことで効果が発揮されます。そのため、上層部だけが懸命に取り組んでも意味がありません。
本記事では、意識改革とは何か、重要性やおこなう目的を解説します。意識改革を効率的におこなうポイントも紹介するので、意識改革の取り組みを検討している方はぜひ参考にしてください。
人事評価は、従業員のモチベーションや生産性に直結するため、正しく制度化され運用されていることが欠かせません。労働人口の減少が問題視される昨今では、優秀な人材を採用し定着させること、従業員エンゲージメントを高めることが、企業の成長に繋がるためです。
しかしながら「工数がかかる割には、人事評価をうまく制度化できていない」「制度自体はあるけれど、評価結果を活かせていない」」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当サイトは、そんな人事担当者に向けて「課題別!システムを使用した人事評価の課題解決BOOK」を無料配布しています。
資料では、人事評価の仕組みや手法の種類など基礎的な解説から、実際に企業が抱えている、よくある人事評価の課題別に解決方法をわかりやすく解説しています。
「人事評価の制度を見直したい」「人事評価の課題を解決したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
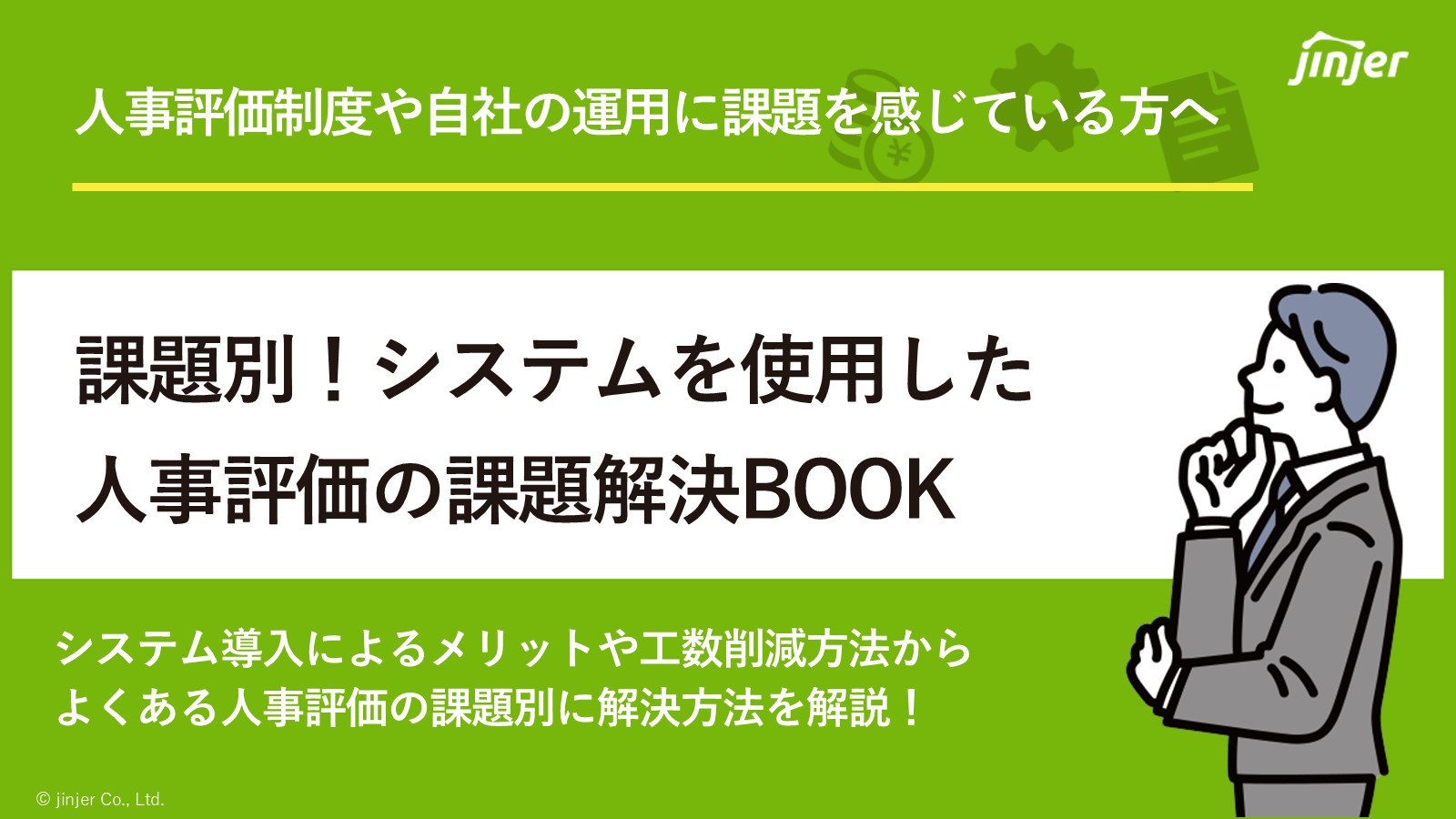
1. 意識改革とは

意識改革とは、企業が目的を達成するために、価値観や考え方、行動パターンを新しいものに変えることです。従来の固定観念や習慣を見直し、より効果的な行動様式に移行します。
意識改革は、ビジネス・教育・社会問題・個人の成長など、さまざまな分野でおこなわれます。意識改革をおこなうことで、企業全体や従業員一人ひとりが、これまでとは違った考え方や価値観を持って業務に取り組めるでしょう。
2. 意識改革の目的

意識改革をおこなう目的は以下のとおりです。
- 業績アップを目指すため
- 生産性やパフォーマンス向上のため
- 働き方を見直すため
2-1. 業績アップを目指すため
意識改革をおこなう目的の一つは、企業の業績アップを目指すためです。意識改革をおこなうことで、従業員の行動や仕事への取り組み方を変えていきます。
例えば、従業員が効率的に働く意識を持つことによって、無駄なプロセスや時間を削減し生産性が向上します。コスト削減や利益率の向上となり、結果として業績アップにつながるでしょう。
2-2. 生産性やパフォーマンス向上のため
生産性やパフォーマンスの向上を目的として、意識改革をおこなうこともあります。従業員が新しい価値観や行動様式を取り入れることで、業務の効率性が向上し、企業全体の生産性が向上することが期待できるでしょう。
重要なのは、従業員一人ひとりが同じ目的意識を持つことです。管理職や経営層だけが率先しておこなっても、従業員が目的の意味を把握しておらず、ただ従う状態では意味がありません。
2-3. 働き方を見直すため
働き方を見直すことを目的に意識改革がおこなわれることもあります。現代のビジネス環境では、リモートワークやフレックスタイムの導入など、柔軟で効率的な働き方が求められているためです。
働き方を見直す際は、企業に根付いている風土や文化を変える必要があります。企業が従業員の身体の健康やメンタルヘルスにも配慮することで、従業員のモチベーションが向上し、長期的な業績向上や持続可能な労働環境を実現できるでしょう。
3. 意識改革のメリット

意識改革のメリットは以下のとおりです。
- 生産性が向上する
- 優秀な人材の確保につながる
3-1. 生産性が向上する
意識改革をおこなうことで、生産性の向上につながります。従業員の業務に対する意識改革をおこなえば、業務の無駄が減り、仕事がスムーズに進むためです。
業務に対する意識を向上させることで、個々の責任感も強くなるでしょう。意識改革によって組織全体がより効率的に機能するようになり、生産性の向上につながります。
3-2. 優秀な人材の確保につながる
意識改革をおこなうことで、優秀な人材の確保につながります。従業員が魅力を感じる企業文化や働きやすい環境を整えることが、優秀な人材を惹きつける鍵となるためです。
例えば、ワークライフバランスを重視した働き方を提供すれば、従業員のエンゲージメントが向上するでしょう。企業文化が改善されることで、社会的な評価が高まり、優秀な人材が集まりやすくなります。
従業員が企業に対して魅力を感じていれば、離職率の低下も期待できるでしょう。
4. 意識改革のデメリット

意識改革のデメリットは以下のとおりです。
- 従業員のモチベーション低下を招く可能性がある
- 意識改革には時間がかかる
4-1. 従業員のモチベーション低下を招く可能性がある
意識改革は、従業員のモチベーション低下を招く可能性があります。意識改革の目的やメリットが従業員に伝わっていなければ、従業員は「押し付けられている」と感じる場合があるためです。
また、従来のやり方に慣れ親しんでいる従業員や、変化を嫌う従業員がいた場合、意識改革に対して抵抗感を抱くことがあります。
従業員が意識改革の必要性を理解していない場合、積極性がなくなり、かえって生産性が低下するおそれがあるでしょう。
4-2. 意識改革には時間がかかる
意識改革をおこない、結果として効果が現れるまでには一定の時間がかかります。意識改革に即効性はないため、長期的に取り組まなければなりません。
新たな考え方が企業内に浸透するまでには時間がかかり、一時的に生産性が低下するリスクも把握しておく必要があります。企業は、従業員が慣れるまで継続的なサポートをおこなわなければなりません。
5. 意識改革の問題点

意識改革の問題点として、経営層と従業員の認識の齟齬が挙げられます。経営層にとって意識改革が必要と考える問題でも、従業員は問題と思っていないケースがあるためです。
経営層と従業員の意識改革に対する認識の齟齬がある場合、経営層が一方的に意識改革をおこなっても意味がありません。また、経営層が新たなルールを策定しても、ルールを遵守することが「指示」になるため、意識改革とは呼べないでしょう。
さらに、従業員同士で意識改革への取り組みに温度差が生まれることも考えられます。従業員一人ひとりが改革の必要性を理解し、真摯に取り組まなければ、企業全体の意識改革は無意味なものになります。
6. 意識改革の方法

意識改革は、以下の手順でおこないます。
- 企業の課題を認識し目的を明確化する
- 行動に落とし込む
- PDCAを回す
6-1. 企業の課題を認識し目的を明確化する
まずは、企業の課題を認識し、意識改革をおこなう目的を明確にします。なぜ意識改革が必要なのか、どのような変化を求めているのかを具体的にしましょう。
現在の組織文化や従業員の意識、業務プロセスなどを分析します。従業員にアンケートを取ることも、企業の問題点を洗い出す有効な手段の一つです。
6-2. 行動に落とし込む
意識改革を実現するための具体的な戦略やプランを立て、実際に行動に落としこみます。意識改革を推進するために、リーダーを選任しましょう。
上層部や管理職が率先して取り組むことが重要です。意識改革に必要な知識や、新たなスキルを身につける必要がある場合は、研修などを積極的におこないましょう。
従業員が新しい価値観や行動を取り入れるためのサポートをおこない、実践できる場を提供することが重要です。
6-3. PDCAを回す
意識改革は一度きりのプロジェクトではなく、継続的におこなう必要があるため、PDCAを回していくことが重要です。最初からすべてが思い通りにうまくいく施策は、ほとんどありません。
進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて改善策を講じましょう。意識改革の成果や改善策はすべての従業員に共有し、チームの一員であることの意識を持たせることが重要です。
7. 意識改革を効率的におこなうためのポイント

意識改革をおこなうためのポイントは以下のとおりです。
- 達成可能な小さな目標からスタートする
- 目標達成までに時間がかかることを理解しておく
まずは、組織全体が一丸となって、共通意識を持つことが重要です。さらに、上記のポイントを押さえることで、意識改革を効率的におこなえるでしょう。
8. 意識改革の成功事例

意識改革の成功事例として、大手自動車会社(A社)が挙げられます。A社は、2000年代に自動車の年間販売台数を急激に伸ばしていましたが、人材育成に伸び悩んでいました。
業績の向上を目指した結果、教育にほころびが生じていたといいます。そこで、A社の社長は大規模な教育改革を打ち出し、人材育成の再構築を目指しました。具体的には、従業員を細かいグループに分け、上司が部下を指導しやすい体制に変えていったのです。
A社の意識改革は、最初からすべてがうまくいったわけではありません。例えば、上司と部下の年齢差があり、コミュニケーションのギャップが生じていました。上司から部下に対する「今どきの若者は」などの意識が、企業内で深刻な問題となっていたようです。
上記のような問題意識を踏まえながら、企業は若手に期待したい能力や資質の定義づけを少しずつおこなっていきました。その結果、教えられる側だけではなく、教える側の責任感も高まり、組織全体のパフォーマンス向上につながったといいます。
A社の事例のように、意識改革をおこなっても新たな問題が出てくることも十分に考えられます。定期的に問題点を見直し、改善策を講じることが重要といえるでしょう。
9. 意識改革により組織の変化を促そう

意識改革は、企業の業績アップや生産性の向上、働き方を見直すために重要な取り組みです。重要なのは、経営層と従業員が意識改革に対する共通の認識を持つことです。
PDCAを回しながら、必要に応じて改善策を講じることで、徐々に成果が見えてくるでしょう。意識改革は、長期的な取り組みであることも忘れてはいけません。
企業の持続可能な成長のためにも、組織の変化を促しましょう。
人事評価は、従業員のモチベーションや生産性に直結するため、正しく制度化され運用されていることが欠かせません。労働人口の減少が問題視される昨今では、優秀な人材を採用し定着させること、従業員エンゲージメントを高めることが、企業の成長に繋がるためです。
しかしながら「工数がかかる割には、人事評価をうまく制度化できていない」「制度自体はあるけれど、評価結果を活かせていない」」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当サイトは、そんな人事担当者に向けて「課題別!システムを使用した人事評価の課題解決BOOK」を無料配布しています。
資料では、人事評価の仕組みや手法の種類など基礎的な解説から、実際に企業が抱えている、よくある人事評価の課題別に解決方法をわかりやすく解説しています。
「人事評価の制度を見直したい」「人事評価の課題を解決したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。