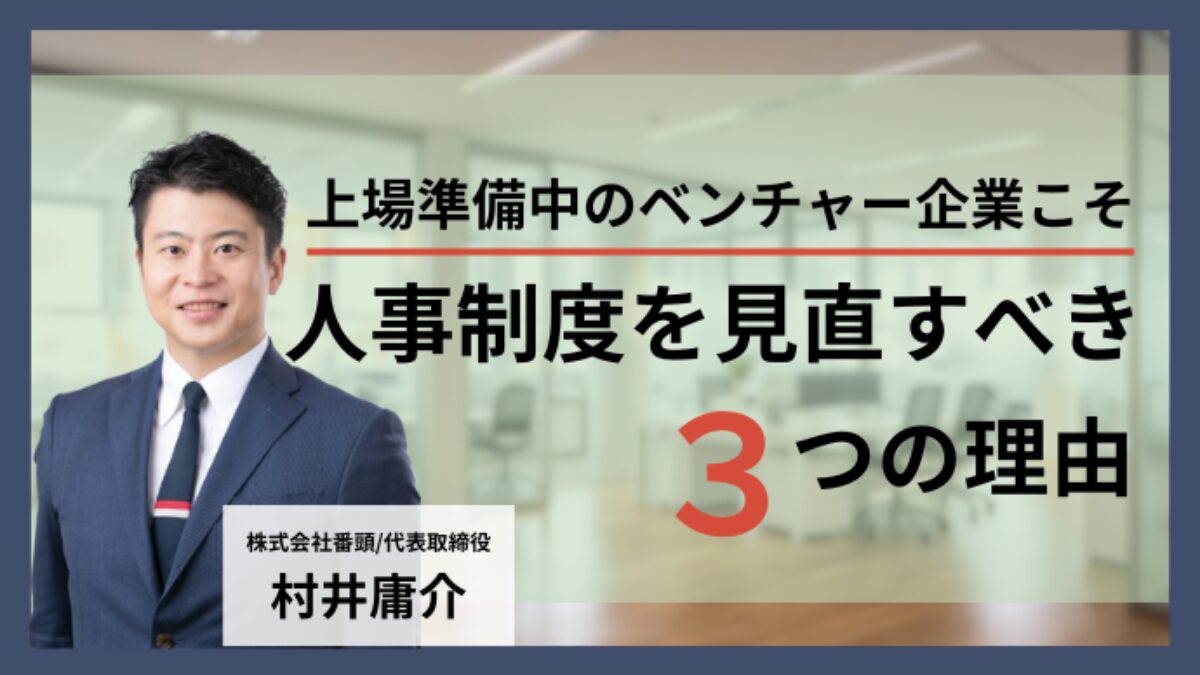
「最近、うちの人事制度を見直したのはいつだっけ?」
上場準備中のベンチャー企業とお話ししていると、よくこんな声を耳にします。
事業は猛スピードで拡大し、社員数もあっという間に倍々で増えていくものの、創業期につくった人事制度は「とりあえず作ったきり」でほぼ手つかず……。
気がつけば制度が時代遅れになり、社員のモチベーションを下げたり、将来のIPOに向けた組織体制の整合性を損なっていたりするケースは珍しくありません。
実は、上場準備中こそ人事制度のアップデートが最大の効果を発揮します。組織が急拡大するベンチャーだからこそ、制度を今の事業戦略や組織の実態に合わせて作り直すことで、業績と組織活性を同時に引き上げるチャンスを得られるのです。
そこで本記事では、「なぜ今こそ人事制度を見直すべきか」を3つのポイントに絞ってご紹介します。実際に上場準備期の企業で組織刷新を行った事例も交え、すぐに活かせるヒントをお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

執筆者村井 庸介氏株式会社番頭 代表取締役
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し,通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中で,グリー株式会社にて人事制度設計に携わった。2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
目次
1. 放置されがちな人事制度が、上場のブレーキになる
 「ベンチャー企業はスピード優先だから、人事制度は後回しでいい」
「ベンチャー企業はスピード優先だから、人事制度は後回しでいい」
そんな考えが根強く、実際に人事制度をほぼ手つかずのまま放置している企業は少なくありません。ところが、上場を目指すうえでは社内統制の強化や人件費の整合性を投資家に示す必要があり、制度が曖昧だと「成長のブレーキ」にさえなりかねないのです。
とはいえ、創業期は事業づくりや資金調達に目を向けがちで、本格的な人事制度設計にまで手が回らないのは仕方ありません。さらに、経営者自身が人事に詳しくないケースも多く、過去在籍していた会社の制度を流用している……そんな状況に陥りやすいのも事実です。
しかし、「事業と組織は一体」です。
組織づくりの軸となる人事制度がおろそかになると、いざ上場準備段階で「古い制度」が組織の足を引っ張る可能性があります。
たとえば、
- 「業績が良いから」とボーナスも昇給も無計画に与える
- 「ポジションが埋まっている」という理由で若手が昇格できない
といった状態が続くと、人件費や昇給ルールの説明が投資家に対して不透明になったり、有望な人材の定着率が低下したりしてしまうのです。
このように創業期の勢いに任せて制度を後回しにしてきたツケは、上場準備期になってから一気に表面化します。だからこそ、事業と組織を同じベクトルで伸ばすために、今こそ人事制度をアップデートするタイミングなのです。
2.「見直し」で得られる3つのメリット
 「古いままの人事制度を放置すると組織が停滞する」と分かっていても、具体的にどんな恩恵があるのかが見えないと動きづらいものです。そこで、上場準備期の今こそ人事制度を見直すことで得られる3つの大きなメリットを紹介します。
「古いままの人事制度を放置すると組織が停滞する」と分かっていても、具体的にどんな恩恵があるのかが見えないと動きづらいものです。そこで、上場準備期の今こそ人事制度を見直すことで得られる3つの大きなメリットを紹介します。
(1)組織を健全にデトックスできる
企業が成長すれば、求められる役割やスキルは刻々と変化します。ところが昔のままの人事制度を放置していると、実態と制度が乖離し、古参社員の滞留や新しい人材の参入障壁を生み出しがちです。
そこで「何を評価するか」を明確にし、事業戦略にマッチした人材を適切に評価・抜擢できる制度にリニューアルすれば、自然と組織の新陳代謝が進むようになります。ときには古参社員が反発して退職するケースもありますが、多くの場合は彼らも新天地で力を発揮できるため、結果として社内外ともにWIN-WINなデトックス効果を生むのです。
(2)上場後を見据えたリスクヘッジになる
上場後は投資家から「人件費の妥当性」や「評価の透明性」について厳しくチェックされます。たとえば、「なぜこの社員がその給与なのか」という説明が曖昧だと、IPO審査でガバナンスや管理体制の不備とみなされ、審査プロセスが長引くリスクもあります。
さらに、上場後のブランド力を活かし、これまで獲得できなかった人材層にもアプローチしやすくなる一方、昔の給与レンジや等級を使い続けていると好機を逃してしまう可能性も。だからこそ、今のうちに等級・昇給ルールを見直しておくことが、上場後の人材戦略を成功に導くカギとなるのです。
(3)実は一番重要!業績アップへの強力なドライバー
人事制度は「社員を縛るためのルール」ではなく、一人ひとりの力を引き出し、業績に結びつける仕組みです。評価や報酬の設計が整えば、会社が何を求めているのかが分かりやすくなり、社員の行動力と成果が飛躍的に向上します。
実際、前章で紹介した企業でも、管理職ポジションの固定化を解消して若手を抜擢した結果、営業戦略の実行力が劇的にアップ。売上や利益は120%超の予算達成を果たし、離職率も改善しました。さらにその評判が広がり、新卒や中途の採用も活性化したのです。
3.成果を加速させる仕組み等級・評価・報酬の再点検

これまでメリットについて解説してきましたが、そうすると「メリットは理解できたものの、具体的に何から着手すればいいのか?」といった疑問が生まれてきます。
そこで、本章では「等級・評価・報酬」という人事制度の3要素を再点検するポイントを解説します。
①等級
社員を役割やスキル、職務内容などに応じて「どの階層に属するのか」を整理する仕組みです。ここが曖昧だと、誰がどんなレベルの仕事を期待されているか分からなくなります。特に重要なのは、昇格要件の明確化です。
- “古参社員の固定化”で組織が硬直するのを防ぐ
- 若手が昇格できる道筋をつくる
など、新陳代謝を促すうえでも要チェックといえます。
②評価
「どんな行動・成果を評価するのか」「評価プロセスをどう進めるのか」を決める枠組みです。
数字や報酬だけを追う組織は、景気の波にさらされやすく、人材が定着しにくくなりがち。
- 数字と同じくらい、“バリュー”や“協力姿勢”など長期的成長を生む行動も評価する
- 成長期ベンチャーなら評価サイクルを短めにして、抜擢しやすい仕組みをつくる
といった工夫が、事業戦略を支える要因になります。
③報酬
給与テーブルや賞与、インセンティブなど「社員をいかに報いるか」を定める部分です。ここがズレると、会社が望む行動と実際の社員の動機づけが噛み合わなくなります。
たとえば、「長期的に技術力を蓄えてほしい」のに、短期成果だけを重視した報酬設計だと、誰も長期施策に手を出さなくなるそんなミスマッチは少なくありません。
上場準備中のベンチャーなら、これら3要素をゼロベースで点検し、経営戦略との整合性を確かめることが大切です。特に「将来こうありたい」「何を成し遂げたい」といった経営陣のビジョンを落とし込むことで、制度そのものが“経営の後押し”をする仕組みに変わります。
4.ビジョンと戦略を映す“評価”こそが組織を強くする
 等級・評価・報酬の3要素のなかでも、組織全体への影響力が最も大きいのは“評価制度”です。なぜなら、評価制度が社員の給与や昇格とダイレクトにつながるだけでなく、評価基準やプロセスが日々の行動を左右するからです。
等級・評価・報酬の3要素のなかでも、組織全体への影響力が最も大きいのは“評価制度”です。なぜなら、評価制度が社員の給与や昇格とダイレクトにつながるだけでなく、評価基準やプロセスが日々の行動を左右するからです。
ここでは、上場準備期にこそ見直したい「評価の目的」と「設計のポイント」を解説します。
上場準備期だからこそ、評価の“目的”を明確に
評価制度の導入でよくある失敗パターンは、
- なんとなく成果主義
- 細かい評点で管理しようとしすぎる
- 流行りの絶対評価を採用
など、手段が目的化してしまうケースです。
こうなると、社員は
- 「あれもこれもやれと言われている気がする」
- 「何を優先すればいいのか分からない」
- 「結局、皆同じ評価で差がつかない」
といった不満を感じやすくなります。
ポイントは、定量指標と定性指標のバランスです。多くの企業が売上や利益、プロジェクトのKPIなどの“定量指標”を評価に組み込みますが、それだけだと短期成果を追うばかりで組織が疲弊しがち。
そこで重要となるのが、コンピテンシー評価(役割や等級ごとの行動特性)やバリュー評価(会社が重視する行動規範の実践度)といった定性指標です。
- コンピテンシー評価:役割に必要な行動特性をどの程度実行しているか
- バリュー評価:会社の理念・行動規範をどの程度体現しているか
ただし、項目を闇雲に増やすのではなく、「経営陣が今、いちばん伝えたいメッセージや行動指針」を軸に絞ることで、社員が何をすれば評価されるのか明確になります。
さらに、上場準備中起業の場合は評価サイクルも重要です。業績の急成長が求められるケースが多いため、評価サイクルを短めに設定して小まめなフィードバックでPDCAを回すのが有効です。ただし、新制度を一気に全社へ導入すると混乱しやすいので、管理職への説明やロールプレイを丁寧に行い、目的や運用方法をしっかり共有する必要があります。
上記の通り、細かいポイントはありますが、最も大事なのは、“評価”に経営陣のビジョンが映し出されていることです。
評価制度は、社員に伝えるメッセージの媒体です。たとえば、「上場後は海外事業を拡大したい」という方針があるなら、海外案件への積極姿勢を評価対象に加えることで、自然とグローバル志向の人材が育つのです。
先述のように「組織が硬直化している」と悩んでいた企業でも、“若手の挑戦を後押しする”評価基準に大胆に切り替えたことで、組織に新しいアイデアがどんどん生まれ、今までにないスピードで利益を伸ばしました。
「何を評価するか」=「どの方向に会社を導きたいか」
を明確にしたことで、評価制度が経営陣のビジョンを的確に反映し、組織全体のマインドシフトを起こした好例といえます。
5.まとめ:上場準備中だからこそ、今がチャンス!
 成長の速いベンチャー企業ほど、人事制度は“作りっぱなし”ではなく、現状に合わせてアップデートし続けることがカギになります。
成長の速いベンチャー企業ほど、人事制度は“作りっぱなし”ではなく、現状に合わせてアップデートし続けることがカギになります。
特に上場準備期は、
- 曖昧だったルールを明文化し、投資家への説明責任をクリアにする
- 評価や昇給の透明性を高め、人材のモチベーションと定着率を向上させる
- 組織を健全に新陳代謝させ、ポジティブな変化を取り入れる
といった、組織基盤を固める絶好のタイミングです。ここで手を打たなければ、上場後に慌ててテコ入れする羽目になり、混乱やコストが増すリスクも高まります。
①ベンチャー企業は組織や人事制度が硬直化しやすい
創業メンバーや古参社員の管理職固定化で、若手が力を伸ばしづらい。
②上場後を見据えた制度アップデートが必要
ガバナンスや投資家説明の観点で、整合性ある制度が求められる。
③人事制度の見直しが業績向上を後押しする
等級・評価・報酬をトータルで再設計し、企業ビジョンに合致させれば社員の行動力が上がり成果も飛躍的に伸びる。
繰り返しになりますが、何より大切なのは「経営陣のビジョン・戦略を評価制度としっかり整合させること」。会社が目指す方向を評価の仕組みに落とし込むことで、社員は自分の役割を理解し、自律的に行動して成果を上げられる組織へと成長していきます。
もし今、「うちはまだ大丈夫」と感じているなら、今こそ人事制度を振り返るチャンスです。人事制度は“作ったら終わり”ではなく、“見直すほど進化する”組織の羅針盤。
上場準備中だからこそ、この好機を活かして、強い組織と圧倒的な業績アップを両立させる第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。







