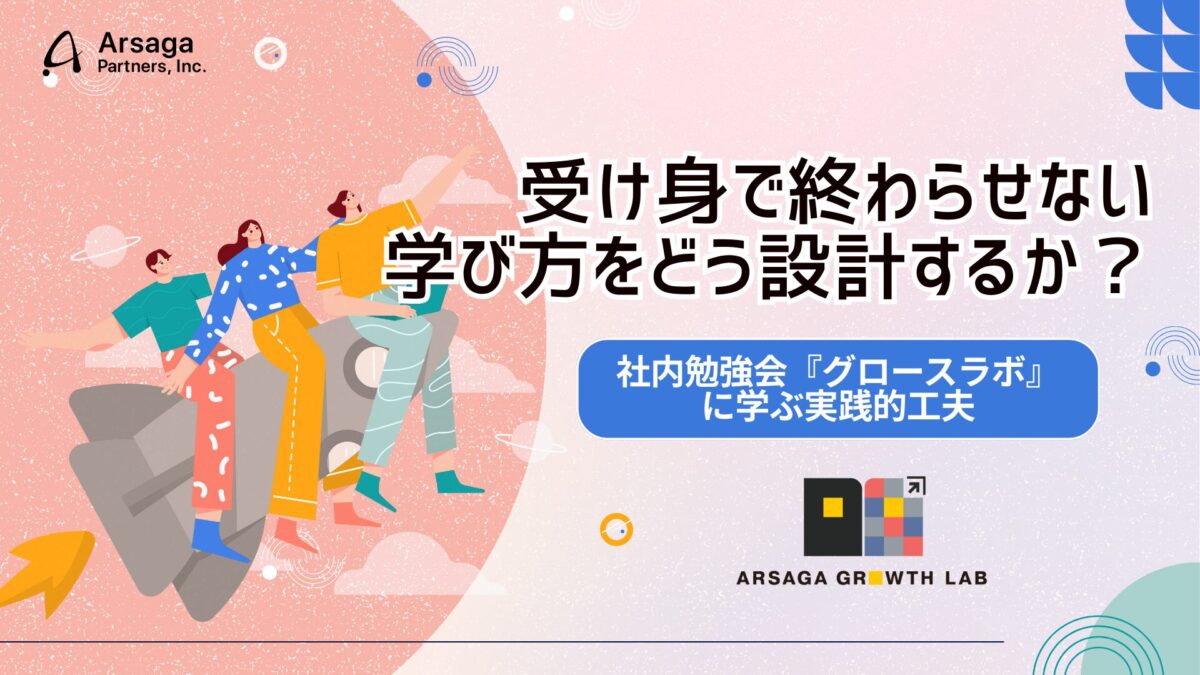
社員教育やスキルアップの一環として社内勉強会を実施している企業は多くありますが、「講師の話をただ聞くだけ」で終わってしまい、学びが十分に深まらないケースは少なくありません。
アルサーガパートナーズが取り組む社内勉強会「グロースラボ」は、そうした“受け身の学び”からの脱却を目指した実践型のプログラムです。少人数制やディスカッション重視といった仕掛けを取り入れることで、知識の習得だけでなく、思考力や主体性まで育む設計がなされています。
本記事では、その背景や具体的な工夫、そして参加者の声から見える成果をご紹介します。
目次
なぜ「受け身で終わらせない学び」が必要なのか?
一方的な講義形式では、どうしても“聞くだけ”にとどまりやすく、知識の定着が難しくなります。メモを取っていたとしても、その後に活用されないまま記憶が薄れてしまうことも多いでしょう。こうした受け身の学びでは、知識が定着しにくく、実務に結びつきにくいという課題が生じます。
さらに、社内勉強会は本来、知識共有だけでなく社員同士の交流や相互理解を深める機会でもあります。しかし、発言や参加の機会が限られた形式では、そうした効果も十分に得られません。
そこで、アルサーガパートナーズの「グロースラボ」では、全員が意見を出し合い議論するスタイルを取り入れています。自ら考え、言葉にし、他者の視点を取り入れるプロセスを経ることで、学びの質と量が大きく変わります。この主体的なサイクルこそが、記憶の定着を促し、スキル向上や行動変容へとつながっていくのです。
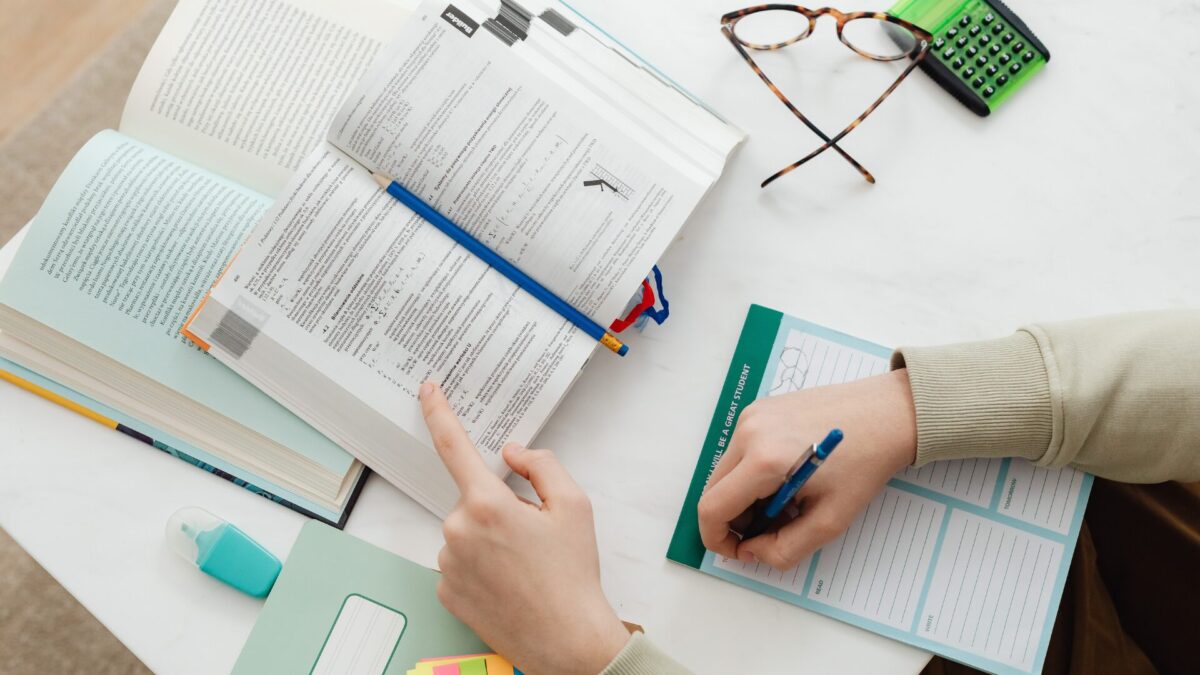
「グロースラボ」誕生の背景:受け身を脱するための挑戦
「グロースラボ」は、コロナ禍で社員同士のコミュニケーションが希薄になったことをきっかけに誕生しました。フルリモートでの働き方が当たり前になる中で、「学びの場ですらも受け身にとどまってしまうのではないか」という懸念があったのです。
そこで着目したのが、ディスカッションを中心とした学習スタイルでした。誰かの話を聞いて終わるのではなく、自分の考えを言葉にし、他者と意見を交わす。そのプロセスにこそ、知識を実践へと変える真の学びがあると考えたのです。
こうした理念をもとに、「グロースラボ」は少人数制で全員が発言できる勉強会として設計されました。単なる知識の共有にとどまらず、社員一人ひとりが主体的に学び、多様な視点から刺激を与え合う場へと進化してきたのです。

受け身を脱する4つの工夫ポイント
1.少人数制(5人)による発言しやすさの確保
「グロースラボ」では、1回あたりの勉強会を5人という少人数で実施しています。これは、心理学で言われる「リンゲルマン効果(人数が増えると一人あたりの関与度が下がる現象)」を避けるための工夫です。
実際、参加者からは「発言しやすかった」「少人数なので安心して話せる」といった声が多く寄せられており、学びの質を高める雰囲気づくりにつながっています。
2.講師も社員が担当し、テーマ選択の自由度を確保
「グロースラボ」の講師は、外部の専門家ではなく、社員が担当します。特別な資格や条件はなく、自らが選んだテーマで自由に登壇できるのが特徴です。
その結果、「講師=教える人」「参加者=教わる人」といった固定的な関係ではなく、互いに学び合うフラットな空気が自然と生まれています。
3.ディスカッション中心の設計
座って話を聞くだけではなく、考え、発言し、議論する。グロースラボの設計では、この「アウトプット」を重視しています。
テーマによっては、事前に資料を用意したり、参加者に問いを投げかけたりと、対話を促す仕掛けも多彩です。こうしたディスカッションを通して、知識の習得だけでなく、思考の深掘りや言語化力といった実践的なスキルが自然と磨かれていきます。
4.参加者の業種・部署制限なしで多様な視点を取り入れる
もう一つの特徴は、参加者を特定の業種や部署に限定しないこと。テーマがITやエンジニアリングに関する内容であっても、興味さえあれば誰でも参加できます。
これにより、「自分には関係ない」と感じていたテーマから新しい発見を得たり、他部署のリアルな課題を知ることで気づきが生まれたりと、多様な学びが広がっていくのです。

実践テーマの具体例とその意義
実際に「グロースラボ」で取り上げられるテーマは、どれも実務に直結する内容です。参加者が日々の仕事の中で抱える課題や関心に根ざしているため、学びをすぐに活用できる点が特徴です。
業界あるあるや失敗事例の共有
現場で実際に起こった失敗や苦労話を題材にし、「何を学び、どう立て直したのか」を議論します。共通の失敗を再び繰り返さないためのヒントが得られるだけでなく、経験をオープンに語り合うことで心理的な安心感も醸成されます。
プロジェクトマネジメントの課題と解決策
クライアント対応やタスク管理など、実務で直面しやすい課題を深掘りします。成功事例と失敗事例を比較することで、実務に直結した知見が共有され、明日からの働き方にすぐに反映できる点が大きな意義です。
コミュニケーション力や提案力の強化
話し方や聞き方、プレゼンテーションの工夫など、ソフトスキル向上を目的としたテーマも人気です。こうしたテーマは、部署や職種を超えて共通の学びにつながりやすく、社内のコラボレーション強化にもつながっています。
生成AIなどの最新トピックへの対応
変化の速い業界に合わせ、生成AIやプロンプト技術などの最新テーマも柔軟に取り上げています。新しい技術を学び合う場があることで、個人のスキルアップだけでなく、組織としての適応力強化にも寄与しています。
どのテーマも「今すぐ仕事に活かせる」ことが重視されており、参加者の関心やモチベーションにもつながっています。実務に直結する知識を共有しつつ、社員同士の相互理解や横のつながりを強める効果も発揮しているのです。
参加者の声から見る「受け身で終わらない学び」の効果
「グロースラボ」の開催後には、毎回参加者からのフィードバックが寄せられます。そこから見えてくるのは、参加者自身の学び方や意識そのものの変化です。
経験談が学びをリアルにする
「講師の失敗談が印象に残った」という声が多く聞かれます。リアルな体験が語られることで、単なる知識ではなく自分ごととして捉える姿勢が生まれています。
言葉にすることで理解が深まる
「自分で説明してみて初めて理解できた」「曖昧だった知識がクリアになった」という感想も寄せられています。参加者自身が積極的にアウトプットすることで、理解が深まり、学びが定着しているのです。
他職種の視点で考え方が広がる
部署の枠を超えた交流により、「自分の部署だけでは気づけなかった視点を得られた」という声もあります。多様な背景を持つメンバーとの対話が、発想の幅や問題解決のアプローチを広げています。
積極的に発言し議論に参加する
堅苦しくない雰囲気の中で、参加者同士が自然に意見を交わすようになり、自分から議論に加わる姿勢が生まれています。安心して意見を言い合える環境が整っていることで、参加者が主体的に学びに向き合う姿勢が育まれています。

まとめ:他社でも実践可能なポイントと注意点
「グロースラボ」のような仕組みは、特別な予算やスキルがなくても実現可能です。重要なのは「設計の意図」と「運営の姿勢」だといえるでしょう。
- 少人数での対話形式にすることで、自然と発言が生まれる
- 講師役を社員に任せることで、主体性や多様なテーマが広がる
- 実務に直結するテーマを選ぶことで、参加者の関心と学習意欲が高まる
- ディスカッションの時間を十分に確保することで、全員参加型に
これらのポイントを押さえることで、どんな企業でも「受け身で終わらない学び」の場を設計できるはずです。
今後の展望と学びの文化形成への示唆
「学ぶこと」自体を目的にするのではなく、日々の仕事の中で自然と学びが深まる。グロースラボが目指すのは、そんな文化を社内に根づかせることです。
肩書きや部署を越えて自由に語り合い、お互いの視点から学び合う。特別な研修制度ではなく、業務と地続きの中で育まれる学びの場。そのあり方が、社員の成長だけでなく、組織全体の活性化にもつながっています。
「グロースラボ」は今後も定期的に開催し、アルサーガパートナーズの「人をつくる」というミッションを、現場で体現し続けていきます。「グロースラボ」について詳しく知りたい方や、開催の様子・参加者の声は、以下の記事でご覧いただけます。
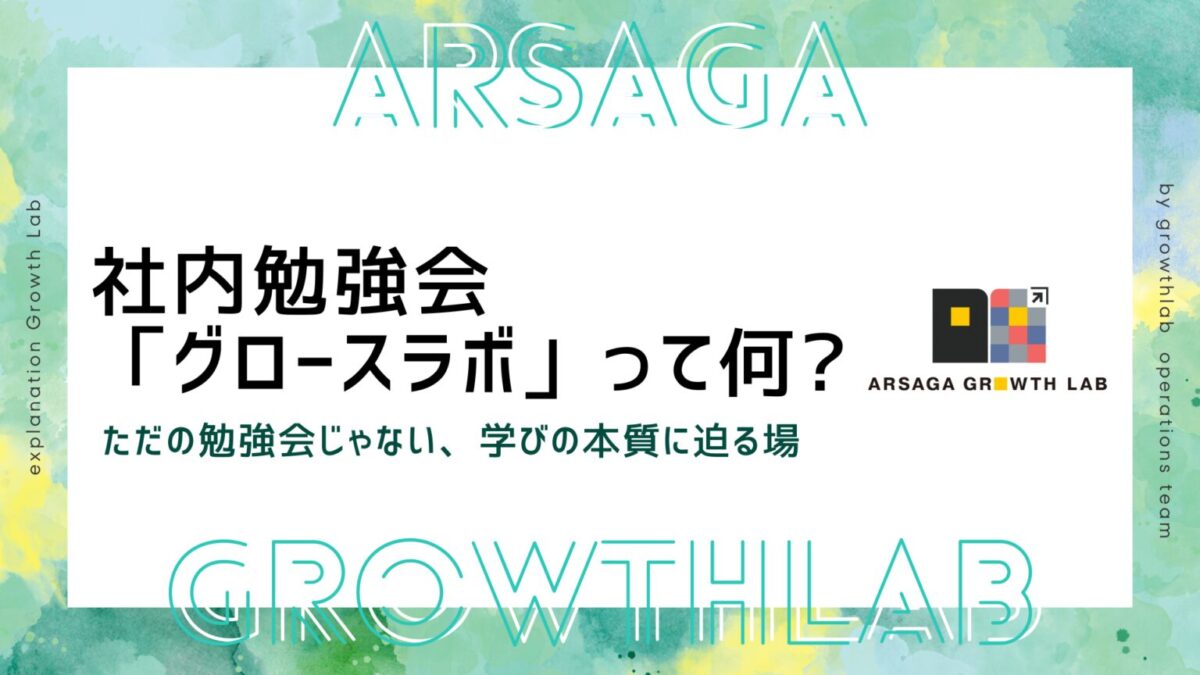
社内勉強会「グロースラボ」って何?ただの勉強会じゃない、学びの本質に迫る場
一般的な勉強会やセミナーでは、講師が一方的に話すスタイルが多いと思います。そうした形式に、どこか退屈さを感じたことはありませんか?アルサーガパートナーズで定期的に開催されている「アルサーガグロースラボ(以下、グロースラボ)」は、受け身になりがちな学びのスタイルに、ちょっとした変化を加えた勉強会です。講師と参加者がディスカッションしながら、一つのテーマについて意見を交わす場。聞くだけではなく、発言し、議論することで学びを深める機会を提供しています。

社内勉強会「グロースラボ」通信 2025年2〜4月号
アルサーガパートナーズでは、「人をつくる」をミッションに掲げ、「学びの場はどうあるべきか?」という問いに日々向き合っています。その取り組みのひとつが、社内勉強会「グロースラボ」。社員同士が学び合い、語り合い、挑戦し続けるこの場を通じて、私たちは学びの文化を育んでいます。
HP:https://www.arsaga.jp/







