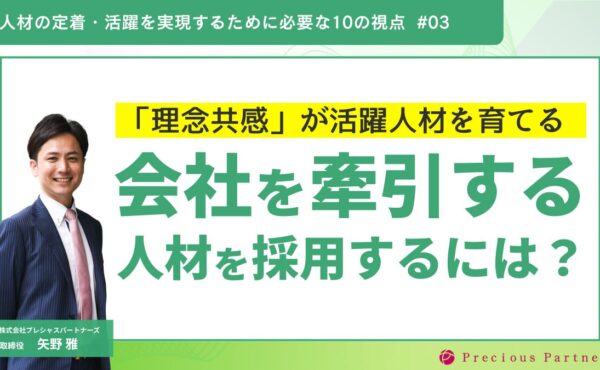本記事では、キャリアSNS「YOUTRUST」が主催したイベント「HR LEADERS 〜なぜ今「採用革命」が必要なのか、“選ばれる企業”になるための視点と打ち手〜」の模様をレポートします。
株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズの小野壮彦氏と、株式会社YOUTRUST 代表取締役CEOの岩崎由夏氏が語った、採用を経営戦略として捉え直す新常識「TA(タレントアクイジション)モデル」への変革と、明日から使える具体的な打ち手に迫ります。

登壇者小野 壮彦氏株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ ディレクター
アクセンチュア入社後、起業したITベンチャーを楽天へ売却。楽天社長室勤務、Jリーグ・ヴィッセル神戸取締役を経て、ベンチャー取締役を歴任後、2008年グローバルに展開するエグゼクティブ•サーチファームへ入社。パートナー就任。2017年ZOZOに転じ、新規事業部の本部長としてゾゾスーツ事業を立ち上げ、国際展開。2019年より日本最大級のベンチャーキャピタル、グロービス・キャピタル・パートナーズにて投資先の成長支援に従事。早稲田大学商学部、SDAボッコーニ(MBA)卒業。著書「世界標準の採用」「人を選ぶ技術」

登壇者岩崎 由夏氏株式会社YOUTRUST 代表取締役 CEO
大阪大学理学部卒業後、2012年株式会社ディー・エヌ・エーに新卒入社。採用担当として経験を積む中で、求職者にとってフェアでない転職市場に違和感を覚え、起業を決意。「日本のモメンタムを上げる 偉大な会社を創る」というビジョンを掲げる、株式会社YOUTRUSTを2017年に設立。2018年4月にリリースした、日本のキャリアSNS「YOUTRUST」は累計ユーザー数は約40万人に成長。

モデレーター石原 沙代子氏株式会社YOUTRUST ヒューマンリソース部 部長
大学卒業後、サイバーエージェント入社。人事本部にてエンジニア新卒採用立ち上げに携わる。その後、医療法人で経営企画と医師採用を経験し、金融教育のABCashにて執行役員CHRO、女性のためのコーディングブートキャンプMs.Engineer取締役CHROを経て、株式会社YOUTRUSTへ参画。現在はヒューマンリソース部部長として採用全般を管轄。
目次
なぜ今、あなたの会社の採用はうまくいかないのか? 〜経験者採用の現状〜
優秀な人材を“待つ”だけ。「ご祈祷型採用」の限界

経験者採用の現状として、エージェントに依頼してあとは待つだけの「ご祈祷型採用」や、候補者を見下すような「お殿様採用」を挙げていただきましたが、こうした状況はまだあるのでしょうか?


「ご祈祷型採用」は、まだ非常に多いと感じます。採用のノウハウがない、担当者がいないといった理由で、エージェントにお願いするだけになってしまう。私たちの投資先でさえ、まだスカウトを能動的に打つことに心理的なハードルがある会社は存在します。

私が前職で中途採用をしていた2012年頃が、ギリギリ「ご祈祷型」があった時代でした。そこからダイレクトリクルーティングに移行していった記憶があるので、まだ残っていると聞くと驚きますね。
候補者を“選んでやる”という勘違い。「お殿様採用」が招く悲劇

「お殿様採用」も、特に地方企業などでは根強く残っています。先日、関西の企業様向けに講演した際、「面接は最初から最後まで3対1や4対1でやっている」という会社があり、驚きました。
新卒採用の延長で考えていたり、外部から人が入ってくることへの不安から、みんなでチェックしないと、という心理が働くのでしょう。 たとえ面接の形式がそうではなくても、「雇ってやる」というマインドの面接官はまだ多く、候補者の体験価値を著しく下げてしまっています。

背景にある市場の構造変化:なぜ「待ち」の採用では勝てないのか

かつては転職回数が生涯で1回程度だったので、多くの人がプロであるエージェントを頼りました。しかし、日本の平均転職回数が2.8回まで増えた今、2回目、3回目の転職者は自分で直接企業とやり取りする「ダイレクト型」に移行しています。
そして、さらに転職回数が増えると「ネットワーク型」、つまり元同僚や知人からの紹介で転職先を決めるようになります。アメリカの平均転職回数は11.3回。日本もいずれそちらに近づいていくと思われます。優秀な人ほど、転職市場に出てくる前につながりのある人たちに声をかけられてしまう。こうした市場の変化こそが、従来の採用手法が通用しなくなった根本的な原因と考えています。

採用の新常識「TA(タレントアクイジション)モデル」とは?

「採用(Recruiting)」から「タレント獲得(Talent Acquisition)」へ

これまで採用は「リクルーティング」、つまり人事の一部門の業務と見なされてきました。しかし、これからの時代に必要なのは「タレントアクイジション(TA)」という考え方です。

これは、単なる欠員補充ではなく、経営戦略の一環として優秀な人材を能動的・戦略的に獲得していく活動を指します。 海外では、事業会社の採用担当者が「リクルーター」と呼ばれると、「私はエージェントではない」と怒る人もいるほどです。彼らは自らを誇りを持って「TA」と名乗ります。それくらい、採用は専門性の高いプロフェッショナルな仕事だと認識されているのです。
組織の作り方:なぜ「TA部」を社長直下に置くべきなのか

TAモデルを実践するための具体的な組織改革として、私は採用機能を人事部から切り離し、独立した「TA部」を作ることを推奨しています。そして、そのTA部は社長直下、もしくは営業・マーケティング部門の役員の傘下に置くべきです。それくらいドラスティックな変革が、企業の採用力を飛躍的に高めます。

実は、弊社の採用チームはまさにその形です。CEOである私の直下に、TA部である採用チームを置いています。労務など他の人事業務とは分けて、採用だけは経営の意志として直接見ています。特に問題は起きていませんし、むしろスピーディーな意思決定ができています。
TAとして求められる人材像とは?

TAとHR(人事)では、求められる人材のタイプが少し異なります。TAに必要なのは、営業やマーケティング人材のような「達成志向性」です。目標を与えられると燃え、達成のために戦略を立てて何が何でもやり遂げる。そうしたメンタリティが非常に重要です。
一方で、よくある誤解として「TAは社交的でなければならない」というものがありますが、それは違います。1対1で深く対話できる内向的なタイプの人も、TAには非常に向いています。
明日からできる!”選ばれる企業”になるための4つの打ち手

1. 候補者体験をデザインする:「点」ではなく「線」で捉える

候補者との関わりは、応募から内定まで、すべてが一貫した体験になっていなければなりません。ディズニーランドに入ってから出るまで、すべてが夢の国であるのと同じです。
面接の日程調整が滞るなど、少しでも流れが悪いと候補者の熱量は一気に冷めてしまいます。採用プロセス全体を「線」としてデザインし、管理する視点が求められます。
2. スピードと柔軟性:候補者の熱量を逃さない

採用にはテンポの良さが不可欠です。
以前、合格連絡が遅れたり、次の日程調整が滞ったりして、候補者の途中離脱率が非常に高かった時期がありました。そこで、「面接の翌日までに次回日程が確定していない人の割合を10%以下にする」というKPIを毎日追いかけたところ、離脱は劇的に減りました。
特に「この人は!」と思った候補者に対しては、「その場で合格を伝え、次回日程もその場で組む」ようにしています。それくらいスピード感は重要です。
3. 質の高いフィードバック:「面接の2日後」が効果的

候補者のエンゲージメントを高める上で、非常に効果的なのがフィードバックです。面接で盛り上がったとしても、その熱は時間と共に冷めていきます。そこで、あえて面接直後ではなく、少し忘れた頃、具体的には「2日後」くらいに丁寧なフィードバックを返すのです。「あなたのこういう点を素晴らしいと感じた」と伝えることで、候補者の気持ちが再び盛り上がり、エンゲージメントが格段に向上します。
4. トップタレントへの正しいアプローチ:”チヤホヤ”より”ゴリゴリの面接”を
 優秀な人材、いわゆるトップタレントを採用する際に、多くの企業がやりがちな間違いがあります。それは、相手を丁重に扱い、会社の魅力を一方的に伝える、いわゆる“チヤホヤする”ことです。 しかし、本当に優秀な人は褒められることに慣れています。彼らが求めているのは、自分のことを深く理解してくれる相手です。だからこそ、トップタレントに会った時ほど、相手のキャリアやスキルについて深く掘り下げる「ゴリゴリの面接」をすべきなのです。「この会社は本気で自分を理解しようとしてくれている」という信頼感が、最終的な意思決定に繋がります。
優秀な人材、いわゆるトップタレントを採用する際に、多くの企業がやりがちな間違いがあります。それは、相手を丁重に扱い、会社の魅力を一方的に伝える、いわゆる“チヤホヤする”ことです。 しかし、本当に優秀な人は褒められることに慣れています。彼らが求めているのは、自分のことを深く理解してくれる相手です。だからこそ、トップタレントに会った時ほど、相手のキャリアやスキルについて深く掘り下げる「ゴリゴリの面接」をすべきなのです。「この会社は本気で自分を理解しようとしてくれている」という信頼感が、最終的な意思決定に繋がります。
Q&Aハイライト:現場のリアルな疑問に答える

Q1:従業員300名以下の企業でのTAチームは何名体制が適切?

年間の採用人数で考えるべきではありません。重要なのは、「能動的に探索しないと採用できない、本当にイケてる人材」を何人採用する必要があるかです。そうした難易度の高い採用を考えると、TAスタッフ1人あたりが年間で希少人材の採用をコミットができるのは6名程度が目安になるでしょう。その目標人数から逆算して体制を考えるのが適切です。
Q2:TAとHRを分けると、入社後のギャップが起こりやすくなるのでは?

組織を分けること自体が入社後のギャップの原因になるのではなく、TAチームの目標設定(KPI)が原因となります。採用決定数だけを追いかけると、質を度外視して無理やり採用してしまうリスクがあります。それを防ぐためには、例えば「イケてる人に何人会えたか」といったプロセスを評価指標に加えることが有効です。これにより、短期的な成果主義に陥ることなく、質の高い採用活動を維持できます。
Q3:自称TAは誰でもなれる気がします。どこからが本物の「TA」でしょうか?

私が認める、というものではありませんが、明確な違いは2つあると考えています。1つ目は、数字で語れるかどうか。採用活動を定量的に分析し、数字を基に報告や戦略立案ができるか。これは従来の人事のカルチャーにいると苦手な方が多い部分で、TAとリクルーターの質を分ける大きな違いです。2つ目は、エージェント以外のチャネルに精通していること。ダイレクトスカウト、リファラル、ネットワーキングといった『直接調達』の技を高いレベルで繰り出せること。これがTAと呼べる人材の条件だと思います。
編集後記:採用にもっと科学的なアプローチを

今回のイベントで浮かび上がってきたのは、採用を単なる人事業務の一部と捉える時代は終わり、経営の最重要課題として戦略的に取り組む「TA(タレントアクイジション)」への変革が急務であるという、力強いメッセージでした。
候補者を「待つ」のではなく、能動的に「探し、口説き、獲得する」。そのための専門組織を作り、科学的なアプローチで候補者体験をデザインしていく。そんな「採用革命」の実践こそが、これからの時代に“選ばれる企業”になるための唯一の道なのかもしれません。
イベントで語られた内容は、登壇した小野壮彦氏の著書「世界標準の採用」で、より深く学ぶことができます。また、YOUTRUSTが新たにリリースした「AIキャリアシミュレーター」は、候補者のキャリア観を理解する上で、採用担当者にとっても新たな武器となるでしょう。YOUTRUSTは今後も、採用に科学的な視点をもたらし、変革を後押しする場を創出してまいります。