
“テクノロジーの進化”を洞察することで、ヒトの働き方が今後どのように変わっていくかを検証する「ヒト×テクノロジー研究所」。
前回は、記念すべき第一回目のレポートとして、所長の村山とヒトテク戦略部門パートナーの高橋が、タクシー業界を代表する経営者、“タクシー王子”こと日本交通・川鍋一朗会長を直撃しました。
今回は後編、「日本交通の未来戦略」についてご紹介します。
※今回は、前編・後編の二部構成でご紹介いたします。
タクシー王子が見つめる「おもてなし」の価値が向上する自動運転技術の未来

川鍋 一朗(カワナベ イチロウ) | 日本交通株式会社 代表取締役会長
「Uber」に教えられた日本ならではの「シェアリングエコノミー」の在り方
村山:アメリカではライドシェアサービス「Uber」や、空きスペースをシェアするAirbnbが大きな話題になり、「シェアリングエコノミー」という市場の盛りあがりが日本にもきていますが、そちらについてはどうお考えですか?

技術やサービスの変化がものすごいスピードで起こる中、実は社会制度が短い時間で影響を受けつつあります。われわれの業界でも、「Uber」を代表するシェアリングエコノミーの影響を受けていますが、これを本業とする人たちが世界では出てきています。

そうすると、本業である以上は従業員としての立場の保全を考えるようになります。これは他業界のシェアリングエコノミーでも同じで、労働力として大分安く買いたたかれていることに気づいて、世界中でストライキが起きたりしています。
つまり、クラスアクション(集団訴訟)を起こしているわけで、これまで産業労働者たちが長い時間をかけてここまで到達させてきた労働闘争史を、猛スピードの早送りで見ているような気分になります。
そういったものに対して、真摯に向き合って解決していくことが必要になるでしょう。
どこかに適正な範囲があるはずなのですが、いまのシェアリング議論はその適正な部分はなしに「安くてかっこいいじゃん」という話ばかりで熟成されていません。

高橋:ある意味先進国モデルというか、やっぱりそうしたシェアについては、東南アジアやアメリカがすごく進んでいますよね。ただし、いまのお話の通りで「節度」というものがまるでない。
日本の場合は「節度」があり過ぎて守られ過ぎているとも思いますが、川鍋さんが目指されているような“節度があるシェアリングの形”…より安心安全で、だけどみんながいまよりもっと移動したくなる、これまでにはない1歩進んだモデルがあると考えていて、そこは大いに期待しています。
タクシー王子・川鍋一朗が未来に向けて挑む「ど真ん中からの挑戦」
村山:これまでの話を受けて、日本交通としてはどんな未来戦略を立てているのでしょうか?
川鍋:今後、タクシー業界は「トランスポーテーションモビリティサービス」の黄金期を迎えます。トランスポーテーションモビリティサービスとは、自動運転技術などによって運営効率性や利便性を高めるサービスのことです。
まずは配車アプリなどによるIT化というソフト面の進化と、自動運転技術というハード面の進化という2つの大きな柱を持って、この黄金期に挑戦していくつもりです。
日本において、車による移動の7割は自家用車によるものですが、ここが今後のモビリティサービスの可能性ととらえています。
だからこそ、この技術に世界中の人たちが投資を始めています。日本を代表する企業として、ここからどのようにグローバル競争に対峙していくかが問われるでしょう。

高橋:そのなかで、業界のリーダーとして、日本交通さんが担う役割は何でしょうか?
川鍋:私は日本のトランスポーテーションを次の時代に向けて動かしたいと思っています。これを、国に向かって、ど真ん中から向き合って、やるべき人間がやる。これが自分の仕事だと思っています。
端っこから始めると、何か問題が起こったときに、やっぱり自動運転は危ないとか、暴走したらどうするんだと言われてしまう。世界最高の技術を誇る日本で実践ができなくて、リスク許容度だけが高い技術に劣る国に先んじられるなど、決してあってはなりません。
だからわれわれがやる。業界の中心にいるという矜持をもって、しっかりと地固めをしながら真正面から取り組みたいのです。

村山:きわめてユニークな取り組みをされていますからね。今がちょうど先々の勝敗を占うタイミングだと思いますが、近未来に向けてはいかがですか。
川鍋:ちょっと宣伝になっちゃいますけど、新サービスをどんどんリリースしていきます。先日都内で導入された「初乗り410円」に加えて「事前確定運賃」というサービスをテストしていきます。
さらに「タクシー相乗りサービス」といった斬新なサービスも検討しており、業界に新しい風を吹き込みたいと考えています。
なにしろ、タクシー業界最高のエンジニアが集まる会社で開発を進めており、イノベーションの震源地を目指しています。自動運転車自体は自動車メーカーが開発するものなので、それをいかにサービスと融合させるかがわれわれのミッションです。
高橋:それは期待できますね!
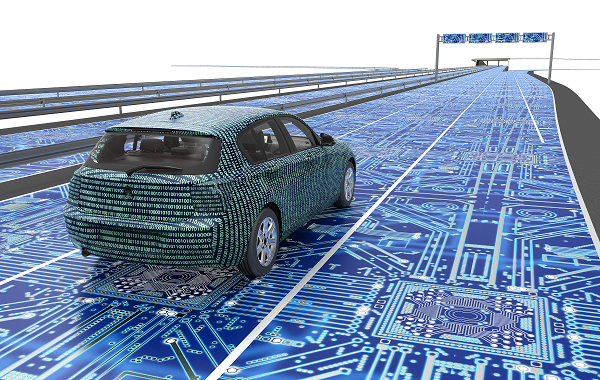
川鍋:近未来ということで、「東京オリンピック」の話をしましょう。羽田空港でパラリンピアンを車椅子のまま自動運転車にお乗せするのです。車内にアテンダントは乗車しますが、運転をする人はいない。そして、選手会場となる豊洲までおもてなしする…このイメージです。
必ずや、実現させてみせます!
タクシー王子が見つめる「おもてなし」の価値が向上する自動運転技術の未来







