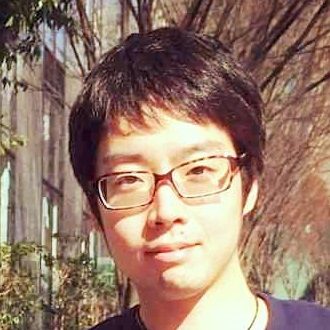近年は人事領域において、さまざまなキーワードが飛び交っています。
その中の一つとして挙げられるのが「ホラクラシー経営」です。新しいマネジメントの手法として、アメリカで話題となりました。しかし、「聞いたことはあるけど、実はよく意味が分かっていない」という方は少なくないのではないでしょうか?
そこで今回は、そもそも「ホラクラシー経営」とは何なのか?また、ホラクラシー経営を理解するうえでおさえておきたいポイントから、実用化していく際の進め方についてまでご紹介します。
【目次】
目次
そもそもホラクラシー経営とは?

そもそもホラクラシー経営とはどのような概念なのでしょうか?基本的には以下のような経営手法を意味します。
ホラクラシー経営の始まりは、アメリカの起業家であるブライアン・j・ロバートソン氏が2007年に、役職をなくして生産性を上げる新しい組織マネジメント「ホラクラシー」という概念を提唱したことに由来します。
そして、このホラクラシーという概念は、アメリカのEC企業であるザッポス社(Zappos.com)が導入・実践していることで有名になりました。
ザッポス社のホラクラシー導入に一役を買ったブリロニ・アレックス氏は、「これまでの官僚的な組織構造により意思決定におけるキーパーソンとつながっているかどうかが重要だったが、より効率的でイノベーティブな組織に変革するためにホラクラシーを導入した」と語っています。
つまり、トップダウン型だった組織の意思決定構造を解体し、より効率的にスピードを持って施策を実行していける組織構造につくり変えたということになります。
このような組織構造が求められた背景には、IT化の進展やプロダクトライフサイクルの短命化の流れを受けて、よりスピーディーに経営判断をおこなう必要性が企業経営に求められていることがあります。
ザッポス社の場合は、既存の組織構造に限界を感じてホラクラシー経営に移行したものだと言えます。
ホラクラシーの前提となる性善説
一見すると、全ての企業がホラクラシー経営を導入した方が良いと考えるのではないでしょうか?意思決定のスピードが求められる昨今、スピーディーな経営判断がおこなえることは願ってもないことです。
しかし、ホラクラシー経営を上手く進めていくためにはある前提条件をクリアする必要があります。それは、会社にいるメンバーを信頼して意思決定を任せられるかどうかです。
つまり、「自社のメンバーに意思決定権を与えた際に、適切に意思決定がおこなえると信じることが出来るかどうか」が、そもそもホラクラシーを導入出来るかどうか、また実際にホラクラシーが定着していくかに影響をします。
実際にホラクラシーを導入した場合、メンバーは仕事を遂行していくうえで以下の事項が求められます。
【ホラクラシー経営を導入するための前提条件】
- 個々人に与えられた役割に対して自発的・能動的に課題を見つけ、課題解決しようとする主体性
- 周囲からの監視がなくても、自走して動くことが出来るセルフマネジメント力
- 自分の利益を最大化することに走らない倫理観
基本的に、ホラクラシー経営を実践する場合には組織のヒエラルキー構造はなくなり、ある課題を解決することを目的としたサークル(タスクフォースのようなチーム)が発生し、それぞれが役割を持って課題解決に取り組んでいきます。
そのため、メンバーは課題解決のために何が必要なのかを自分で考え、自分だけでは難しい場合には周囲の協力を仰ぎながら主体的に動く必要があります。だからこそ、能動的でなく受動的なメンバーからしてみれば、何をどのように進めていけば良いのか分からずに意思決定が出来ずにプロジェクトが進展しないという状況に陥ってしまいます。
言い換えると、全てのメンバーが上司の指示を仰がずとも自律的に動けるかが、ホラクラシー経営の重要な前提条件となります。また、そもそも会社のメンバーが主体性を持って働くことが出来るという性善説的な発想から、権限移譲をおこなえるかもホラクラシー経営を導入するうえでは必要となります。
マネジメントは性悪説的発想?

一方で、従来のマネジメント型経営は、先述したホラクラシー経営を導入するための前提条件とは反するように感じています。
マネジメント型経営は、メンバーが主体的に動かない(動けない)ことを前提に、ヒエラルキー構造を利用して意思決定のフローを明確化し、トップダウンで指示を出してメンバーをマネジメントすることで組織としての最適化を図ることを目的にしているものだからです。
昨今ではさまざまなマネジメント手法が提唱されています。個人の労働時間と業務内容と成果を細かく確認する「マイクロマネジメント」と呼ばれる手法から、大雑把に数字目標だけを設定して実績だけを見て判断するようなマネジメント方法まで千差万別です。
しかし、どのマネジメント手法においても、前提には「メンバーが主体的に正しい意思決定が出来るかどうか分からない」という性悪説的な発想があるのではないでしょうか。
つまり、ホラクラシー経営を導入する場合には、自社のメンバーに対して性悪説的な発想から性善説的な発想に転換して向き合うことが求められます。
スタートアップでは、ホラクラシーの概念を取り入れられることが多い?

日本においてホラクラシー経営を導入している企業はまだそこまで多くありません。ホラクラシー経営を導入することは、これまでのマネジメント型経営から大転換をおこない、大幅な組織改革に着手する必要があるため、現実的に難しいというのが本音だと思います。
一方で、いわゆるスタートアップと呼ばれるフェーズの企業では、ホラクラシー的な考え方に基づいた経営がおこなわれていることも多くなってきているように感じています。
これらの企業では、いわゆる「0→1」と呼ばれるような事業の立ち上げがメインで、少人数で経営していることがほとんどです。スタートアップの多くは、主体的に仕事をしたいという人が集まるから自然とホラクラシーの考え方に近い経営ができているということもあるでしょう。
しかし、それよりもスタートアップにおいては、数少ないリソースを最大限活用することが求められおり、その中でもマネジメントにかけるリソースは無駄であるという考え方が強いからだと考えられます。
事業を立ち上げたり新しいプロダクトを生み出す過程において、マネジメントは基本的に何の成果も生みません。マネジメントにかける時間があるなら、プロダクトのバグ修正をおこなったり、実際にお客さんのもとに赴いてヒアリングをおこなう方が事業の成果につながります。
少ないリソースで最大限の成果を出すためにも、そもそもマネジメントをおこなわない企業が日本でも増えてきているようです。
ホラクラシーの導入は小さく始める
もし、ホラクラシーを導入したいという場合、組織全体として大きく始めようとすると途中で頓挫する可能性が高くなります。また仮に上手く導入出来たとしても組織として機能せずに、トラブルが続出することも想定されます。
そのため、まずは部署やチームといった規模感からはじめるのが現実的です。先に引き合いに出したザッポス社においても、実際のホラクラシー導入は2013年初頭にパイロットグループが結成され、人事部門の2チームからスタートしています。
そこで機能していることが確認されてから、段階的に他の部署にも導入されていき、最終的に会社全体としてホラクラシー経営に移行しています。
スタートアップなど小規模な組織においては最初から全社で導入することも可能かもしれませんが、基本的には小さくはじめて自社で機能するかどうかを検証するのが望ましいのではないでしょうか。また全社で導入するか小さくはじめるかの境目は、社長が全メンバーを把握出来る範囲か否かが一つの指標になると考えられます。
【※私見】求職者の立場から考えるホラクラシーとマネジメント
今回は「ホラクラシー経営」について、そもそもの定義から「マネジメント型経営」と比較までおこなってきました。ここまでの説明は、今いる自社のメンバーのみが対象となる前提でホラクラシー経営について考察しています。
しかし、実際には今自社にいるメンバーだけでなく、今後自社で働いてくれるメンバーからの視点についても組織の在り方を考えることが採用面から求められています。そこで最後に求職者の視点から「ホラクラシー」と「マネジメント」について考えていきます。
仮にあなたがエンジニアで新しいプロダクト開発に携わりたいという志向を持ってい場合、魅力的に感じる組織は「ホラクラシー経営」ではないでしょうか?
このような場合は「自分で主体的に開発を進めていきたい」「細かい修正や改善について逐一確認を取りたくない」と考えることが多く、マネジメントされることを嫌う傾向があります。基本的には性善説的な発想を前提とした組織を好むことがほとんどです。逆にマネジメントされることを求める求職者もいらっしゃいます。
このように求職者の視点を考慮すれば、戦略的に「ホラクラシー」と「マネジメント」を比較して、組織を構築していくことが優秀な人材の採用と定着が求められている昨今においては必要かもしれません。