
いまさらで恐縮ですが、ここ数年で「●●会社を辞めました」「○○会社に入社しました」という、いわゆる『退職エントリ』がやたら目に入るようになりました。
私も過去に転職をしたことがある身ですが、当時は退職エントリの存在を全く知らず、「退職エントリを書こう」と頭に思い浮かぶことすらありませんでした。ただ、実際書くとなると、結構な勇気が必要な気がします・・・(小心者なので)。
なぜ、多くの方々は退職エントリを書くのでしょうか。そして、それはどのような内容のものなのでしょうか。また、退職エントリの内容を読み解くことで、何かしら人事の方々に参考になるものがあるのではないでしょうか。
そこで今回は、『退職エントリ』について調べてみました。
目次
退職エントリとは?

『退職エントリ』とは、会社を辞めた方がブログなどに退職の旨を書いた記事のことを意味します。
もともと、ブログに投稿された個々の記事のことを「エントリー」と言い、そこから退職の報告に関する記事を『退職エントリー』『退職エントリ』と呼ぶようになったと推測されます。
呼び名に関して私の調べた範囲では、『退職エントリー』よりも『退職エントリ』と、「ー(伸ばし棒)」をとった言い方のほうが多いように見受けられました。そのため、本記事でも『退職エントリ』という名称で記載しています。
ちなみに、退職エントリはいつから書かれるようになったのでしょうか?
正確なはじまりに関してはわかりかねますが、少なくとも、こちらの『退職エントリまとめ』のサイトをみると、どうやら、既に2006年からあったようです。私がまだ大学生の頃からあったのですね。そもそも、退職エントリのまとめサイトがあることにも驚きを覚えました。
どんな退職エントリがあるのか?
ここでは、どのような退職エントリがあるのか、いくつかピックアップしてみました。
セブ島行ってたら面白法人カヤック辞めてリクルートに転職してました。
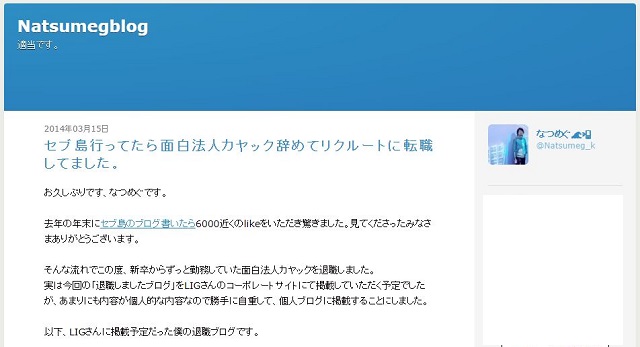
面白法人カヤックからリクルートに転職した際の退職エントリになります。カヤックで今までどのような業務をおこなってきたのか、その詳細の内容が中心に書かれています。なぜ辞めたのか、なぜリクルートにいくのかといったことも記載されています。
大手水産商社を退職しました。古すぎた日本の水産業界

こちらは、大手の水産商社を退職した際の記事になります。前職になぜ入社したのか、その入社理由や業務内容が簡単に書かれており、退職理由については、具体的にかつ赤裸々に記載されています。また、Amazonのウィッシュリストを最後に載せています。
【退職エントリー】わずか8ヶ月で会社を辞めました

前々職ではSI企業に勤めており、そこから転職したらしいのですが、8ヶ月で退職となります。本エントリでは、なぜ8ヶ月で退職してしまったのか、その理由が記載されている内容となっております。
ドイツの受託開発会社を退職しました

非常に長文な退職エントリですが、「海外で働くとは?」といったことが、非常に赤裸々に記載されており、興味を持ってどんどん読み進めてしまう内容でした。プライベートの様子の写真も掲載されており、海外の仕事のリアルを見ることができます。
桜も満開ですね。株式会社LIGを退職しました。

クリエイティブ会社LIGのさえりさんの退職エントリです。こちらの記事は私の周囲で結構話題になりました。一見すると普通の、むしろあっさりした退職エントリなのですが、文末に不自然なスペースがあることにお気づきでしょうか。こちらのスペースを範囲選択すると・・・。
退職エントリにはどのような内容が書いているのか?

今回調べたところ、以下の7つの項目をもとに退職エントリが構成されているように感じました。特に①、②、③の項目は、ほとんどの退職エントリに記載されている印象です。
①今まで何をしてきたのか?
入社してからどのような職種でどのような仕事をしてきたのか。そこで学んだことや失敗したことは何かなど、前職で経験してきたことを整理する意味も含めて記載しています。
②退職理由は何か?
こちらはネガティブなものからポジティブなものまで理由はさまざまです。「新しいチャレンジがしたくなった」「職場の雰囲気に合わなくなってしまった」「上司との関係性」などなど、いろいろな声が見られます。
③これから何をするのか?
次はどのような職場で働くことになるのか、今後やっていきたいことは何かといった、新天地に向けての意気込みや報告が書かれています。
④次の会社への入社経緯
どんなきっかけがあってその会社に出会い、どのような選考・面接を経て入社したのか。現在どのような仕事をしているのかが書かれています。
⑤前職の良いところ悪いところ
「成長させてくれた」「いい人たちばかりだった」「技術環境が良かった」といった良かった部分を記載している一方、「給料が良くない」「社員の声が届きにくい」「遅くまで働いている」といったネガティブな意見も多くあります。
⑥転職アドバイス
自身の転職経験をもとに、転職活動中におこなって良かったことや失敗したことなどを記載しています。
⑦欲しいものリスト
Amazonウィッシュリストが多く見られます。新天地に向けて準備しておきたいものをピックアップしている方が多い模様です。
上記のような内容が多く見られることから、多くの方々が退職エントリを書く理由として以下が挙げられると推測しました。
- 【決意表明】:自分の決心が揺らがないように
- 【整理・振り返り】:自分自身のこれまでを振り返って整理する
- 【備忘録】:あのときの気持を忘れないように備忘録として
- 【感謝】:今までの感謝の気持ちをこめて
- 【共有】:自身と同じ境遇の方々に何かきっかけを与えられるように
- 【批判】:前職での不満をとにかく吐き出したい。周囲に訴えたい
退職エントリを書くことのメリット・デメリット
ここでは、退職エントリのメリット・デメリットを記載しています。「退職」という話題はネガティブな面も多くあるため、それを記事にすることによる悪影響も存在します。
メリット
上記にも記載しているように、退職エントリを書くことで自身のこれまでを振り返ることができ、また新天地に向けた決意も固まるという点ではメリットと言えるのではないでしょうか。
また、周囲の方々から応援される声が増えるといったこともあるかと思います。
退職エントリを通して、その人が何をしてきたのか、どんな想いを持っているのか、どんな経緯で転職したのか、今後何をするのかなど、詳細が書いてあるため、その人に対する理解が深まり、「それなら次も頑張れよ」と思ってもらえるのではないでしょうか。
その波及効果として、「うちで働いてみない?」とお誘いをいただくケースもあるようです。
デメリット
退職理由にまつわるエピソードは、赤裸々に書きすぎると本人特定ができてしまうこともあります。
内容によってはせっかくその会社でつくった信頼や人脈がゼロどころかマイナスになってしまう可能性もあるでしょう。さらには、転職先の会社にも影響があるかもしれません。何を書くか、内容には気をつけるべきでしょう。
退職エントリを読み解くことで見えるもの
今回、多くの退職エントリを見ていて感じたのは、ITエンジニアの方の記事が非常に多いということです。もちろんそれ以外でも、営業、人事、マーケティングなど、さまざまな職種の退職エントリもありました。
「退職エントリを書く人はITリテラシーが高い」ということが共通してあると思います。
また、退職理由にはどのようなものがあるかを見ていくと、
- 自身の成長と会社の成長のベクトルが合わなくなった
- もっといろんな人と働きたくなった
- 周囲と比較して、今のままでいいのかと不安になった
- 評価制度に不満があった
- 給料に不満があった
- 人間関係がうまくいかなくなった
- 仕事の進め方が合わなくなった
- 激務だった
など、本当にさまざまな理由が見られます。
前向きな理由もありましたが、「前職に対する不満の声」も同様に多く見られました。中にはかなり過激な内容の退職エントリもあり、企業ブランドにダメージを与えるほど炎上しているものもありました。
自社と似たような業種・職種の方の退職エントリを見かけた際は、どのような理由で退職したのか気に留めておくと良いかもしれません。
「退職の引き金となりそうな要素」として参考になる場合もあるのではないでしょうか。







