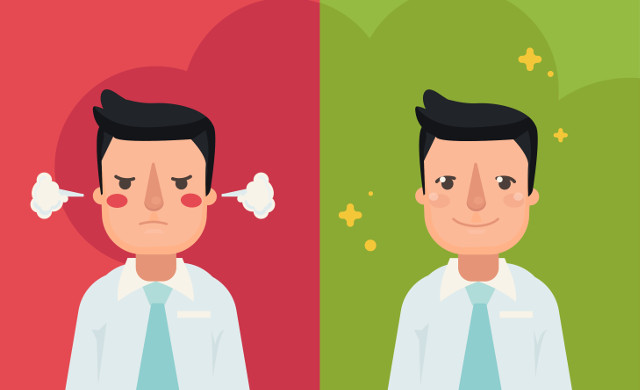
仕事をしていると、業務トラブルや人間関係などから「怒り」がたまることも少なくないでしょう。アンガーマネジメントにより、怒りを上手くコントロールすることで、気持ちよく働ける職場環境を構築し、生産性を向上させることができます。
この記事では、アンガーマネジメントのメリット・デメリットをわかりやすく紹介します。また、アンガーマネジメントの診断方法ややり方についても解説します。
目次
1. アンガーマネジメントとは?

アンガーマネジメントとは、怒りやイライラの感情を整理し、上手にコントロールするための手法・方法を指します。ここでは、アンガーマネジメントが注目される理由・背景を解説したうえで、なぜ怒りやイライラが生じるのかをわかりやすく解説します。
1-1. アンガーマネジメントが注目される理由・背景
近年ではテクノロジーの発展や働き方改革により、人々の価値観は多様化しています。自分が信じてきた価値観と合わない出来事により、怒りを感じる機会が増えています。また、少子高齢化により、人材確保の問題が多くの企業で課題となっています。パワーハラスメント問題が生じると、企業のイメージダウンや離職率の上昇へとつながり、人材確保がより困難になります。
このような理由・背景により、イライラを上手くコントロールするスキルが求めらるようになり、アンガーマネジメントが注目されています。
1-2. 「怒りのメカニズム」とは?
そもそも、イライラ・怒りはなぜ発生するのでしょうか。怒りが発生するには、段階があります。下記のように、日々の不安や恐怖といった第1次感情が蓄積し、自分の許容範囲を超えてしまうと、第2次感情として怒りの感情が表面化するようになります。
|
怒りのメカニズム |
|
|
第1次感情 |
不安、恐怖、疲労、困惑、落胆、孤独、焦燥など →日々の負の感情が蓄積している段階 |
|
第2次感情 |
涙を流したり、イライラしたり、パニックになったりといった感情が表面化するようになる →第1次感情が蓄積して許容範囲を超えている段階 |
|
負の感情が爆発して周囲に怒りを発散するようになる |
|
このように、怒りが発生したら、その背後にある第1次感情にまず気づくことが、アンガーマネジメントの第一歩となります。
2. アンガーマネジメントのメリット

アンガーマネジメントのスキルを身に着けることでどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、アンガーマネジメントのメリットについて詳しく紹介します。
2-1. 従業員のストレスが減少する
アンガーマネジメントのスキルを習得することで、客観的に自分の感情を理解することができるようになります。自分がどのようなことで怒りを感じているかを把握し、それに対して適切な対応をすることで、ストレスを減らすことが可能となります。これにより、怒りの感情に振り回されず、上手く自分をコントロールすることができます。
2-2. 円滑なコミュニケーションにつながる
チームに怒りをコントロールできないメンバーがいると、コミュニケーションが取りにくくなります。コミュニケーションの希薄化は、生産性低下や業務トラブルにつながります。
アンガーマネジメントにより、怒りの感情をコントロールして、理論的に言葉で説明できれば、どのようなことで悩んでいるのかを相手にわかりやすく伝えることができます。このように、アンガーマネジメントは円滑なコミュニケーションを促し、良好な人間関係の構築に役立ちます。
2-3. 仕事の生産性が向上する
アンガーマネジメントを導入することで、自分と異なる価値観をもつ従業員に対しても寛容になり、コミュニケーションを円滑に取ることができるようになります。意見を出しやすい環境を構築し、プロジェクトをスムーズに進めることが可能です。また、個人としても無駄な感情に振り回されなくなるので、仕事の生産性が向上します。
2-4. パワーハラスメントを抑止できる
怒りの感情がエスカレートすると、パワーハラスメントにつながる恐れがあります。パワーハラスメントの問題が生じると、メンタルヘルスの不調を訴える従業員が出てくるかもしれません。また、暴行罪や傷害罪といった刑法上の罪が生じる恐れもあります。アンガーマネジメントにより、自分自身で怒りをコントロールできるようになることで、パワーハラスメントの問題を抑止することが可能です。
3. アンガーマネジメントのデメリット

適切にアンガーマネジメントのスキルを習得しなければ、デメリットが生じることもあります。ここでは、アンガーマネジメントの導入により発生する恐れのあるデメリットについて詳しく紹介します。
3-1. 無理に怒りを抑えようとする
アンガーマネジメントのスキルがきちんと習得できていないにもかかわらず、無理にイライラの感情を抑えつけてしまうと、蓄積して大きな問題に発展する恐れがあります。
誰しも怒りの感情が発生することはあります。怒りの感情が発生したら、無理に抑えつけず、その背後にある原因に目を向けることが大切です。また、イライラの感情を爆発させないため、無理せず他の人に頼ることも大切なスキルの一つです。
3-2. 仕事へのモチベーションが下がる恐れがある
「感情」は「行動」へのエネルギーとなることもあります。アンガーマネジメントにより、怒りの感情が発生する場を避けるようになると、感情が湧かなくなり、仕事へのモチベーションが下がる可能性もあります。アンガーマネジメントでは、イライラの感情をなくすのでなく、コントロールすることを目的としています。アンガーマネジメントの目的をきちんと理解して、正しいスキルを身に着けましょう。
4. アンガーマネジメント診断とは?

アンガーマネジメントのスキルを習得する前に、自分がどのようなことで怒りを感じるのか把握することが大切です。そのために用いられるのが「アンガーマネジメント診断」です。
ここでは、アンガーマネジメント診断の実施方法から活用方法まで詳しく紹介します。
4-1. アンガーマネジメント診断の実施方法
アンガーマネジメント診断を実施するには、自社で研修を開催したり、外部講座を受講したりなど、さまざまな方法があります。ここでは、日本アンガーマネジメント協会が提供している無料で実施できる「アンガーマネジメント診断」について紹介します。アンガーマネジメント診断により、6つのタイプうちどれに該当するかがわかります。また、自分のタイプの特徴や課題も把握することが可能です。
4-2. アンガーマネジメント診断の活用方法
アンガーマネジメント診断により、自分の怒りの傾向がわかったら、実際の行動に役立てましょう。
たとえば、プライドが高くリーダー気質であるタイプだった場合、思い通りにいかないときにイライラを感じやすくなります。このようなタイプの場合、「意見」と「批判」を区別し、冷静に出来事を見つめなおしてみることが怒りを鎮静化させるためのコツです。
このように、自分の性格や特徴を正しく把握し、怒りが発生しやすい状況を理解することで、イライラをコントロールするためのポイントが見つかります。
5. 今すぐ簡単にできるアンガーマネジメントのやり方

ここでは、今すぐできるアンガーマネジメントのやり方を紹介します。自分の会社やチームでもできると感じたら、ぜひ取り入れてみてください。
5-1. 6秒ルール
怒りが生まれてから理性がはたらくまでの時間は「6秒」といわれています。イライラしたら6秒待ってみることで、怒りに冷静に対処できる可能性が高まります。
しかし、6秒何もせず過ごすのは難しいかもしれません。そこで、その時間に深呼吸をしたり、実際に6秒をカウントしてみたりするのがおすすめです。6秒ルールは、簡単に導入できるので、まず試しに取り入れてみましょう。
5-2. 怒りの点数化
怒りを客観的に捉えるには、自分がどのくらいイライラしているかを数値化するのが効果的です。これまでに一番イライラしたことを思い浮かべ、それを「10」と設定します。最近怒りを感じたことも同じように10段階で数値化しまう。最近イライラしたことは、「10より下」になるはずです。このように、怒りの点数化をおこなうことで、自分の状態を客観視して、落ち着かせることができます。
5-3. イライラを予測する
怒りの原因となっている第1次感情を自覚できれば、次にくる怒りの感情を抑えることができます。「自分の怒りポイント」を知るため、どのような時に自分がイライラするかを整理しておくことが大切です。このように、怒りが発生するパターンを把握できれば、イライラが発生する前に対処することができます。
5-4. その場から離れる
怒りが湧きそうな場面にいることに気づいたら、その場から離れてみるのも一つの手です。オフィスにいる場合は外の空気を吸いに出かけたり、失敗を引きずっている場合は趣味に没頭したりしてみましょう。時間が経つにつれて、イライラの感情が収まってくるのがわかるかもしれません。怒りをコントロールできた成功体験を積み重ねることで、徐々にイライラに対して上手く対処することができるようになります。
5-5. 「べき思考」を手放す
完璧主義の人や、責任感が強い人は「べき思考」にとらわれている可能性があります。自分の価値観と合わない出来事に遭遇すると、「べき思考」から怒りの感情が湧いてきやすくなります。
まずは、自分が「べき思考」に取りつかれていることに気づきましょう。なぜ許せないのかを分析してみると、視野が広がり、イライラの感情が鎮まる可能性があります。
6. アンガーマネジメントを導入して職場環境を改善しよう

「感情」は、人を奮い立たせるものでもありますが、逆にイライラさせたり、落ち込ませたりするものでもあります。だからこそ、仕事における「判断」を左右してしまわないよう、怒りをコントロールすることが大切です。イライラの感情に上手く対処できれば、生産性の向上が期待できます。アンガーマネジメントの考え方を取り入れて、職場環境を改善させましょう。







