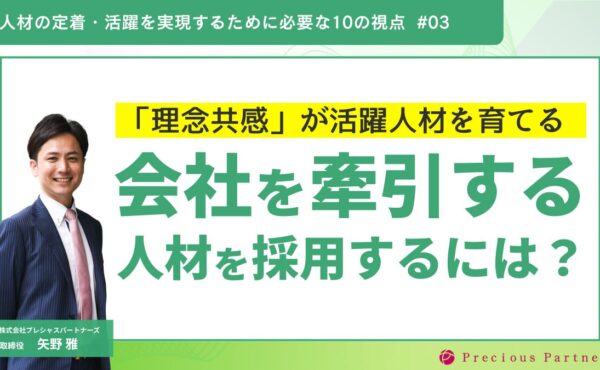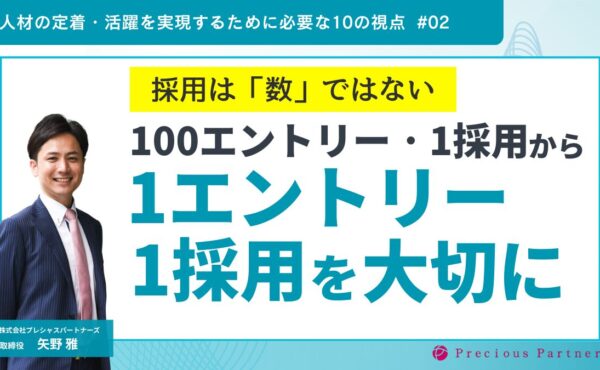私事ですが、大学生活もほぼ残り1年。
「就職活動を終えたあとに挑戦したいことややりたいこともたくさんあるけれど、ゼミや卒論準備に追われてそんな時間があるのか…」と最近考えています。
そんな悩みを先輩に相談したら、「ギャップイヤーを推奨している企業もあるよ!」とのアドバイスがありました。ギャップイヤーとは何でしょうか。はじめて聞きました。
そこで、今回はギャップイヤーについて調べてみました!
「ギャップイヤー制度とは」

ギャップイヤーとは、高校と大学や大学院と大学など、卒業と入学の間などの節目と節目の間の期間のことで、英語では「人生の節目の空いた期間を使って旅をする」という意味です。1978年イギリス皇太子が世界中の17歳~24歳の若者を集め、世界各地で働くという活動をサポートした「ドレイク活動」が始まりといわれています。
英国圏の大学では、ギャップイヤーをつかってさまざまな体験をすることが推奨されており、そのために入学までの期間はあえて長めに設定されています。この期間を使ってアルバイトなどで学費を稼ぐ人も多いですが、語学留学やボランティア活動、海外での就労(ワーキングホリデー)をする人も多いそうです。
大学のギャップイヤーの取り組み

このギャップイヤー制度についてですが、近年日本の大学でも推進されています。名古屋商科大学(愛知県)と光陵女子短期大学(愛知県)では、平成17年度の学生から、1年次か2年次の4~7月に、語学留学やボランティア活動など学生の自主的な計画に基づいた活動をおこなう、「ギャップイヤー・プログラム」を実施しています。
大学が「ギャップイヤー制度」を推進することにより、
- 大学と地元の技術系企業との協力(主に理系)
- 就職率向上
- 国際人の育成
- 交換留学生の増加
といったメリットがあります。
逆に、学生がこの空白期間に遊び呆けたり、怠惰に過ごしてしまうのではないかと懸念する声もあります。しかし、いままで受験勉強に専念してきた学生が自身の学部や興味、将来について考え、「何のためにどのように学生生活を過ごすか」を考え直すための良い期間だといわれています。
実際にギャップイヤーを取る学生は自主的な学生が多く、ギャップイヤーでの経験を通して社会を見つめることにより、目的をもって大学生活を過ごすことができるようになります。
また、日本の大学では、4~9月の空いた期間をギャップイヤーとしているのに対して、海外では自主的な活動を重要視しているため、学生に対して1年入学時期を遅らせる制度や、休学中の自主的な活動を単位として認めるなど日本よりも進んだ受け入れ制度がとられています。就職前に将来のキャリアアップのためにギャップイヤーを活用し、語学習得、国際文化交流、社会事業などに取り組むことも海外のトレンドになっています。
学生は何をしているのか

では、学生はこのギャップイヤー制度を活用してどのようなことをおこなっているのでしょうか。
- 世界一周
- 語学留学
- インターンシップ
- ボランティア・NGO活動
- 長期旅行
- 家業手伝い
- 起業
- 無人島生活
なかには、映画製作や聖地巡礼など自分の趣味や興味を突き詰めた活動をする人もいるそうです。年齢制限があるコンテストや、まとまった時間を取らないとできないような活動・旅行といった「今しか挑戦できない活動」「今のうちに挑戦しておきたい活動」などのために制度を取得する人が多く、ギャップイヤーを活用することによって期待される、スキルアップのためだけにおこなわれてはいないということがわかります。
制度化するべきか

そんなにメリットがあるなら、制度化すればいいのではないかという意見もありますが、それを大学が制度化してしまうと、また違う意味になってしまうという意見もあります。ギャップイヤー制度はそもそも「自主的な計画に基づいた行動をサポートする」制度です。
「ギャップイヤーを制度化するべき」という意見は日本の学生全体の能力・思考力向上を期待して支持されているのかと思いますが、そもそも能力・思考力育成は学生個人の強い意志の結果としてついてくるものではないかと思います。
大学で、留学する人の中には「なんとなく留学をした方がよさそうだから」と言う学生や、就職活動前のインターンシップでも「なんとなくインターンシップをした方がよさそうだから」といった意見をもった学生も少なくはないのが現状です。制度化されてしまえば同じようなことになると思います。「大学がギャップイヤーを推奨するから何かやろうかな」という気持ちではなく、ギャップイヤー制度を活用したいと思うほどの強い目的と意識に基づいた行動が大切なのではないかと思います。
また、ギャップイヤーについて調べていると、制度を通して求められているのは「国際力の育成」だという意見が多く、学生側もギャップイヤー=留学をする期間ととらえている人も少なくはありません。「ギャップイヤーで何が求められるか」を念頭において留学を選ぶ学生が多くなってしまうのではないでしょうか。
社会に対して、ギャップイヤーを推奨するべきかという問題ではなく、学生の自主的な意見を受け入れる取り組みが必要とされているのではないかと思います。