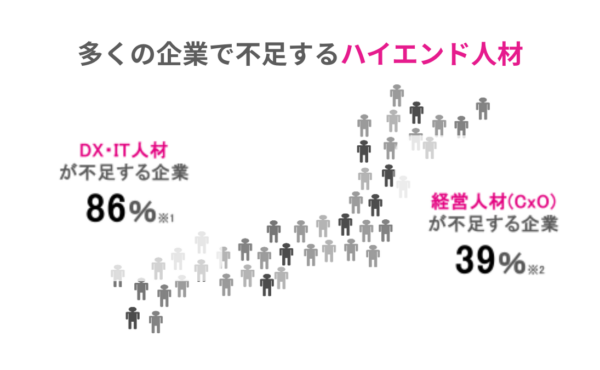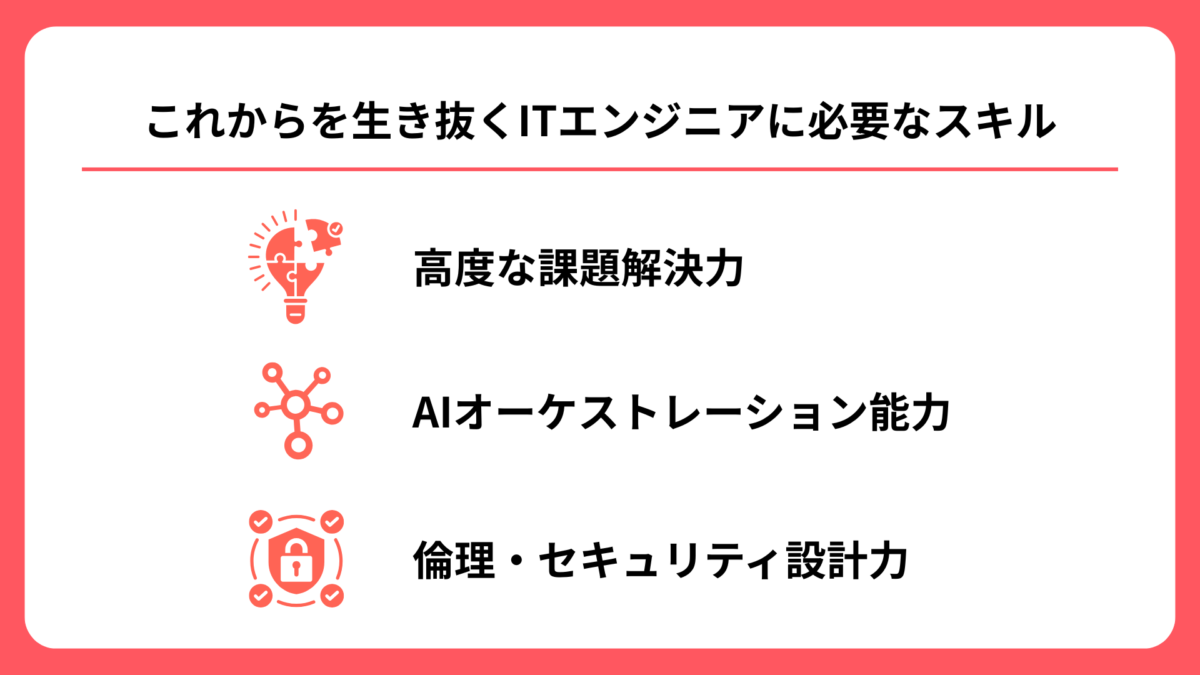
株式会社ハイヤールーの代表、葛岡です。

執筆者葛岡 宏祐氏株式会社ハイヤールー 代表取締役
1996年生まれ、最終学歴中卒。2018年にAIエンジニアとして株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)に入社。2020年2月にテックリードとして株式会社メルカリに入社。同年12月に株式会社ハイヤールーを創業。
私は中卒の経歴ながら、独学でコンピューターサイエンスを学んできました。しかし、学歴を理由に採用試験では門前払いされることもありました。そうした経験から、スキルを重視した採用のあり方を考えるようになり、ハイヤールーを立ち上げました。
ここ数年、特にこの一年間は、生成AIが業務にも使われるようになり、エンジニア採用にも変化が生じてきています。事実として、エンジニアという職種に対し期待することが変化し、見極める観点も変わってきたという話も聞くようになりました。その結果、採用計画を増やす企業、減らす企業どちらも現れています。
外部環境は変化している。しかし、企業としてはどのように対応すればいいのか。今回は、エンジニア組織向けプラットフォームを提供するハイヤールーがエンジニアの方々、そして採用企業と対峙する中で「採用担当が今やるべき」と感じていることをご紹介します。
目次
今、エンジニア採用市場で何が起きているか

生成AIの登場により、わかりやすく変化したのは「職種」です。職種の統合と新職種の出現がみられるようになりました。
フロントエンド・バックエンドといったこれまでの明確な分業が崩れ、「プロダクトエンジニア」への統合が進んでいく方向であることは、エンジニアと会話していてもわかるのではないでしょうか。
加えて、AIを使った開発運用(AIOps)や、自律型AIエージェントを管理する「AI Agent Manager」など、これまで存在しなかった役割が生まれつつあります。実際にLayerX社では、「AIオペレーションマネージャー」という職種が新設されたようです。
この変化により、人事担当者が最も直面するのは『評価軸の変化』です。これまでよりも、言語やフレームワークを使うような単一の技術スキルの評価の比重は下がり、課題を定義・要件化・AIを活用して検証まで進められる“課題解決型エンジニアリング”能力が重視されるようになってきています。
これによって、AIを活用するスキルを持つジュニア層は、プログラミング自体の経験不足でも即戦力化のチャンスが広がりつつあります。
そんな中、日本の採用プロセスは依然として学歴・職歴重視の企業が多く、米国ビッグテック企業のようなスキルを軸とした評価文化と格差が広がっています。ハイヤールーに投資いただいており、海外でのエンジニア採用経験もある元メルカリCTOの若狹氏は、「日本の採用文化は、世界の採用市場から取り残されている」と語っていました。
これからを生き抜くITエンジニアに必要なスキル
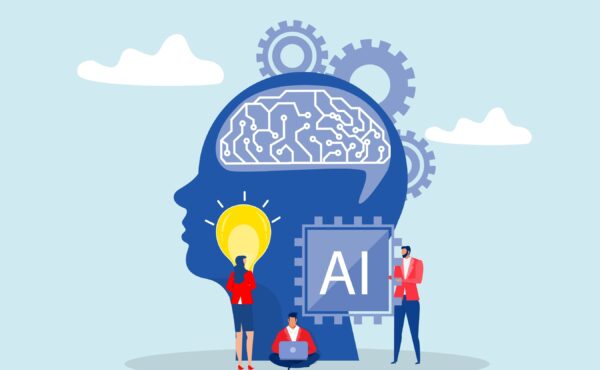
改めてここで、これからのエンジニアに必要なスキルについて考えていきます。
①高度な課題解決力
これまで人事の方は、職務経歴書を見ながら 「Reactを使えるか」「Kubernetesを使ったことがあるか」を確認していたと思います。
しかしこれからは、手段ではなく「課題解決」の能力が重視されます。顧客の要望や業務フローの曖昧さを掴み、AIが扱える粒度まで分解し、データ・指標・リスクを構造化することで、課題解決に近づけるのです。
この、課題→要件→検証のプロセスを、AIを活用しながらより短期間で回せることが重要視されます。
②AIオーケストレーション能力
CopilotやCursor、Devinといった生成AIツールを活用し、MVPを迅速に立ち上げることができることも重要です。
AIを補助的に活用するのではなく、自分が指揮官となってAI全体をマネジメントする感覚が求められるでしょう。
③倫理・セキュリティ設計力
AIのブラックボックス性や著作権・情報漏洩リスクを踏まえた設計・監査能力も重要です。
2024年には、欧州(EU)AI規制法である「EU AI Act」も発表されました。このような世界情勢を踏まえ、規制対応まで織り込んでサービスを設計する人材がいることが、組織の“最後の守備”となるはずです。
これらの能力を持ち合わせることで、仮説検証サイクルの速さは急速に上がります。そのスピード感や変化についてこれる人材かどうかも、重要な見極めポイントになるでしょう。
では、今企業は何をすべきなのか

これまでAIの登場によるITエンジニアへの影響を語ってきましたが、今度は人事・採用担当者が具体的にどのようなアクションを取るべきかについて説明したいと思います。
取り組むべきこと①
:評価基準を刷新する・AIの要素を加える
貴社はこれまでの採用基準で、学歴や職歴のフィルターを重視していませんでしたか?重視していないつもりでも、「〇〇社出身だから書類選考を通過させよう」など、実はスキル以外の要素で判断している企業が多いのが現実です。
今後は、「課題を構造化し、AIを活用して価値を生み出せるか」という実力を評価する仕組みが必要です。とはいえ、これは大きな構造改革となるため、本腰を入れて取り組んでいる企業はまだ多くないのが現状です。また、AIを前提としたスキル評価の方法を確立するのは難しく、すでに検討を進めている企業もごく一部にとどまっています。
もちろん、これは採用だけの課題ではありません。社内に在籍するエンジニアにも共通するテーマです。改めて必要なスキルを定義し直し、自社がAI時代に対応できる組織かどうかを俯瞰して把握する必要があります。
取り組むべきこと②
:AIネイティブ人材を積極的に登用する
AI活用スキルの有無によって、ソフトウェア開発の生産性には大きな差が生まれることは明白です。“コードをただ書くだけ”の業務は、すでにAIに代替されつつあります。抽象化力や事業や技術のドメイン理解力を持つ人材の採用が鍵となります。
AI活用に対して積極的かどうかを図るため、これまで「プログラミング言語」の経験を問うてきた採用選考から、「AIエージェントツール」の使用経験を問う形に変わってきているはずです。
併せて、各社は判断できる程度にはAIエージェントツールを使い、現状のAIの技術発展の状況を理解し、どのような体制が自社のAIを用いたソフトウェア開発のプロセスとして正解なのか考え続ける必要が生じます。
取り組むべきこと③
:エンジニアのキャリアパスの多様性を提示する
前述の通り、「AI Agent Manager」という職種が出現しています。これから新たな職種は他にも発生することでしょう。
また、弊社の投資家であり、Chatworkを運営するkubell社の山本代表は、今後エンジニアのキャリアパスが大きく3つの方向に分かれていくと述べています。
技術が好きな人
アルゴリズムやOSなどディープな領域に関心があり、テックリードやリサーチャーの道に進むタイプ。これまで比較的多くのエンジニアがこのキャリアを目指してきたようにも感じられますが、変化が大きい時代になり、エンジニアの志向も変化するかもしれません。
プロダクトが好きな人
技術を手段として捉えているタイプで、フルスタックでプロダクトを作ることに喜びを感じる人です。エンジニア出身のプロダクトマネージャーを目指すケースもあるでしょう。
組織が好きな人
開発プロセスやアジャイルの導入等、エンジニアリング組織そのものに関心があり、エンジニアリングマネージャーやVPoEのような、ピープルマネジメントの道に進むタイプ。
取り組むべきこと④
:採用プラットフォームの活用
Cursor AIやClineなど、ソフトウェア開発におけるAIの活用スキルを可視化できる採用プラットフォームの活用が必要です。
ハイヤールーの提供するサービスを使用することもその選択肢の一つですが、まずはその前に「スキルを測る」採用スタイルへの転換が急務です。自社にあった人材を定義し直し、その人材の発掘精度を高める努力が必要です。
今後のエンジニア採用市場はどう変わるか?

これらの変化によって、ソフトウェア開発におけるエンジニアの必要人数が減り、エンジニア採用自体が簡単になるかと言えば、そういうわけでもありません。
単に、「競争優位の源泉の移動」がおきていると言えます。従来の実装技術よりも、ビジネス課題に近い高レイヤーの課題設定力・検証力が、エンジニアとしての生存戦略を左右します。
スキルや評価基準が変われば、今まで陽の当たらなかった人材に陽が当たる、という可能性もあります。なのでチャンスだと捉えるエンジニアの方もいるでしょう。
何よりもこれからの市場変化において必要なのは、エンジニアは変化を恐れずAIを強力なツールとして使いこなすこと。そしてエンジニアを採用する企業は、その姿勢を理解し、適正に評価する努力を惜しまないこと。それが、これからのIT全体の市場を成長させることにつながると信じています。
最後に
ソフトウェア開発のスキルは正しく評価できていますか?AIを活用してコーディングすることで、スキルの評価はさらに難しくなっていくことが予想されます。
感覚に頼らず、「スキルを測る」採用スタイルへの転換には、プラットフォームの導入が必要です。スキルを測る採用の実現の一手として、ハイヤールーのサービス導入もご検討ください。
採用から見極めまで実現できる All-in-One エンジニアリング組織プラットフォームを提供中!
 HireRoo Skill Interview:エンジニアのスキル見極め
HireRoo Skill Interview:エンジニアのスキル見極め
エンジニア採用において、候補者のスキルを正確に評価することは極めて重要です。AI時代のスキル面接サービス「HireRoo Skill Interview」では、事前課題と面接時の深掘りを通じて、ハードスキルとソフトスキルの両面から候補者を可視化し、採用後のパフォーマンスに直結する判断材料を提供します。これにより、公平かつ効率的な選考プロセスを実現し、企業の最適な人材選びを支援します。
HireRoo Skill Hiring:エンジニア人材と企業の最適なマッチング
従来の採用手法では見逃されがちだった、即戦力層以外の高スキル人材にも着目し、ポテンシャルを正しく評価・提示できる仕組みを構築。「スキル保証型採用」の HireRoo Skill Hiringは、スキルが可視化された状態で候補者と企業をマッチングし、採用ミスマッチの低減と、エンジニア一人ひとりが真に活躍できる環境との出会いを実現します。