
異なる国や地域の人とのビジネスで、しばしば課題となる“文化”の違い。あなたも思い当たる節はありませんか?
「文化の違いは対処のしようがない……」。もし、そう思っているならちょっと待ってください。文化の違いは乗り越えられますし、文化は変えることだってできます。とりわけCQという力をふるってみたのなら。
IQ(知能指数)、EQ(こころの知能指数)に並び、世界的に注目されるCQ(文化の知能指数)。なじみのない言葉かもしれませんが、CQという観点があると文化の違いを理解し、その違いを楽しむことだってできます。
今回は実際に違いを楽しんでいるビジネスパーソンの具体的な事例から、CQについて知っていただこうと思います。CQが高いと具体的に何ができるのか?海外事業や海外メンバーとの協働などに役立つヒントを聞きました。

寄稿者宮森 千嘉子氏アイディール・リーダーズ株式会社 CCO(Chief Culture Officer)
「文化と組織とひと」に橋をかけるファシリテータ、リーダーシップ&チームコーチ。 サントリー広報 部勤務後、HP、GEの日本法人で社内外に対するコミュニケーションとパブリック・アフェアーズを統括し、 組織文化の持つビジネスへのインパクトを熟知する。 また50カ国を超える国籍のメンバーとプロジェクトを推進する中で、 多様性のあるチームの持つポテンシャルと難しさを痛感。 「違いに橋を架けパワーにする」を生涯のテーマとし、日本、欧州、米国、アジアで企業、地方自治体、プロフェッショナルの支援に取り組んでいる。英国、スペイン、米国を経て、現在は東京在住。ホフステードCWQマスター認定者、CQ Fellows、米国Cultural Intelligence Center認定CQ(Cultural Intelligence)及びUB(Unconscious Bias)ファシリテータ、 IDI(Intercultural Development Inventory) 認定クォリファイドアドミニストレーター、 CRR Global認定 関係性システムコーチ(Organization Practitioner, Gallup認定ストレングスコーチ。著作に「強い組織は違いを楽しむ CQが切り拓く組織文化」、共著に「経営戦略としての異文化適応力」(いずれも日本能率協会マネジメントセンター)がある。 一般社団法人CQラボ主宰。
目次
外国人の部下の課題に寄り添えなかった失敗から
「当時、部下から分厚いカタログを投げつけられまして」
包み隠さず話してくださったのは、三谷産業株式会社の取締役海外事業担当・ベトナム事業企画促進室長である三浦秀平さん。
同社は石川県・東京都に本社を置き、化学品、樹脂・エレクトロニクス、情報システム、空調設備工事、住宅設備機器、エネルギーという、6つの事業領域を広げています。一方で1994年からベトナムに進出。現在7社17拠点から成る「Aureole(オレオ)」グループを展開しています。Aureoleグループは約2,300人のベトナム人社員が働く中、日本人駐在員は20人程度に過ぎません。
三浦さんは同社で約20年にわたり、このベトナムの事業をけん引してきた存在です。ですが就任当初は苦労もあったそう。
大学卒業後に大手設計事務所に勤め、2004年からベトナムと関わってきた三浦さん。縁あって三谷産業に入社したのは2006年のことです。ベトナムで2年働いてきた経験から、三浦さんにはベトナム人のマネジャーたちを束ねる、いわゆるプロジェクトマネジャーの役割を任せられました。

三浦秀平さんはベトナムで働き20年以上が経つ。
「でも、うまくいかなかったんです。部下であるマネジャーに指示を出すと、彼がまた部下たちに指示をする。ただ、課題があるときにその報告が上がってこなかった。それに気づくまでに時間がかかりました。課題の原因究明や対処については『自分の仕事ではない』と。日本とは違うということに気づきました」
けれども当時は、なぜ違うのかまでは理解しようとせず、マネジャーを責めてしまったといいます。
「結局、彼のモチベーションは非常に下がってしまいまして。険悪な関係が1年は続きましたね」。
これが冒頭の話につながります。
「今考えれば、一緒に何が課題かを見極めたり、解決方法を探ったり、課題解決に向けて相手に寄り添うことが必要でした。社会的背景や文化、特性を理解せずに『自分たちのやり方』を最上段に置くと負の連鎖が起こりやすい。こうした認識もCQを通じて整理された部分がありますね」
制度を相手国に合わせていく必要性

Aureoleグループの工場
さらに具体的に三谷産業では、どんな寄り添いがあったのでしょうか。三浦さんは人事制度を例にとって話してくれました。
「2006年当時にベトナム現地にあった人事制度・目標管理制度は、言ってしまえば日本の本社で使われているものをベトナム語に翻訳しただけ。すると日本的というか、役割の規定が曖昧なんですよね。例えば『マネジャー職は仕事に対して、より大きな責任を持つ』という言葉は人によって解釈が異なる。おそらくベトナムでの『大きな責任』とは『トップダウンで部下にしっかり指示を出す』という理解だったと思います」
現地の文化を許容した新しい制度設計の必要性を感じたそう。けれども、どう取り組めばいいのか――。
契機は、日本本社への異動でした。社長室長に就いた三浦さん。そこで日本本社の考え方、組織の特徴、キーマンなどの理解が深まったといいます。
「日本本社を深く理解できたことが、ベトナム事業を成功させるための制度やマネジメントの仕組み作りに役立ちました。具体的にはベトナム各社のルールをそろえてガバナンス強化を図る。そのためのグループの内部統制、人事労務などを担う会社を立ち上げました」
ただ当初は、ベトナム人の社員からの「面倒だ」といった反発も。三浦さんはそこでも、相手に寄り添います。ベトナム人の社員に対して取り組みの目的などを丁寧に説明。ときにはベトナムの工場に寝泊まりもしたそうです。
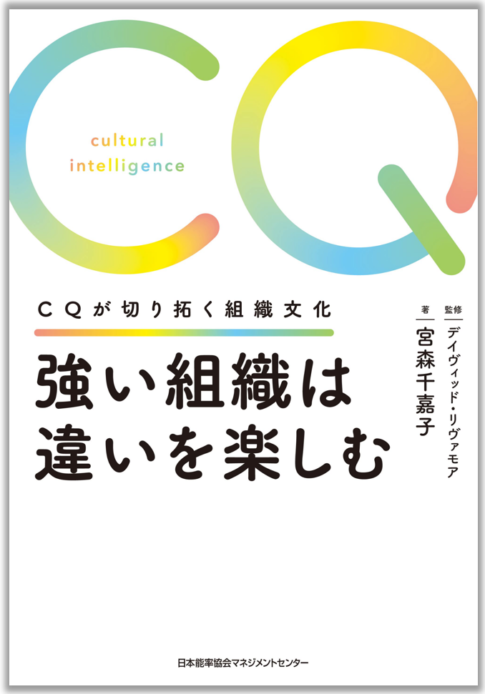
【こんな方におすすめの一冊】
- 組織に課題感がある人事担当者
- 組織文化の変革に取り組みたいマネジャー・経営層
- 多様性を活かしたリーダーシップやチームマネジメントに関心のある方
- 異なる背景や価値観を認識し、チームとして最大化する思考を身につけたい方
ベトナムと日本との相互理解

Aureoleグループのオフィス
今、同社の人事制度は、さらにその先を見据えています。
「日本本社には、日本で採用したベトナム人の社員も少なくありません。その人たちは、事業部門のほか人事や財務、監査などの部門をローテーションしていきます。そこで現在、日本のマネジメントを知った人たちが将来的にベトナムの経営幹部となっていけるような、社内スキームを作ろうとしています」
今後は日本への理解を踏まえたベトナム人の社員が、双方の橋渡し役を担うことも期待できるでしょう。日本本社への理解を深めた三浦さんが、両国の違いを踏まえた制度設計につなげたように。
もちろん一方では日本人社員への施策にも取り組んでいます。日本から現地への駐在などのスキームも整え始めました。
「日本人は日本人で、ベトナムのことをきちんと理解しなければいけません。日本の事業もベトナムの事業もひっくるめて見られる人を増やしたいですね。当社はベトナムの事業を長く続けていきたい。時間はかかると思いますが、ベトナムと日本のそれぞれの仕組みで、好循環を生み出したいです」
と三浦さんは声を強めます。CQとは<違いに橋を架け、ポジティブなエネルギーに変える力>。その観点は特に、違いとの向き合い方に強く表れると言えます。
CQを通じて“文化の違い”の理解が深まる
さてここまでで、CQは海外経験の長さや語学の堪能さとは違う力だとちょっとイメージしていただけたのではないでしょうか。海外駐在が長くてもCQが低い方もいますし、海外経験がなくてもCQが高いこともあり得ます。
三浦さんがCQを知ったきっかけはアイディール・リーダーズ提供の「エグゼクティブ・コーチング」でした。そこで宮森千嘉子さんから教わったといいます。
「月1回程度のコーチングでは、CQの観点で非常に的確なアドバイスをいただいています。また、これはCQにも通じると思うのですが、宮森さんご自身がいつも相手の話をしっかり聞き、相手を否定することがありません。相手の特徴や違いを理解・把握した上でレスポンスをされていると感じます」
ベトナムですでに多くの課題を乗り越えてきた三浦さんでしたが、CQを知ったことで文化の理解は一層深まりました。
「特に『7つの組織モデル』は分かりやすかったですね。日本の組織は『職人型』の傾向があり、ベトナムは『家族型』。両者の相違点が把握できました」
7つの組織モデルとは、文化の傾向を7つに分類したもの。
「不確実なことを避けたいと考えるのか、受け入れるのか」「ピラミッド構造の組織を好むのか、フラットな組織を好むのか」などから分類されています。
「ベトナムは歴史や地勢の関係もあり、トップダウン型のマネジメントが機能している。日本もトップダウン型の傾向はあるかもしれませんが、その場その場で調整したりしますよね。文化が異なれば、目的に向かうプロセスも違います。違う国や文化の人たちと一緒に物事を進める上では、やはりその違いを認識しなければなりません。その点で、CQを通じた考え方や行動が非常に有効だと感じています」
違いを楽しむということ
「ベトナムの人はとても優秀です。AIやITを活用した業務効率化は、日本よりも得意だと思いますよ」
三浦さんは続けます。
「例えば社内決裁にRPA(Robotic Process Automation)導入を提案してくれたりするんですよ。役職者ごとの確認を仰ぐようにしていたところに『三浦さん、決裁が楽になりましたよ。ボタン1つで社長の確認まで進みます!』。要は途中の承認行為が全部自動化されていて……」
ちょっとびっくりしてしまうようなエピソードですが、三浦さんはどこか楽しそうに話します。
「もちろんそれだとガバナンス上良くないですよね。そこで一つひとつ指導していく。『けれど〇〇さんは、いつも十分に見ないで承認していますよね』という意見が出てくれば『なるほど。承認する人が多いなら減らそうか』などと業務プロセスを見直すきっかけになる。それを元に日本側へも提言ができますよね。これは非常に面白いと思うんですよ」
システム開発はベトナム側に、一方でガバナンスの観点でのチェックは日本側に。相手を活かしつつ、日本本社として大事にしたいビジョンなどは守るようにきちんと一線を引く。
こうした組み合わせは、それぞれの違いがあってこそ。違うからこそ強い組織をつくれていると言えるのではないでしょうか。
未来を見据えて文化の違いを活かす

グループの30周年式典は、元ベトナム(社会主義共和国)計画投資省大臣ヴォー・ホン・フックさんなど多くの方が出席して執り行われた。
2024年、Aureoleグループは30周年を迎えるに当たり記念式典を行いました。
運営主体は現地のベトナム人の社員たち。またこれに当たってグループ全体の行動規範“Aureole Way”を、ベトナム人の社員たちに策定してもらいました。数年ごとに入れ替わる日本人の駐在員ではなく、現地の社員にベトナム事業を引っ張っていってほしいという想いの表れです。
三浦さんはCQを高めていくことで組織文化が変わっていく実感があると話します。
「同じ想いを持つ仲間が増えていることを強く感じます。ポイントはやはり、他の人をいかに巻き込むか。以前は現地の方を中心に巻き込んでいました。けれど、やはり日本の本社があるわけで、日本側も巻き込まないといけない」
そうは言っても、両者のあいだに立つことは大変ではないのでしょうか?
「もちろん大変なこともあるかもしれません。けれども、いろんな国の人が一緒になって、会社を成長させていくことはもう特別なことではありません。日本国内においても自国だけで事業が成立するとは、おそらく皆さんも考えていませんよね。遅かれ早かれ、必ず皆さんその壁に突き当たると思うんですよ。そのときにCQをもって異なる文化を理解していく。共通点は強みとし、相違点はどう活かすかという思考に転じていけば、強い武器になると思います」
今後ますます、異なる文化を持つ人たちとの共創は重要です。その際にCQを高めることで、違いを乗り越え、楽しむことにつながっていくことでしょう。

Aureoleグループは人材育成をテーマとする「Aureoleカンファレンス」を毎年開催。写真は2023年に宮森千嘉子さんがパネリストとして参加したときの様子。







