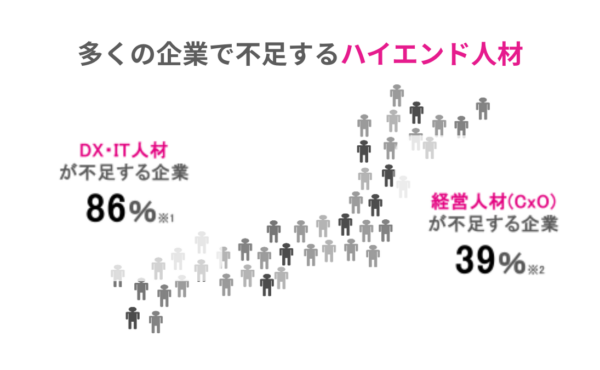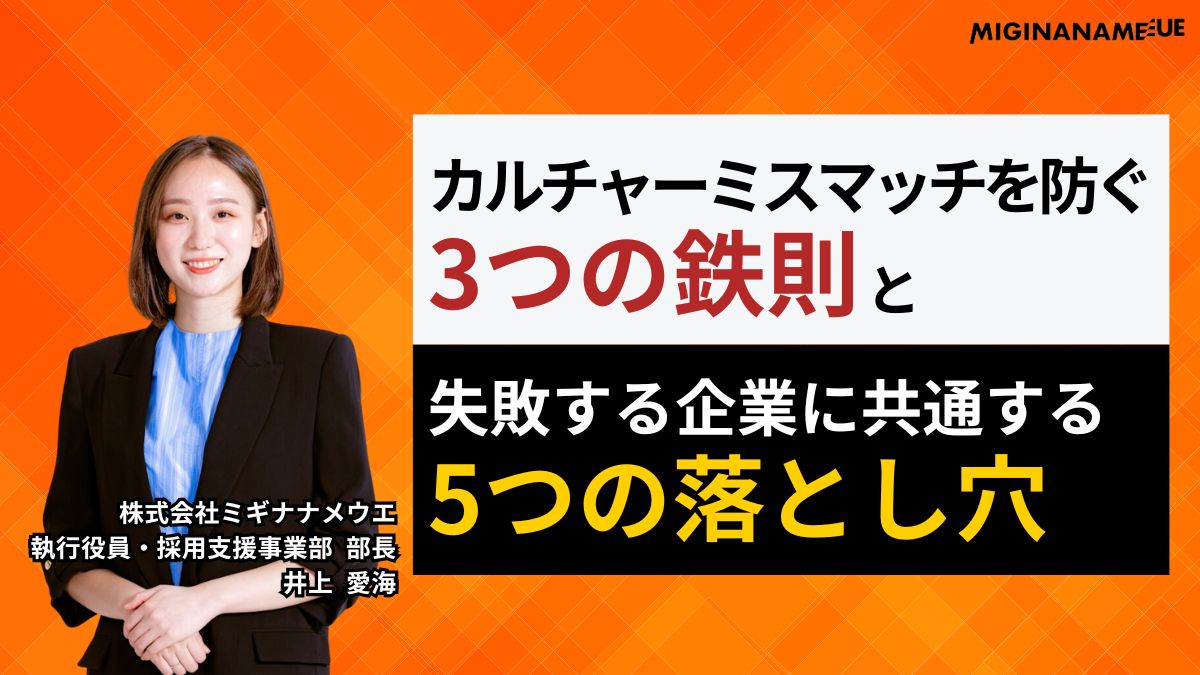
採用活動では「スキルマッチ」ばかりが重視されてしまいがちですが、「カルチャーマッチ」も非常に重要な要素です。というのも、自社のカルチャーや組織に合っていない人材を採用してしまうと、組織は一瞬で崩れてしまうのです。
今回は、採用においてミスマッチが発生しやすい「5つのポイント」と「3つの鉄則」について、累計400社以上の採用を支援してきた「即戦力RPO」で収集したメソッドをもとに解説いたします。

寄稿者井上 愛海 (いのうえ まなみ)氏株式会社ミギナナメウエ 執行役員/採用支援事業部 部長
2019年8月、株式会社ミギナナメウエに入社。東京大学大学院所属。入社以来、採用コンサルタントとしてベンチャー/スタートアップ企業を中心に異例のスピードで採用成果を構築。2021年に事業部責任者、2022年9月には執行役員に就任。現在は、累計400社を超える顧客様の採用を支援し、新卒〜CXOクラスまで独自のマーケティング戦略によって次々と採用を成功させている。
目次
1. 近年の採用で多発する「カルチャーのミスマッチ」の危険性
現在、採用市場は人口減少の影響を受け、かつてないほどの売り手市場となっています。
その中で、多くの企業は他社よりも早く、そして採用目標を達成するために人材を確保しようと焦り、採用基準を緩和してしまうことがあります。それにより発生する「妥協採用」は、一時的に人数を揃えられても、長期的には組織全体の生産性低下を招きかねません。
また、「スキル面だけが理想的な人材」を採用しても、自社の社風やカルチャーとマッチしていなければ、既存社員との間で齟齬が生じるリスクが高まります。
そのような、カルチャーミスマッチの人材がもたらす最大の問題は、早期離職と社内士気の低下です。
自社の働き方やカルチャーに共感していない人材は、採用しても結局早期離職されてしまい、採用期間やコストが無駄になってしまったり、既存メンバーのモチベーションまで悪影響を受けるため、結果的にたった1人のカルチャーのミスマッチが組織全体のパフォーマンスの低下を引き起こしてしまいます。
一方で、カルチャーマッチした人材を採用できると、いわゆる「人材の掛け算の効果」が生まれ、メンバー同士が相互に協力することで、さらに質の高いアウトプットが生まれるようになったり、組織全体の推進力が強くなったりと、企業の成長にとってかなりプラスに働くようになります。
このように、採用活動において基本的なスキル要件とともに重要な「カルチャーマッチ」の要素ですが、定量的な判断が難しいことからなかなか採用業務に取り入れにくいことが問題です。
そこで何が原因なのか、どのフェーズでどのような施策を行えばいいのかを理解し、取り組むことが重要です。
2. カルチャーのミスマッチが起こる企業に共通する5つの落とし穴
まず、自社含め400社以上の採用現場に携わってきた中で、カルチャーのミスマッチが発生しやすいシチュエーションを以下の5つに洗い出しました。
- 候補者のスキルが優秀で判断力が鈍ってしまう
- 採用目標が未達で、妥協してしまう
- 候補者の営業力が高く「マッチしている」と思わされてしまう
- 現職と前職の組織風土ギャップが激しい
- 現場のメンバーが採用に関与していない
2-1. 候補者のスキルが優秀で判断力が鈍ってしまう
選考の場に採用要件ドンピシャの人材が現れると、現場がうまく回るイメージがつき「なんとしてでも採用したい」という気持ちが強くなってしまいます。
その結果、選考時の見極めが甘くなってしまい、カルチャーのマッチ度合いを見誤ってしまう可能性が高まります。
2-2. 採用目標が未達で、妥協してしまう
期日が迫っている中で、採用目標を達成できていない状態では、「普段であれば採用しないが、活躍してくれるかもしれない」と、妥協して内定を出してしまうことがあります。
焦っている時こそ慎重に、カルチャーマッチを見極めましょう。
2-3. 候補者の営業力が高い
候補者の営業力が高いということは、つまり「面接官が自分に何を求めているのか」を察知して適切な回答をする能力が高いということです。
この能力そのものは問題ありませんが、その候補者にとって面接を受ける目的が「自分に合う企業を探すこと」ではなく「どこでもいいから内定をもらうこと」な場合、面接で適切にすり合わせができず、入社後にミスマッチが発生しやすくなります。
2-4. 現職と前職の組織風土ギャップが激しい
例えば、大手企業からベンチャー企業、公務員から民間企業への転職のケースで発生します。
隣の芝生が青く見えてしまうが故に「今いる環境から別の環境に変えたい」というニーズで転職した結果、「自分にとっての当たり前」を大きく変える必要があるため、入社後のミスマッチが起こりやすくなります。
このケースでは、面接ですり合わせる時間を十分に設けていても、候補者側はこれまでの環境とは違うため働くイメージがつきづらく、アトラクトの言葉をそのまま受け取ってしまったり、都合良く解釈してしまうことがあります。
2-5. 現場のメンバーが採用に関与していない
選考に現場のメンバーを絡めるかどうかは、企業の採用方針やリソースによって変わると思います。
しかし、候補者が人事や経営陣に対して出す一面と、メンバーに対して出す一面が全く異なることよくあり、管理職に対して礼儀正しく接していたにも関わらず、自分よりジュニアだと判断したメンバーに対して横柄な態度をとる人も一定数いることを念頭に、人事や役員面接で所感がよかった候補者もしっかりと見極めるようにしましょう。
3. 【離職率が35%→10%以下に】カルチャーマッチ採用の事例
実際に、どのようにカルチャーマッチ採用を進めていくのかについて、人材事業を展開し年間50名以上の採用を行っている、弊社の事例を元にご紹介します。
弊社では、インターン組織から正社員主体の組織に移行した当初、カルチャーにマッチしていない人材を採用して派閥が生まれたり、社員の士気が低下したりして離職率が35%を上回った時期がありました。
そこで、カルチャーの言語化や社内ラジオなどの施策を動かしつつ、「カルチャーマッチ人材の採用」を重視し、以下のような施策に取り組みました。
- 面接を“選ぶ”から“すり合わせる”に変更
- 経営陣自らカジュアル面談や一次面接に参加
- 選考参加者向けの広報コンテンツ(記事・YouTube)を配信
- 面接後の言語化とナレッジ化
- 適性検査の導入
まず、そもそも面接を選ぶ場から「認識をすり合わせる場」に変更したことです。人を選ぶというスタンスではなく、弊社のカルチャーについて本当に理解してもらえているか、経営陣や人事以外のメンバーから見てもマッチしているかを判断するようにしました。
次に、見極める場でありつつもアトラクトも必要であるため、最も自社を語れて候補者をアトラクトできる経営陣が面談や選考に参加することも決定し、かなりの時間を割くようになりました。
また、広報コンテンツを拡充させ、カジュアル面談前・面接後などのフェーズ別や職種別でそれぞれの候補者に適したコンテンツを共有することで、弊社とのマッチ度を判断してもらったり、選考段階でカルチャーに馴染みを持ってもらえるよう取り組みました。
そして、面接後には、必ずよかった点と懸念点をできるだけ明確に言語化し、採用担当者の間で共有することで担当者間で評価基準などをナレッジ化したり、「この部分は懸念にならないのではないか」と評価のズレを見つけることもできています。
最後に、適性検査の導入です。適性検査を導入して既存社員の特性やカルチャー、候補者の志向性を定量的に判断できるようになったおかげで、そのデータを採用に活かすことができ、導入前と導入後で明らかに採用の質が向上しました。
上記のような取り組みを行った結果として、弊社は月間4-5名の採用目標を達成し続けながらカルチャーマッチ人材を採用し、離職率を35%→10%以下まで下げることができました。
4. カルチャーミスマッチを防ぐ3つの鉄則
では最後に「カルチャーミスマッチを防ぐ3つの鉄則」についてご紹介します。
- カルチャーの言語化を徹底する
- 選考中の方のみ閲覧できるコンテンツを作成する
- 本音を引き出せる関係値構築を行う
4-1. カルチャーの言語化を徹底する
まず、大前提としてカルチャーミスマッチを防ぐためにはカルチャーの言語化を徹底することが重要です。カルチャーのミスマッチが発生する根本的な理由は、前述したとおりカルチャーという概念が定性的であり、人によって解釈が異なりやすいからです。
たとえば「チームワークを大切にする」というカルチャーでも、それを「メンバー同士が対等に意見を出し合える環境」と解釈するのか、「リーダーの指示にとにかく素早く応える」と解釈するのかによってそのカルチャーによって引き起こされる実体が全く異なります。
そのため、掲げているカルチャーや、言語化されていない要素を細分化し、具体的な行動指針や事例ベースとして言語化することで、カルチャーのミスマッチを格段に減らすことができます。
4-2. 選考中の方のみ閲覧できるコンテンツを作成する
次に、広報においては「選考中の方のみ閲覧できるコンテンツを作成する」ことがポイントです。採用広報コンテンツを作る際、より多くの方の認知を獲得するためにターゲット層よりも広く訴求をしてしまうケースがよくあり、結果として実際求めている方よりもズレた方に応募されてしまいます。
しかし、打ち出す訴求を狭めてしまうと母集団が減ってしまうため、選考に参加した方のための広報コンテンツを作ることをおすすめします。
前述の通り、これは弊社でも行っている施策で、母集団形成のためのコンテンツと選考中にカルチャーマッチ度合いを判断してもらう材料としてのコンテンツを作ることで、募集の段階でスクリーニングしすぎることなく、選考時でミスマッチの誘発を防ぐことができます。
4-3. 本音を引き出せる関係値構築を行う
最後に、面接時のポイントは本音を引き出せる関係値構築を徹底することです。 面接の中で質疑応答だけを繰り返していくのではなく、例えば「面接官自身の失敗談」や「苦労した経験」を自己開示することで、候補者側も自己開示しやすくなり、より素に近い状態で話してもらえるようになります。
また、あらかじめ「候補者を見極める場」ではなく「相互にマッチしているかを見極める場」であることを共通認識として伝えておくことも重要です。
世間一般的に、面接は「企業が候補者を見極める場」として認識されているため、候補者側が「自分と企業がマッチしているか」を主体的にすり合わせていく意識が弱く、結果としてミスマッチな状態で採用することに繋がるため、候補者にも面接の目的を伝え、本音を引き出せる場を整えるよう意識しましょう。
5. まとめ
採用において、カルチャーマッチは後まわしに考えられてしまうことが多いと思います。確かに、中途採用やハイクラス人材の採用ではスキルマッチが前提ではありますが、特に組織規模の小さいベンチャー・スタートアップ企業やポテンシャル採用であれば、カルチャーマッチは非常に重要な検討項目です。
弊社ではベンチャー企業から上場・大手企業まで400社以上のご支援実績がございますので、カルチャーマッチ採用の施策や、ミスマッチによる早期離職、面接官育成などに課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。