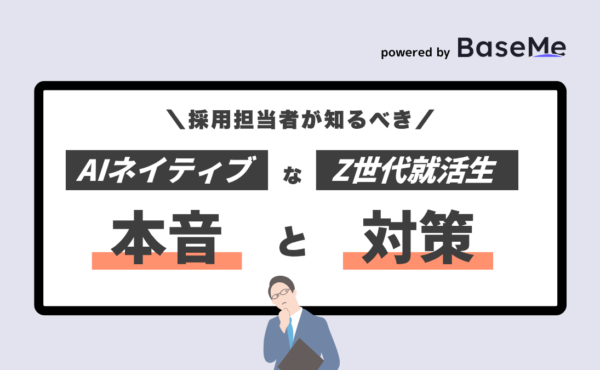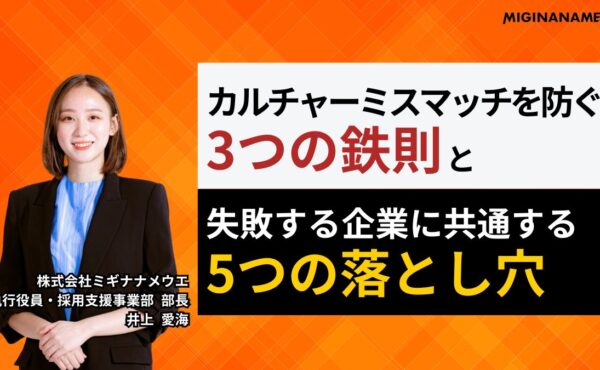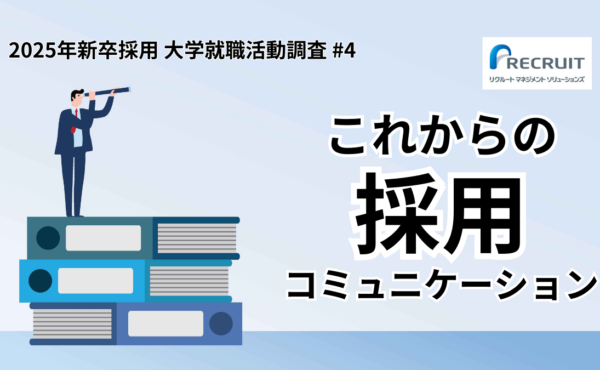2024年11月28日、リクルートダイレクトスカウトを展開する株式会社リクルートが「人材超予測」のイベントを開催しました。本記事では、そのイベントの内容について、イベントレポートとしてご紹介します。
人材の未来を語ると題し、サントリーHDの新浪剛史社長、リクルートHDの瀬名波文野COOが「コーポレート」から「ビジネス」、そして「経営」に至るまで、多彩な視点で人材論を徹底的に掘り下げていただきました。
トップリーダーたちが考える未来のビジョンと、そのリアルな視点を肌で感じるチャンスとして、自身のキャリアをアップデートするきっかけとなる内容が盛りだくさんです。
ぜひ、ご一読ください。

新浪 剛史|サントリーホールディングス 代表取締役社長
ハーバード大学経営大学院を修了。三菱商事入社、その後、ローソン代表取締役社長CEOを経て、2014年より現職であるサントリーホールディングス株式会社代表取締役社長を務める。
公職では、2014年から経済財政諮問会議の民間議員、2019-2020年に全世代型社会保障検討会議、2020年に未来投資会議、そして2023年4月からこども未来戦略会議、2023年5月から新しい資本主義実現会議に参画。2023年4月より経済同友会代表幹事を務める。
Asia Business Council Chairman、三極委員会アジア太平洋委員長、米日財団副理事長に加えて、世界経済フォーラムInternational Business Council、米国外交問題評議会Global Board of Advisors、米国The Business Councilのメンバーとして、グローバルに活躍。

瀬名波 文野|リクルートホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 兼 COO
リクルートホールディングス入社。経営企画室を経て、2008年HR領域にて大手企業の営業を担当。
2012年ロンドンに赴任、2014年買収直後の人材派遣会社ADVANTAGE GROUP LIMITEDのManaging Directorに就任。
2018年よりリクルートホールディングス執行役員、Indeed, Inc.のChief of Staffを歴任し、グループのグローバル化を牽引。
2020年取締役就任、2021年より取締役兼常務執行役員兼COOとして人事・総務本部、ファイナンス本部、リスクマネジメント本部、経営企画本部を担当し、グループ全体のガバナンスや、サステナビリティ推進をリード。
Georg Fischer社外取締役、AIガバナンス協会 (AIGA)の理事を務める。

佐々木 紀彦(MC)
PIVOT株式会社 代表取締役社長 「東洋経済オンライン」編集長を経て、NewsPicksの初代編集長に。
動画プロデュースを手がけるNewsPicks Studiosの初代CEOも務める。
スタンフォード大学大学院で修士号取得(国際政治経済専攻)。
目次


皆様、本日はお越しいただきありがとうございます。
これからの時代に求められる人材を深掘りする「人材超予測」ということで、本日はサントリーHDの新浪社長とリクルートHDの瀬名波文野COOと、多彩な視点で人材論を徹底的に掘り下げます。
今の労働市場・転職市場の今後を見通す「人材超予測」
 昨今、人手不足ということで、人材市場の話がよく出てきていますが、今の人材市場を「超予測」するうえでのポイントは何でしょうか。
昨今、人手不足ということで、人材市場の話がよく出てきていますが、今の人材市場を「超予測」するうえでのポイントは何でしょうか。

インフレと人手不足が進行する中で、人材の流動化が重要になります。一人ひとりのスキルアップも行いながら、成長分野へ人の移動を促していくことに、いち早く手を打たなければなりません。
インフレに伴い給料も上がることが望まれますが、現状なかなかそのようにはなっていないことが課題です。給料を上げなければ人材が集まらないという時代に入ったことを認識し、企業も手を打っていかないといけません。
 人材を採用できる企業、できない企業の明暗が分かれてきそうですね。
人材を採用できる企業、できない企業の明暗が分かれてきそうですね。
人材需要の高まりについて、実際に数字としても求人は増えているのでしょうか。
 ちょうど今年の面白いデータが出たのでご紹介しますが、中途採用の割合を増やす会社と、新卒採用の割合を増やす会社で比較した際に、日本で初めて中途採用の割合を増やす会社が新卒採用の割合を増やす会社を上回りました。
ちょうど今年の面白いデータが出たのでご紹介しますが、中途採用の割合を増やす会社と、新卒採用の割合を増やす会社で比較した際に、日本で初めて中途採用の割合を増やす会社が新卒採用の割合を増やす会社を上回りました。
中途採用に力を入れる企業が増えており、実際の転職市場のジョブ数もコロナ前後で右肩上がりと波が来ており、転職者にとっては売り手市場が到来していると言えます。


私が1981年に三菱商事に新卒入社した頃は会社を辞める人は多くありませんでした。
それが、今の時代は、「面白い仕事ができるか」という観点で、5年ほどで新しい企業に転職する方も多く、以前と比べて価値観が随分変わってきたと思います。
 私は、これだけ求人が増えている一方で、日本では転職がまだ海外と比較して増えていないと感じます。転職して給料が上がるイメージも、日本だとなかなかない印象です。
私は、これだけ求人が増えている一方で、日本では転職がまだ海外と比較して増えていないと感じます。転職して給料が上がるイメージも、日本だとなかなかない印象です。
 ここについては、政府との会議でも議論しているポイントですが、これから確実に上がると思っています。その中で、生産性が高く給料の高い組織に移っていく人材が増えていくと考えています。
ここについては、政府との会議でも議論しているポイントですが、これから確実に上がると思っています。その中で、生産性が高く給料の高い組織に移っていく人材が増えていくと考えています。
 求人数・ジョブ数は増えているので、人材が欲しい企業は増えています。転職希望者も年々増えており、日本の転職市場は他国と比較しても発展市場です。会社として転職者を受け入れたい気持ちがある一方で、日本には、将来の展望やキャリアについて考えたことがない方が多く、もう少し転職者側のキャリアに対する考えを変えていく必要があるのではないかと思います。
求人数・ジョブ数は増えているので、人材が欲しい企業は増えています。転職希望者も年々増えており、日本の転職市場は他国と比較しても発展市場です。会社として転職者を受け入れたい気持ちがある一方で、日本には、将来の展望やキャリアについて考えたことがない方が多く、もう少し転職者側のキャリアに対する考えを変えていく必要があるのではないかと思います。
 全世代においてキャリアを深く考えていない傾向にあるのでしょうか。
全世代においてキャリアを深く考えていない傾向にあるのでしょうか。

将来に対して夢を持てない時代が長く、考えても無駄だという諦め感もあるのかもしれませんね。
過去、バブルが弾けたタイミングで、日系企業が最初に行ったことは、人材の育成費を削減し、非正規雇用を増やすことでした。そのような歴史がある中で、自分自身で将来キャリアをデザインするというのは難しい話です。まずは、抜本的にそこから変えていく必要があるのではないでしょうか。

 給料を上げることができなかった理由は、経営者が固定費が上がることを苦しいと感じていたからなのでしょうか。
給料を上げることができなかった理由は、経営者が固定費が上がることを苦しいと感じていたからなのでしょうか。
 事業成長のための投資先として海外にお金を使う傾向にあることが1つの要因だと思います。そこが課題で、いかに投資を日本に戻し、日本の成長を促すことで、結果として働く人の給料にもつながるのだと思います。
事業成長のための投資先として海外にお金を使う傾向にあることが1つの要因だと思います。そこが課題で、いかに投資を日本に戻し、日本の成長を促すことで、結果として働く人の給料にもつながるのだと思います。
 個人としてキャリアを考える人が少ないといったお話もありましたが、キャリアを自律的に考えられる人をもっと増やすために企業としてはどのようなことをやっていけばいいのでしょうか。
個人としてキャリアを考える人が少ないといったお話もありましたが、キャリアを自律的に考えられる人をもっと増やすために企業としてはどのようなことをやっていけばいいのでしょうか。
 正直、本当にいいタレントは取り合いです。売り手市場の中で、企業と従業員は対等という感覚がなければ、良いタレントが退職したり、良いタレントが採用できなくなったりしてしまうと思います。
正直、本当にいいタレントは取り合いです。売り手市場の中で、企業と従業員は対等という感覚がなければ、良いタレントが退職したり、良いタレントが採用できなくなったりしてしまうと思います。
良いタレントに来ていただくために、採用の工夫や制度改革が重要であり、これをやれなかったら企業は淘汰されていくのではないでしょうか。
 「AIによってホワイトカラーは消滅する」とも言われています。本当に売り手市場なのかということに少し疑問を感じる時もあるのですが、その点はいかがでしょうか。
「AIによってホワイトカラーは消滅する」とも言われています。本当に売り手市場なのかということに少し疑問を感じる時もあるのですが、その点はいかがでしょうか。
 AIをどう仕事に使っていくかを考えるのは人間です。AI自体は手段として活用すればいいとは思いますが、やはりクリエイティビティという我々が持っている「考えること」が仕事にとっては重要だと思います。その中で失敗があり、そこから人間は学びます。人間の凄さは馬鹿にできず、人間の仕事が消滅することはないと思います。
AIをどう仕事に使っていくかを考えるのは人間です。AI自体は手段として活用すればいいとは思いますが、やはりクリエイティビティという我々が持っている「考えること」が仕事にとっては重要だと思います。その中で失敗があり、そこから人間は学びます。人間の凄さは馬鹿にできず、人間の仕事が消滅することはないと思います。
 アメリカでは、「テクノロジーによって全ての仕事が代替されることは少ないが、テクノロジーを使いこなす別の人間によって代替されることになる」と言われています。上手に使いこなす人間が、そうではない人間を代替していく流れになるのではないでしょうか。
アメリカでは、「テクノロジーによって全ての仕事が代替されることは少ないが、テクノロジーを使いこなす別の人間によって代替されることになる」と言われています。上手に使いこなす人間が、そうではない人間を代替していく流れになるのではないでしょうか。

 ここで議論が分かれそうなテーマを入れ込みますね。
ここで議論が分かれそうなテーマを入れ込みますね。
私は、日本人でキャリアを考えている人が少ない背景には、同じ会社で働き続ける方が多かったからだと思っています。以前、新浪さんが発言された「45歳定年制」は一部誤解を生じる印象を与えてしまったものの、キャリアを考える節目といった観点では良い考えだと私は思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
 たとえば45歳で辞めるとなると「どんなスキルを身につけるべきか」「これからのキャリアをどう歩むべきか」など、30代で自分が何をすべきかを考えるはずです。大企業は定年が60歳〜65歳ですので、将来のキャリアを考えることを先伸ばしにする傾向がありますが、自分の人生を早い段階で考えるきっかけを作っていくことが重要ではと考えています。
たとえば45歳で辞めるとなると「どんなスキルを身につけるべきか」「これからのキャリアをどう歩むべきか」など、30代で自分が何をすべきかを考えるはずです。大企業は定年が60歳〜65歳ですので、将来のキャリアを考えることを先伸ばしにする傾向がありますが、自分の人生を早い段階で考えるきっかけを作っていくことが重要ではと考えています。
 私もその考え方には賛成です。私の世代は40歳を超えていますが、ある種の諦めや、得意不得意など、40代になってわかる人生の優先順位がだんだん出てきます。
私もその考え方には賛成です。私の世代は40歳を超えていますが、ある種の諦めや、得意不得意など、40代になってわかる人生の優先順位がだんだん出てきます。
40歳以降で、どのように生きたいかが見えていないと次の一歩を踏み出すことが難しく、その時点でぐずぐず考えるのはとてもきついと思います。

私も商社に入社後、「このままでいいのか」と他の会社を探したこともありましたが、なかなか転職先がない時代でした。優秀な方々の中で役員になれたとしても、50歳頃になることが明白でした。
そんな時に社外の勉強会に参加し、海外に目を向けている先輩が近くにいて、自分も留学をして経験を積むことを決意しました。その時思いましたが、自分の人生を自分で決めることが大切だと思います。
大きな会社では自分で決められない要素も多いです。そのため「自分が決められる要素を自分で作る」というスタンスで、自分で判断してきましたね。

 リクルートさんの制度は日本の最先端で、今やグローバル企業としてもトップクラスだと思います。瀬名波さんは、海外の他企業の制度も見てこられた中で、どのように制度を作っていくのが良いとお考えでしょうか?
リクルートさんの制度は日本の最先端で、今やグローバル企業としてもトップクラスだと思います。瀬名波さんは、海外の他企業の制度も見てこられた中で、どのように制度を作っていくのが良いとお考えでしょうか?
 事業内容・企業規模次第で、最高の制度は千差万別だと思います。
事業内容・企業規模次第で、最高の制度は千差万別だと思います。
我々も国内でやっていること全てを海外に転用しようとせずに、むしろ現地では現地のやり方でどう伸ばしていくかを重視していますね。
ターニングポイントを見通す「リーダーたちのキャリア」
 ここからキャリアのターニングポイントに移れればと思います。新浪さんの一番のターニングポイントはいつだったのでしょうか。
ここからキャリアのターニングポイントに移れればと思います。新浪さんの一番のターニングポイントはいつだったのでしょうか。

給食会社の社長時代ですね。三菱商事にいたときは、世の中のことがわかっていなかったと感じました。人の上に立って働く際にどのようなことを考えればよいか、全くわからなかった。現場に飛び込み、わかりやすく伝えないと人は動いてくれません。
そこから経営について考えるようになりましたね。
 ありがとうございます。瀬名波さんのキャリアのターニングポイントもお伺いしてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。瀬名波さんのキャリアのターニングポイントもお伺いしてもよろしいでしょうか。
 海外の事業部に移った時ですね。20代後半の時に手を挙げて、国内事業から海外事業に移動して、29歳で現地法人の社長に就きました。それまで管理職に興味はありませんでしたが、ある経営者の話を聞き、雷に打たれたように憧れて、どうやったら自分も近づけるかと考えてました。そんな時に、社内公募で海外事業の応募があり、要件を何も満たしていませんでしたが申し込むことにしました。
海外の事業部に移った時ですね。20代後半の時に手を挙げて、国内事業から海外事業に移動して、29歳で現地法人の社長に就きました。それまで管理職に興味はありませんでしたが、ある経営者の話を聞き、雷に打たれたように憧れて、どうやったら自分も近づけるかと考えてました。そんな時に、社内公募で海外事業の応募があり、要件を何も満たしていませんでしたが申し込むことにしました。
結果、書類選考が通り、面接にも受かり、そして、買収直後の会社の社長の側近というかたちで、日本人が誰もいない中で現地に向かいました。現地の方々からすると、聞いたことのない極東のよくわからない会社に買われ、さらによくわからない20代の姉ちゃんが来たぞ、となるわけで、日本人が一人しかいない中で、どうやって彼らと仲間になっていくか考える必要がありました。
日本の本社からは片道切符で、現地の社長が使えないと言ったら首という状況で。失敗もたくさんして痛い思いもしましたが、一番キャリアを大きく変えた経験ですね。
 最初の3〜4ヶ月は現地のスタッフから拒絶され、暗黒時代だったみたいですね。前社長とも方針が違う中で、よく戦いましたね。
最初の3〜4ヶ月は現地のスタッフから拒絶され、暗黒時代だったみたいですね。前社長とも方針が違う中で、よく戦いましたね。
 自分でやりたいと手をあげている以上、「負けたままでは帰るまい」という思いはありましたね。
自分でやりたいと手をあげている以上、「負けたままでは帰るまい」という思いはありましたね。
あとは、要件を何も見たしていない状態で赴任したため、できなくて当たり前であり、学んでできるようにならなければという考えがありました。
 お二人の共通項として、日本人として海外に乗り込んで開拓していったことが言えますね。
お二人の共通項として、日本人として海外に乗り込んで開拓していったことが言えますね。
 その業界や組織の常識を持ち合わせていないことは、逆に良かったのかもしれません。知っているかどうかより「なんか面白そうだな」と思うことが重要で、逆に知っていることがバリアになることもあります。そういう意味では、知らないということは決して悪いことではないと思っています。自分が情熱を燃やせるかが重要だと思います。
その業界や組織の常識を持ち合わせていないことは、逆に良かったのかもしれません。知っているかどうかより「なんか面白そうだな」と思うことが重要で、逆に知っていることがバリアになることもあります。そういう意味では、知らないということは決して悪いことではないと思っています。自分が情熱を燃やせるかが重要だと思います。
 知らないことは悪ではない。まさしくですね。瀬名波さんも経営を立て直すのは大変だったと思いますが、実際に現地ではどのようなことをされたのですか?
知らないことは悪ではない。まさしくですね。瀬名波さんも経営を立て直すのは大変だったと思いますが、実際に現地ではどのようなことをされたのですか?
 経営に対しては、特別なことはしていません。ある意味、赤字転落の危機をどう乗り越えるかは、その当時の単純なテーマの1つでした。しかし、このテーマについて、最初は社長に全然話を聞いてもらえず、挙句の果てにはデータや業績の開示もされないようになりました。
経営に対しては、特別なことはしていません。ある意味、赤字転落の危機をどう乗り越えるかは、その当時の単純なテーマの1つでした。しかし、このテーマについて、最初は社長に全然話を聞いてもらえず、挙句の果てにはデータや業績の開示もされないようになりました。
「このままだと赤字で倒産する可能性もあります」と全従業員に伝えましょうと話したところ、社長は私に「無責任だ」「そんなことをみんなの前で言ったら、いいタレントから他の企業に行ってしまう」「人が抜けた空っぽの会社で立て直す責任は持てないだろ」と一蹴されました。
ただ、このまま収支が合わずに何人もリストラした場合、一緒に働いていたメンバーが何も説明されずに会社を去ることになるのが明白でした。従業員全員で変わる必要があったため、いずれもリスクがあるなら、従業員に伝えた方が勝率が高いだろうと社長に伝えました。
全従業員を集め、社長がみんなの前でプレゼンをして「なぜ変わらないといけないのか」を共有しました。該当スライドになった瞬間、従業員の息を呑む音が聞こえ、4ヶ月目にしてやっと価値ある仕事をしたと感じました。
それから、経営にも少しずつ入り、事業を一緒に動かしていきましたね。

 お二人とも過酷なアウェイ環境で戦う経験をしていることが共通していますね。まさに、転職においてもアウェイの感覚だと思いますが、こういった経験は、自ら積極的に求めた方がよいのでしょうか。
お二人とも過酷なアウェイ環境で戦う経験をしていることが共通していますね。まさに、転職においてもアウェイの感覚だと思いますが、こういった経験は、自ら積極的に求めた方がよいのでしょうか。
 どちらかを選ぶ際は、きつい方を選んだ方が能力開発にはなりますよね。人間は弱いから、心掛けてきつい方を選んだ方がいいと思います。私は、そういう意味で難しい方を選択してきました。
どちらかを選ぶ際は、きつい方を選んだ方が能力開発にはなりますよね。人間は弱いから、心掛けてきつい方を選んだ方がいいと思います。私は、そういう意味で難しい方を選択してきました。
 私は、アウェイがホームになる感覚が大事ではないかと思います。転職先が新しいホームになる感覚は、アウェイだと考えている時には感じられないものです。
私は、アウェイがホームになる感覚が大事ではないかと思います。転職先が新しいホームになる感覚は、アウェイだと考えている時には感じられないものです。
年月が経ちキャリアの材料が揃った際に振り返ると、目の色やカルチャー、食生活も異なる方々と仲間になれたことが、私の人生の財産になっています。
このように、アウェイがホームになる感覚は、やってみて分かりました。本当にアウェイでも一緒にチーム・仲間になれる可能性があり、その感覚があるからこそチャレンジする時にその感覚を転用できます。
 アウェイをホームにする感覚は大事ですね。その感覚があれば、なんでもチャレンジできます。お二人は精神的にタフであり、アウェイにいっても幾分耐えられる印象です。
アウェイをホームにする感覚は大事ですね。その感覚があれば、なんでもチャレンジできます。お二人は精神的にタフであり、アウェイにいっても幾分耐えられる印象です。
 僕は全然そんなことはないですよ。給食会社をやっている時も「辞めればよかった」、「いまから戻れないかな」などと考えてばかりでしたよ。ただ、一つだけタフだと言えるならきついことを選んできたというのはあります。
僕は全然そんなことはないですよ。給食会社をやっている時も「辞めればよかった」、「いまから戻れないかな」などと考えてばかりでしたよ。ただ、一つだけタフだと言えるならきついことを選んできたというのはあります。
 私と似てます。赴任前は、「ビザが取れる前に申請が下りないといいな」とか考えていました。そうなったら、不可抗力で日本に帰れるのにと思ってました。
私と似てます。赴任前は、「ビザが取れる前に申請が下りないといいな」とか考えていました。そうなったら、不可抗力で日本に帰れるのにと思ってました。
 お二人とも徐々にタフになっていったのかもしれませんね。
お二人とも徐々にタフになっていったのかもしれませんね。

質疑応答
①海外と比較した日本の労働生産性
ー日本と同じくらい流動性が少ないイギリスが労働生産性を上げている理由はなぜでしょうか。
 明確に生産性に差があるのは、産業構造そのものの要因が大きいかと思います。
明確に生産性に差があるのは、産業構造そのものの要因が大きいかと思います。

日本の課題は、約70%の労働力を持っている中小企業にあると考えています。中小企業の生産性が上がったら日本の国力は一気に上がります。Aという会社は頑張っていても、Bという会社は補助金を受け取って事業を継続している。健全な競争が起こらない状況では、なかなか生産性は上がりません。
重要なのは、中小企業の新陳代謝を促進することであり、これにより一気に生産性が上がると思います。日本は中小企業(数)が約99.8%を占めます。中小企業を中堅企業にしていくことが日本の成長に繋がると考えています。
 補助金をやめて、M&A税制をもっと優遇していく等すればよさそうですね。
補助金をやめて、M&A税制をもっと優遇していく等すればよさそうですね。
②仕事で悩んだ際の解決方法
ー役職が上がるほど、仕事の相談をしにくくなると思う。お二人は、悩んだ際はどのように仕事の悩みを解決しているのでしょうか。

自分の悩みを打ち明けることは基本的にはないです。同じ年齢の方でも悩みが全然違います。社長同士が集まってもなかなか言いません。ただ、悩んでいるときには、サントリーHD会長の佐治に言われた「悠々として急げ」ということは意識しています。また、歴史から学ぶことを意識し、僕も先人たちと同じようなことを経験しているのか、そうするとこういうことをした方がよいな、などと考えます。
また、自分の時間もなかなか持てないのが実情ですが、働いていることで問題解決になることも多いと感じます。結局、自分で解決するしかないです。あとは、運動を週2回必ずやっています。その際は、忘れられます。
 私は相談をしますが、解決を求めるというより、いったん話してみるということをします。
私は相談をしますが、解決を求めるというより、いったん話してみるということをします。
自分とは考えが異なる人たちの意見を聞くことが効果的だと思います。たまに会う人たちに聞くと「あ、なるほど」という時があります。15歳年下と、15歳年上と話すとかいいかもしれません。
 ともすると、日本だとキャリアのアドバイスを誰からもらえばいいのでしょうか。日本は転職する際に、上司にも同僚にも相談できない風潮があると思います。
ともすると、日本だとキャリアのアドバイスを誰からもらえばいいのでしょうか。日本は転職する際に、上司にも同僚にも相談できない風潮があると思います。
 私には三菱商事の同期で相談相手がいました。その方は転職を多くしていた経験者で、アドバイスをくれましたね。
私には三菱商事の同期で相談相手がいました。その方は転職を多くしていた経験者で、アドバイスをくれましたね。
 私は親、友達、パートナー、先輩等ですね。自分に見えていない視点があるため、違う人に聞くということは意識しています。
私は親、友達、パートナー、先輩等ですね。自分に見えていない視点があるため、違う人に聞くということは意識しています。
これからの時代を担う人材というテーマの答え

 自分で考えて自分で行動できる人が絶対にいいと思います。また、大人の言うことは聞きすぎない方がいいと思います。
自分で考えて自分で行動できる人が絶対にいいと思います。また、大人の言うことは聞きすぎない方がいいと思います。
自分が思うままに行動した方が、たとえ失敗してもpivotできます。そのため、「どうしたらいいのか」を自分に聞き、納得感を持って行動することが大事ですね。魔法はないので、そこを自分で考える必要があります。

瀬名波さんは、これからの時代の人材そのものですね。
重要なのは、思ったらやってみることだと思います。やりたいと感じたら、色々な方の意見を聞くことが重要だと思います。
また、日本の教育に不足していると感じることは、リベラルアーツ、歴史です。これらは意思決定するうえで参考になる、非常に重要な知識です。世界的に起こっている世界情勢が変わった際に、歴史から紐解いて考えてみるなど、自分で考えてみること。迷う時の礎をつくることが重要だと思います。
 お二人とも、貴重なお話しをありがとうございました。
お二人とも、貴重なお話しをありがとうございました。