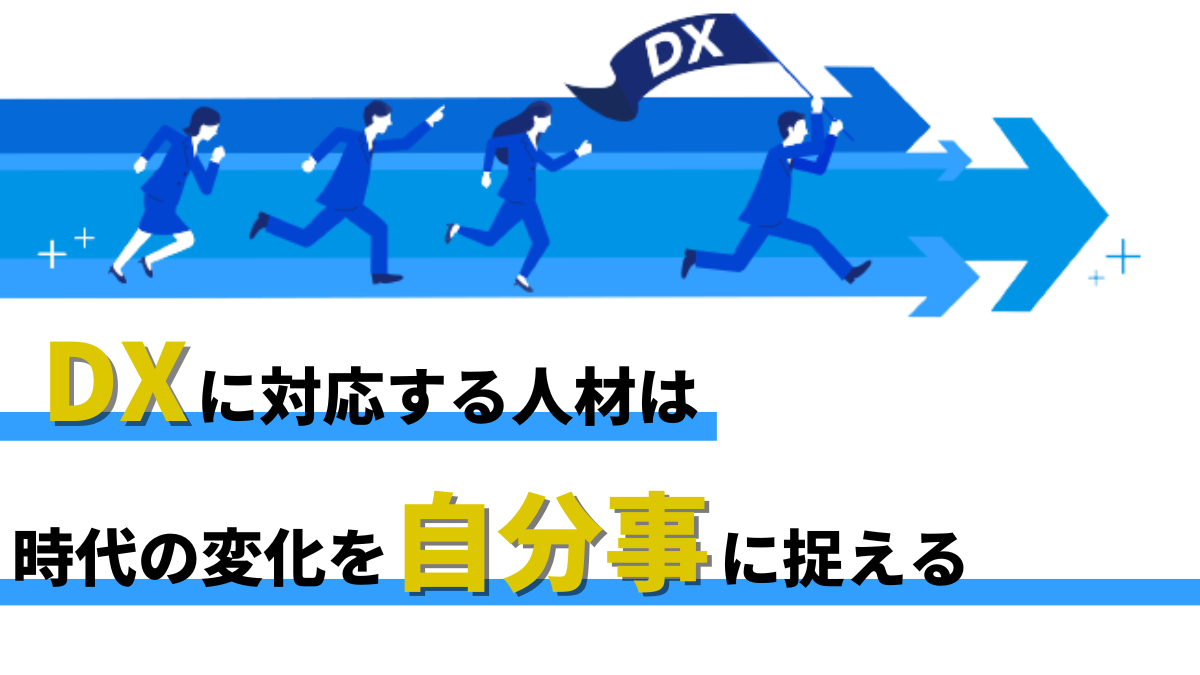
皆様ご無沙汰しております。株式会社WEの戸田です。
今回は、世の中が大きく変革する中で注目されている「リスキリング」について書かせていただきます。

執筆者戸田 裕昭氏株式会社WE 代表取締役 / 上智大学非常勤講師 / 総務省地域力創造アドバイザー
大学卒業後、オフィス家具メーカーにて新規事業創出・地域活性化に携わる。総務省地域力創造アドバイザーや国土交通省スマートアイランド推進実証事業コーディネーターなどを担い、全国各地の地域における事業振興のアドバイスを行なっている。 また、個々人のやりたいことが起点となる事業創出を目的とした伴走型教育プログラムを開発・構築。小学校から大学までの教育機関や自治体、民間企業と連携し、人材育成を軸とした「組織変革」「事業創造」「地方創生」を行う。
1.リスキリングとは
 そもそもリスキリングとは、「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」とされています。
そもそもリスキリングとは、「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」とされています。
近年では、特に「技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、新しい知識やスキルを学ぶこと」が増えています。
では、「技術革新やビジネスモデルの変化」とは、具体的にどのようなことが起きているのでしょうか?それがわからないと対応することはできません。
私が実際に見たり聞いたりしたことから現在の変化を考えてみましょう。
2.DXによる人員配置の効率化が進んでいる
 人間は、誰か(時には「上」の人たち)が決めたことに対して、自分自身がその実施意図や目的を理解しきれていなかったとしても、先に行動することで成果を出してしまう、ということがあると思います。
人間は、誰か(時には「上」の人たち)が決めたことに対して、自分自身がその実施意図や目的を理解しきれていなかったとしても、先に行動することで成果を出してしまう、ということがあると思います。
たとえば、「SDGs」で「貧困を無くそう」と取り組んだ結果、本当に「貧困層が減ってきている」ということを示す数字が出ているそうです。
もちろんすべてが解決したわけではありません。またさらに新しい課題が発生する事態になっています。ただ、結果が出ているという事実は、人間の力によるものだと思います。
そのような中で、最近はどこでも「デジタルトランスフォーメーション(DX)」という言葉を耳にします。
この「DX」も浸透するにつれて成果が見えてきているようで、DXによって、これまで5人を必要としていた仕事が2人で足りる、といったケースも出てきているようです。
身近な部分では「受付」がわかりやすいと思います。私がオフィス家具メーカーで営業していた当時は、企業を訪問するとたいてい受付の方がいらっしゃって、とても親切に対応してくださっていました。受付の方と話すことが楽しいと思える企業さんもあったくらいです。
ただ、今はタッチパネル式の受付システムや電話に変わりました。楽しみの一つが消えてしまったのが残念ですが、テクノロジーによって置き換わったことの表れだと思います。
「DX」により、このようなことが様々な箇所で発生している状況だと理解できます。それでは、これからはさらに何が起きるのでしょうか?
テクノロジーによって仕事が効率化され、その業務に対して人員配置をする必要がなくなります。先ほどの事例のように、5人を必要としていた仕事が2人でまかなえるようになると、3人の手は余ります。
では、その3人はどうなるでしょうか?他の仕事もDXによって効率化し、人員配置の余地がなければ行き先がなくなってしまうのではないでしょうか?
しかし、これを悲観するのではなくポジティブに捉え、「増えた戦力が新しいスキルを身につけて更なる事業拡大をしていけばいいじゃないか!」ということがリスキリングだと思っています。
3.従業員はリスキリングについてどう思っているのか?
 国や企業目線でのリスキリングの必要性は理解できます。しかし、実際に働いている従業員の皆さんはどう思うでしょうか?
国や企業目線でのリスキリングの必要性は理解できます。しかし、実際に働いている従業員の皆さんはどう思うでしょうか?
私は、今までの「教育」と同じ状態になってしまっているのではないかと思います。
皆さんは、教育を受ける過程で、どのような気持ちで勉強していましたか?学校で、学びたくて学んできた方もいらっしゃるとは思いますが、「なぜ学んでいるのかわからない。学んでいることがどのように社会で活かせるのかわからない」といった感情で勉強している方も多いのではないでしょうか?
私はそうでした。学んでいる意味がわからず、苦痛な時間でしかありませんでした。
今になってみると後悔しています。大学時代に「経営工学学科」に所属し、さまざまな視点で経営を学んでいましたが、内容は全く覚えておりません。そんな私が、今は経営者です。戻れるなら大学時代に戻って、きちんと勉強したいです。
この事例からお伝えしたいことは、つまり、「言われたからやる」というリスキリングになっていないか、ということです。上述のように、ポジティブな捉え方でリスキリングを伝えたとしても、従業員の皆さんは、「それは国や会社の勝手な都合だろう。自分たちは今まで通り働きたいんだ!」と、なってしまいます。
4.「学ぶことの本質」がわからないといけない
 では、その「自分たちは今まで通り働きたいんだ!」という従業員の想いは叶うのかというと、残念ながらDXによる効率化によって、その方々のポストがなくなってしまいます。
では、その「自分たちは今まで通り働きたいんだ!」という従業員の想いは叶うのかというと、残念ながらDXによる効率化によって、その方々のポストがなくなってしまいます。
既に某大企業では、事業に対して人手の数が過剰になり、従業員の派遣ビジネスが始まっています。コロナ禍において航空会社が実施した施策がわかりやすい事例かもしれません。こうしたことが、航空会社以外でもDXの浸透によって起き始めています。
そのため、従業員の方には「教育」も「リスキリング」も学びであり、「なぜ学ぶのか?」ということを個々人が理解して学ぶ必要があると伝えることが大事になります。
時間が経ってやりたいことが見つかったり、やらなければいけないことができたりして、今の自分のスキルではできないから学ぶ、といったこともこれからは増えるでしょう。
私自身も、営業を始めてからやっとExcelを勉強しました。大学の授業で扱っていたはずなのに、社会人になってから本を買って勉強しました。
世の中はすごいスピードで変わっています。気がついたらもう手遅れ。そんなことがあったら悲しいですが、人間は、実はそんな時にしか変われないのではないかと思っています。
タバコのパッケージには「健康への悪影響が否定できません」と書かれているのにやめられない方がいます。しかし、「今タバコをやめないと明日には命がないですよ」と言われたら一瞬でやめる方も多いのではないでしょうか。
企業の現場で考えると、「残念ながらあなたの仕事はもう我が社に必要はありません」なんて言われてしまうことが、最悪のケースです。そうならないように、従業員の皆さんが学んでいくことが大事だと思います。
5.学びを進めるためにはどうしたらいいのか?
 では、学びを進めるためには、どうしたらいいでしょうか?
では、学びを進めるためには、どうしたらいいでしょうか?
「リスキリング」の必要性を国や企業が声高に訴えても、実際に自分に対する危機的な状況がこないと、人間は変わりそうもありません。
結局のところは、これまでお伝えしていたことの繰り返しになりますが、リスキリングも従業員の皆さん個々人が目的を理解しないといけません。
- これからの人生をどうしていきたいのか?
- 会社においてどんな自己実現をしていきたいのか?
- 会社にいることで会社にどんな貢献をしていきたいのか?
こういったことについて、従業員の皆さん個々人が自分で納得するまで考える必要があります。
「生きていくとはいったい何なのか?」「自分にとっての幸せは何なのか?」と、今の世の中が勝手に作り上げてしまっている「見えないレール」を取っ払って考える時期が来ています。
「見えないレール」を取っ払って、自分の目的を考えるために、弊社ではオリジナルプログラム「Will Based Learning®」を提供しております。
過去の記事で、このプログラムの要素を書かせていただいているので、ぜひ読んでいただき、従業員の皆様が自分自身と向き合っていっていただくためのきっかけとして、ご検討いただければと思います!
6.最後に

物事には、合理的に行えることと行えないことがあります。
合理的に行えることはどんどんデジタル化していけばいいと思いますが、人は合理的に動くように変えることはできません。丁寧に向き合うという「非合理的」なことが結果を生み出すこともあります。
「向き合う」ことは、「Will Based Learning®」で多く取り組むことができます。何かありましたらいつでも相談してください!!
You’ll Never Walk Alone.
あなたは1人ではありません。私は必ずあなたを応援します!
今回も読んでいただきありがとうございました!次回もよろしくお願いします。







