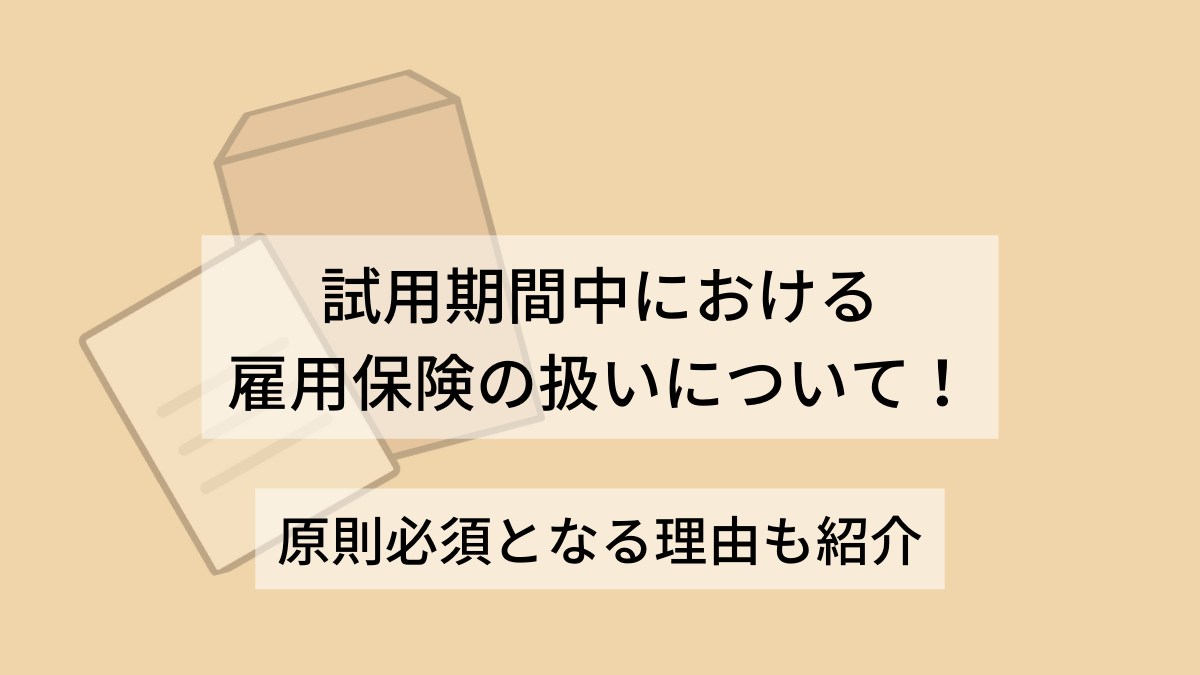
従業員を新たに雇う際に試用期間を設けるケースがあります。試用期間中には、その従業員を本採用するか否かを判断するために業務の能力や適正を幅広くチェックします。
試用期間の時期であっても、その扱いは一般の従業員と変わりません。企業が雇用保険に加入しているときには、試用期間の従業員についても雇用保険に加入させる必要があります。
雇用保険非加入の状態で働かせると大きなリスクを負う可能性もあるので、十分気をつけましょう。
この記事では、試用期間中における雇用保険の扱いについて解説していきます。
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 試用期間中でも雇用保険や社会保険は加入すべき!その理由とは?

企業は試用期間を設け、新たに雇用した従業員の適性をチェックすることがあります。その際気になるのが、雇用保険に加入させるか否かという点です。
雇用保険というと一般社員のみのものであり、試用期間中の従業員は適用外なのではないかと考える方もいます。しかし、試用期間中でも特別な場合を除き、雇用保険へ加入させなければならないので気をつけましょう。
そもそも雇用保険とは、「雇用する従業員の生活の安定や支援を目的とした強制保険」のことです。
健康なときには問題なく働けていても、なんらかの事情で失業したときには収入が途絶えてしまうものです。また、育児や介護などを目的とした休業で収入が減ってしまうケースもあります。
雇用保険には、こういったリスクから従業員を守るという意味合いがあります。雇用保険に加入しておけば万一の際に給付金の支給をはじめとした支援を受けることができ、リスクを最小限に抑えられるのです。
雇用保険法では、企業の事業主は基準を満たす労働者を必ず雇用保険に加入させるよう定められています。特別な事情がないときには、試用期間中であっても従業員を雇用保険に加入させるようにしましょう。
一般的な企業には雇用保険への加入義務があります。株式会社など法人の事務所であれば、事業主が個人で働いている場合でも雇用保険に入らなければなりません。また、個人事務所であっても従業員が常時5人以上在籍するときには雇用保険加入の義務が発生します。
ただし、従業員の働き方によっては雇用保険の適用が除外となるケースもあります。
例えば、1週間の所定労働時間が20時間以内となる場合には、雇用保険への加入義務はありません。また、昼間学校に通っている学生は雇用保険では労働者とみなされないため、雇用保険に加入させる必要がありません。
また、臨時に雇用して6ヶ月を超えない範囲で働く場合など、期間限定で雇用するときにも雇用保険への加入が必要ない場合があります。とはいえ、試用期間を設ける場合のほとんどが長期的な雇用を見込んでいるため、この除外の例に該当することはほとんどないと思います。
こういった特別な条件がある場合を除けば、試用期間であっても雇用保険への加入が必要です。
なお、雇用保険への加入日は原則的に、試用期間初日からということになります。試用期間を終えてから加入させるといった方法は選べないので気をつけましょう。
試用期間初日の段階で業務時間が1週間20時間以内に収まるなどの理由で雇用保険加入が必要ない場合もあります。この場合には、労働時間を増やすタイミングなど雇用保険加入の必要性が生じた段階で即座に加入させる必要があります。
このように、試用期間中であっても雇用契約を締結している状態に変わりないため、不当な待遇にならないよう気を付けましょう。雇用契約の原則や禁止事項について確認しておきたい方は、当サイトで無料配布している「雇用契約手続きマニュアル」もご覧ください。資料では雇用契約の結び方から解雇まで雇用契約の原則についてわかりやすく解説しているため、気になる方はこちらのフォームから資料をダウンロードしてご活用ください。
2. 試用期間中に雇用保険を加入しないリスク4つ

たとえ試用期間であっても、従業員を雇用したときには働かせる初日から雇用保険に加入させましょう。未加入の状態で働かせた場合、多くのリスクが生じることになるので注意しましょう。
試用期間の雇用保険未加入は、従業員と企業双方にとって大きなダメージとなるものです。具体的なリスクを1つずつ見ていきましょう。
2-1. 従業員が必要とする支援を受けられなくなる
雇用保険に加入していれば、失業手当や育児休業給付、介護休業給付といった制度を利用できます。しかし未加入の状態が続いている場合こういった制度についても対象外となるため、万一の際に従業員が必要とする支援を受けられなくなるリスクが発生します。
育児や介護を理由として休業する際に十分な支援を受けられないのは従業員にとって大きな負担となります。また、試用期間中や試用期間満了のタイミングで解雇した場合、雇用保険未加入が原因で失業手当が受けられず、従業員が窮地に陥る例もあります。
試用期間中の雇用保険加入は、従業員を万一のリスクから守るという意味合いがあります。
2-2. 従業員の次の転職が不利になることがある
雇用保険未加入だった場合、その従業員は退職後に再就職手当など就職促進にかかわる給付を受けられなくなってしまいます。
再就職にあたって受けられる給付には再就職手当のほか、就業促進定着手当や就業手当、常用就職支度手当などがあります。これらの給付条件は、前職で雇用保険に加入していることです。
また、再就職の際には応募先の企業に社会保険加入に関する情報が開示されることになります。この情報で雇用保険未加入が発覚しトラブルに発展するケースもあります。
最悪の場合、その従業員が再就職できなくなるおそれもあるので十分気をつけたいものです。
2-3. 罰則の対象となることがある
雇用保険への加入が必要であることを把握していながら未加入の状態にしておくと、是正勧告を受ける可能性もあるので注意しましょう。
違反している事実が認められた場合、まず労働局は企業に対して是正のための指導や勧告を複数回おこないます。それでも違反が是正されなかったときには、懲役6ヶ月以下または罰金30万円以下の罰則が課せられることになります。
これに加え、雇用保険料の追徴金や延滞金の納付を求められることもあります。
複数の従業員を雇用し、試用期間中に雇用保険に加入させなかったという場合、その追徴金や延滞金の金額が高額になるおそれもあります。追徴金や延滞金は基本的にまとめて支払う必要があるため、企業経営に影響するほどの資金的ダメージを負う可能性も考えられます。
2-4. 企業の信頼が失墜するおそれがある
雇用保険未加入で試用期間中の従業員を働かせた結果、企業の社会的な信用が大きく低下するおそれもあります。
試用期間中の雇用保険加入について詳しく把握し、適正な運用を心がけることが大切です。社内で適切な運用ができないときには、弁護士に相談し雇用保険手続きを委託するなどの方法を検討しましょう。
3. 雇用保険の加入を忘れていた場合の対策

もしも、雇用保険への加入義務があるにもかかわらず会社が加入させていなかった場合には、問題に気付いた段階ですぐに対処しましょう。早めに対処すれば、企業や従業員が抱えるリスクを最小限に留めることができます。
雇用保険料はあとから申請すればさかのぼって納付することができます。ほとんどの場合、事情を話して申請すれば2年以上という長期間にさかのぼって雇用保険料を支払うことが可能です。
必要に応じて弁護士に相談するなど工夫し、正しい方法で雇用保険料を支払いたいものです。
4. 試用期間中であっても従業員を雇用する際には必ず雇用保険に加入させよう

雇用保険をはじめとした各種社会保険は、試用期間中であっても加入が必須とされています。
雇用保険に加入させず従業員を働かせたときには、追徴金や延滞金を求められたり罰則を課せられたりする可能性もあります。また、企業の信頼度も下がってしまうことになるので十分気をつけましょう。
例外的な条件がある場合を除き、従業員の試用期間をスタートさせるときには必ず初日から雇用保険を適用させたいものです。
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
--------------------
今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!
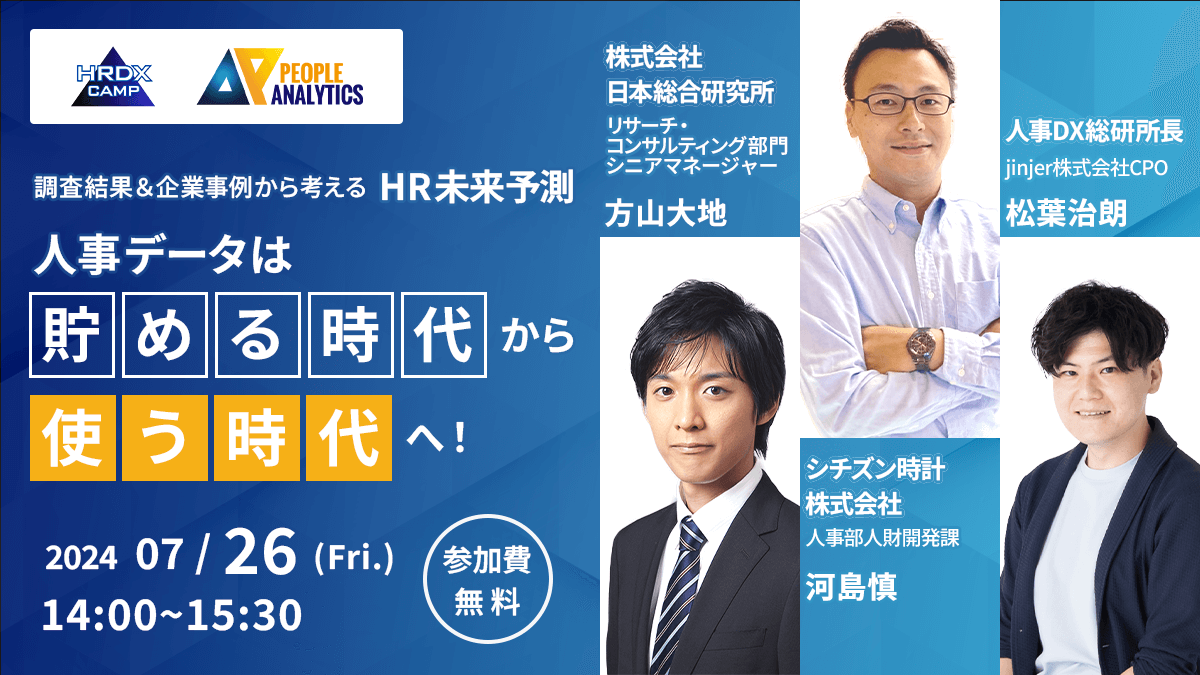
組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?
今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。
【こんな方におすすめ!】
- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない
- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている
- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある










