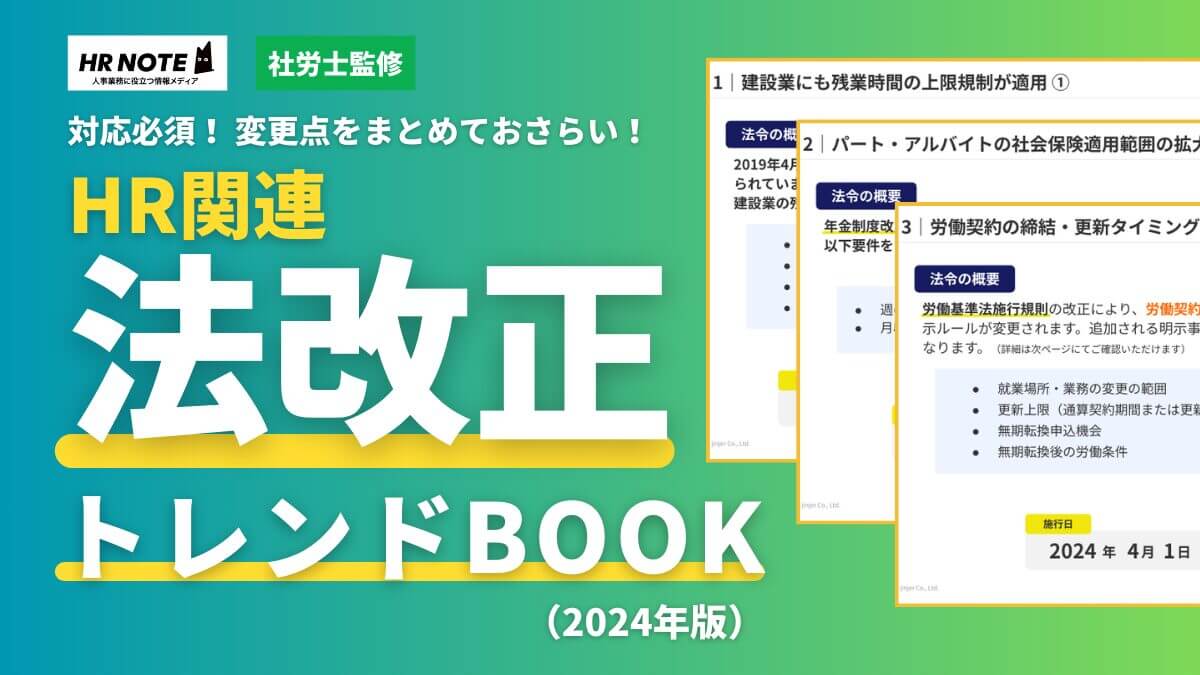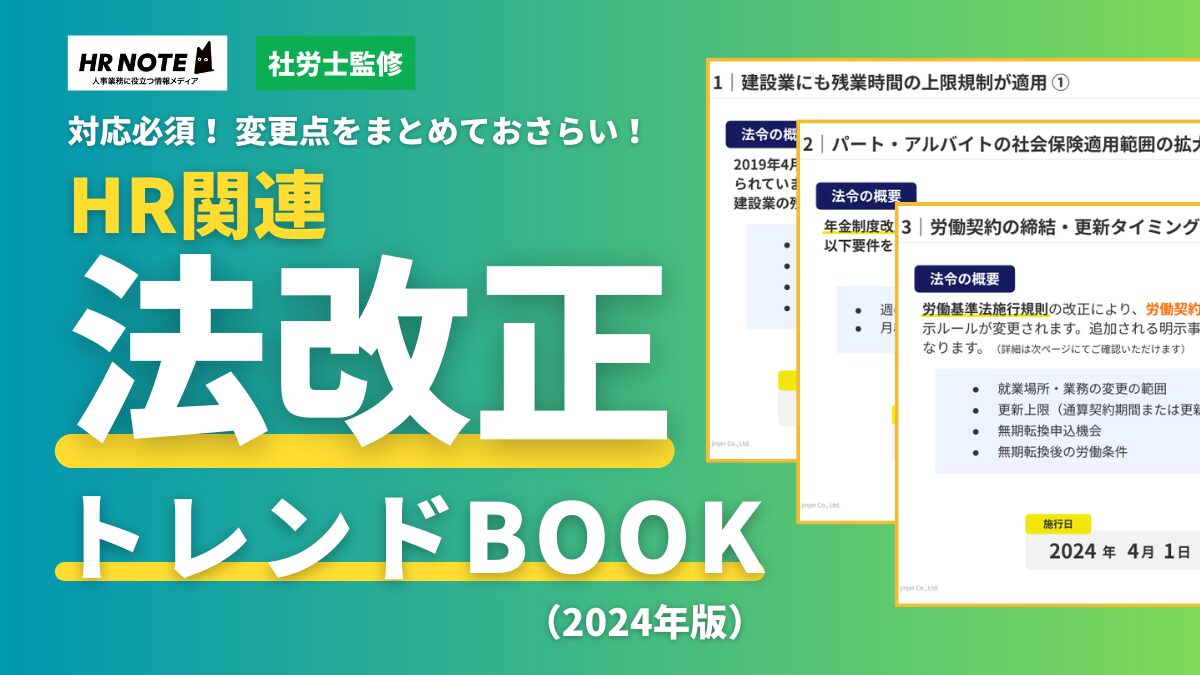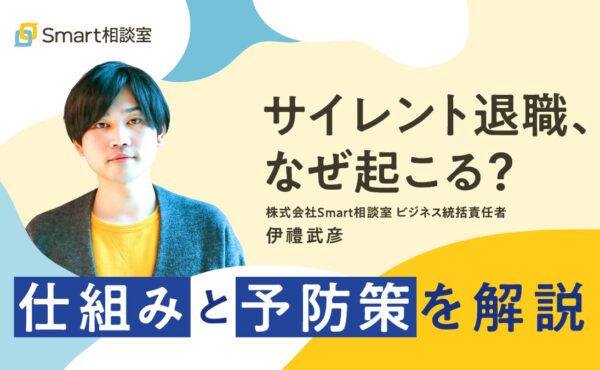残業代の計算は、労使で認識の違いが起きやすい問題です。労働者から残業代請求があった場合、そのまま鵜呑みにするのも、請求を放置することも企業にとっては大きなリスクになります。
厚生労働省によると、2016年に100万円以上の残業代請求があった企業は1,349社。また、それらの企業で支払われた残業代は労働者1人あたり13万円になっています。
「残業代請求」が労働者の中で一般的になってきている近年、残業代の計算方法は労務管理の上で必須の知識となっています。この記事では、残業代の計算方法や労働者から残業代請求をされた場合の対処法などについてご紹介します。
目次
【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版
2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。
2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。
人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。
- 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい
- 社労士が監修した正確な情報を知りたい
- HR関連の法改正を把握しておきたい
という方はぜひご確認ください!
1|残業代の計算方法|割増賃金の考え方

残業代は、大まかに以下の式で計算することができます。
ただし、残業代は、働いた時間帯や労働契約の内容、月の残業時間によって、割増率や計算方法が異なります。この項目では、時間外労働や残業代の計算方法などについてご紹介します。
1-1|時間外労働の考え方
時間外労働の考え方時間外労働とは、一般的に会社で定めた労働時間を超えて働くことを意味します。残業などの時間外労働には、主に以下の3つがあります。
法定内残業
法定内残業とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内で所定労働時間を超えて働いた残業をさします。会社によっては、所定労働時間を1日8時間以下に設定している場合もありますよね。
このような場合、8時間を越えない間の労働は、法定内残業になります。法定内残業は、就業規則で別途定めがない場合には割増のない労働賃金が支払われます。
法定外残業
法定外残業とは、法定労働時間を超えて働いた残業をさします。法定外残業は、法定の割増率以上で計算される割増賃金が支払われます。
深夜残業
深夜残業とは、夜22:00〜翌5:00の間に働く残業のことです。深夜残業をした場合にも割増賃金が支払われます。みなし残業制や裁量労働制などの場合でも、深夜残業について割増賃金支払義務が発生します。
1-2|残業代の割増率
残業代の割増率残業代の割増率は以下の表のとおりです。
| 労働時間 | 5:00〜22:00 | 深夜(22:00~翌5:00) | |
| 所定内労働 | 割増なし | 1.25倍(原則) | |
| 法内残業 | 1日8時間、週40時間以内 | 割増なし | 1.25倍 |
| 法外残業 | 1日8時間、週40時間超 | 1.25倍 | 1.5倍 |
| 1ヶ月に60時間超 | 1.5倍 | 1.75倍 | |
| (法定)休日労働 | すべての時間 | 1.35倍 | 1.6倍 |
残業代計算の際、働いている時間帯や月の残業数などによって変わります。残業代計算の際、働いている時間帯や月の残業数などによって変わります。一定の規模以上の企業では1ヶ月60時間以上の残業代をしている場合、割増率が高くなるので注意が必要です。
1-3|残業代の計算方法
残業代の計算方法残業代の計算式は以下のとおりです。
【1時間あたりの賃金】は基準賃金を月平均所定労働時間で割ると算出できます。なお、通勤手当や住宅手当などの諸手当は通常は基準賃金に含まれません。その後、残業時間数や働いた時間帯などに応じ、割増率を変えて計算すれば、残業代が算出できます。
ここでは、具体的な計算方法を事例とともにご紹介します。
<事例>
Aさんは2月に合計35時間の残業をしましたが、月給は21万5,000円でした。給与明細を見ると内訳は、基本給18万円、住宅手当2万円、通勤手当1万円、主任手当5,000円となっており、残業代は含まれていないようでした。
Aさんの会社の月平均営業日は22日で、所定労働時間は8時間と設定されています。
<計算>
残業代の計算式は以下のとおりです。
まず、【1時間あたりの賃金】を求めます。
【1時間あたりの賃金】= 【基準賃金】/【月平均所定労働時間】なので【1時間あたりの賃金】= 185,000 / (22営業日×8時間) = 1,051円
月の残業時間は35時間で、深夜残業はなかったと仮定すると以下の式ができます。
35 × 1,051 × 1.25 ≒ 45981
したがって、この月の残業代は4万5,981円となります。
2|労働者から残業代請求をされた場合の対処法

労働者から残業代請求をされた場合の対処法労働者から残業代請求の書面が送られてきたら、どのように対処すればよいのでしょうか。未払いの残業代に関しては、支払い義務がありますので、支払わなければなりません。
一方で、残業代請求に対しては、その請求が正当なものか、精査する必要があります。この項目では、労働者から残業代請求をされた場合の対処法についてご紹介します。
2-1|労働者からの請求に反論の余地があるか検討する
残業代の計算は、労使で認識の違いが起きやすい問題です。残業代の計算は、労使で認識の違いが起きやすい問題です。
- 労働者の残業代計算方法は合っているか
- 労働時間の計算は合っているか
- 労働者に割増賃金を請求する権利があるか
など、十分に吟味し、適切な対応を心がけましょう。精査の結果、労務管理に問題があるようであれば、将来的なリスクを払拭するためにも管理体制の見直しを検討しましょう。
2-2|時効が過ぎている賃金がないか確認
残業代の請求権は2年を過ぎると時効消滅します。
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
引用元: 労働基準法
労働者からの請求がこの時効期限に対し、適当なものであるかは必ず確認しましょう。なお、残業代の請求権は労働者が退職した後でも有効です。
2-3|時効の援用をおこなう
労働者の残業代請求が消滅時効にかかっている場合には時効の援用をおこないます。この援用を怠ると、時効消滅している分の未払い残業も支払うことになる場合があります。労働者からの請求書は放置せず必ず時効を援用しておきましょう。
2-4|労使の話し合いによる解決を目指す
労使の話し合いによる解決を目指す残業代請求は、まずは当事者間の話し合いによる解決を目指しましょう。当事者間で解決が難しい場合は、弁護士などの専門家や労働局などの社外窓口を利用することも検討してください。
3|労働者の残業代請求が認められないケース

労働者の残業代請求が法的根拠に基づくものであれば当然支払わなければなりません。ただし、労働者側の請求に法的根拠が伴っていないという場合もあり得ます。
この項目では、労働者側の請求が認められないケースについてご紹介します。
3-1|請求された残業代が誤っている場合
請求された残業代が誤っている場合労働者側が自ら計算し、請求書を送付してきた場合、計算が誤っていたり、結んでいる労働契約と異なっていたりするケースは少なくありません。
- 固定の割増賃金により支払い済みである。
- 管理監督者であり割増賃金請求の権利がない。
- 労働時間の計算・評価に誤りがある。
会社としては、このような問題がないか十分に吟味しましょう。この段階で弁護士に相談することも検討すべきかもしれません。
3-2|時間外労働の対象外となる労働者の場合
取締役など、労働者ではない場合は割増賃金を請求する権利は基本的にありません。取締役など、労働者ではない場合は割増賃金を請求する権利は基本的にありません。
また、労働者であっても管理監督者など、経営者と一体的立場にある場合も時間外労働・休日労働の割増賃金を請求することはできません。
ただし、役職上は「管理職」という扱いをしていても、「名ばかり管理職」のように、実態として経営者と一体的立場とはいえない場合は残業代を請求する権利があります。
4|残業代請求をされたら弁護士に相談

未払い残業代は近年、厳しく追及される問題です。労働者が訴訟を起こしてきた場合などは早い段階で弁護士に相談し、対応を検討する必要があります。
--------------------
▼無料ダウンロードはこちら▼
https://hrnote.jp/document/?did=148030