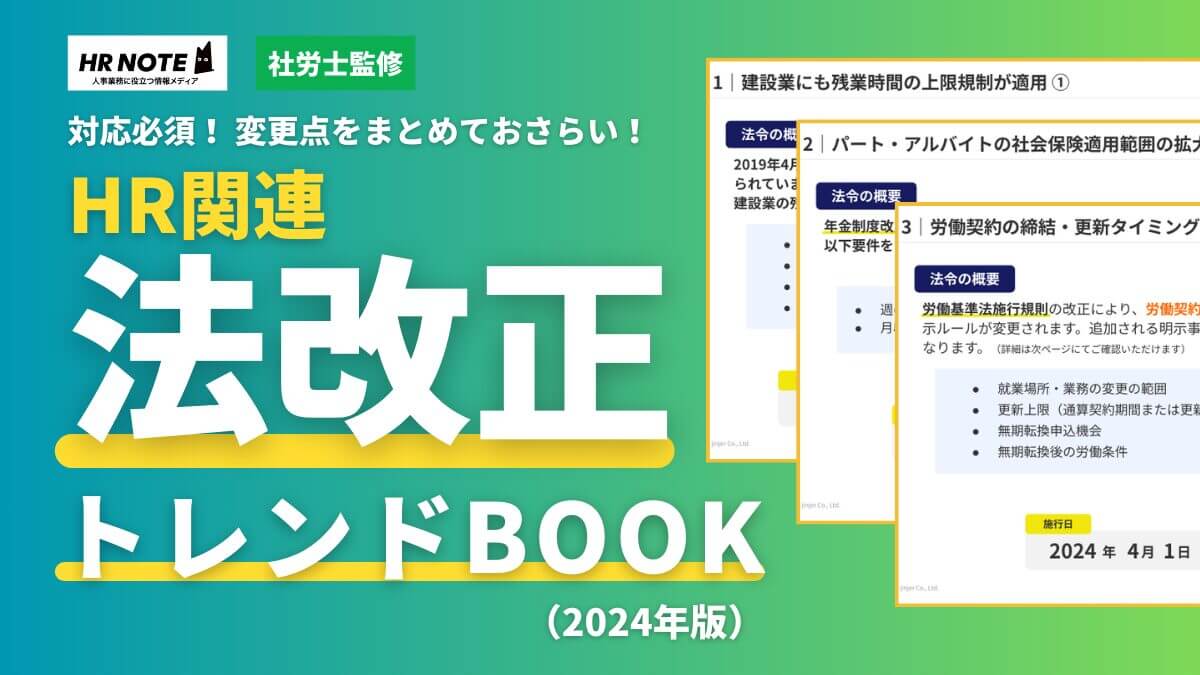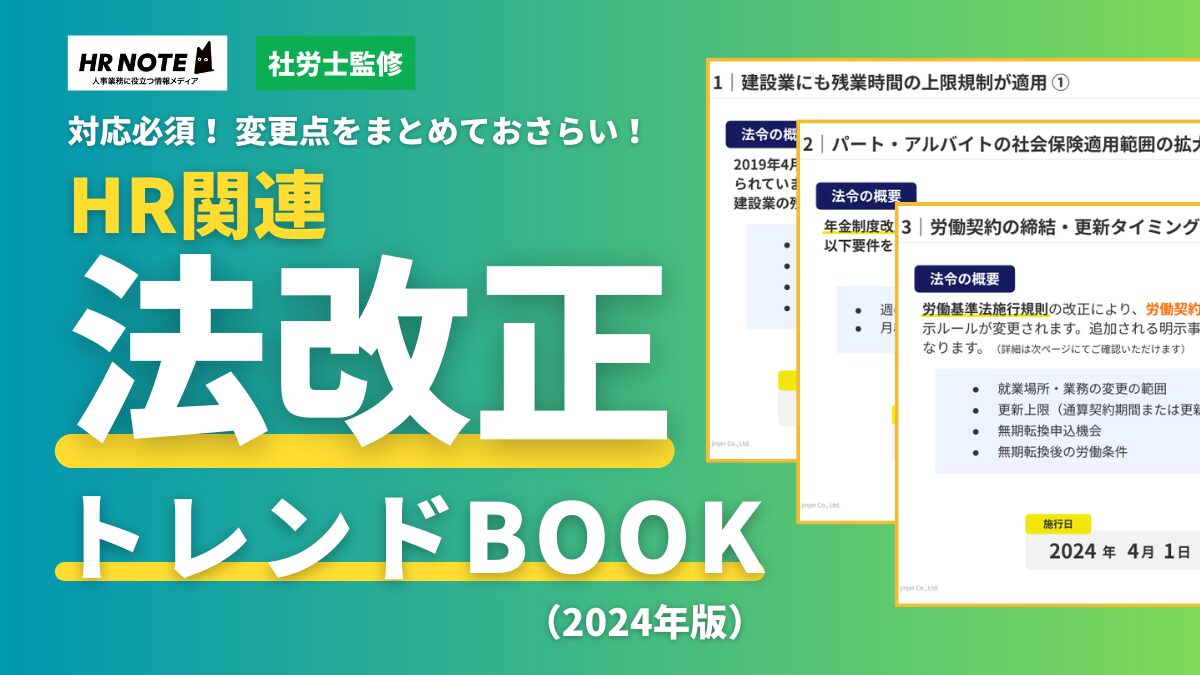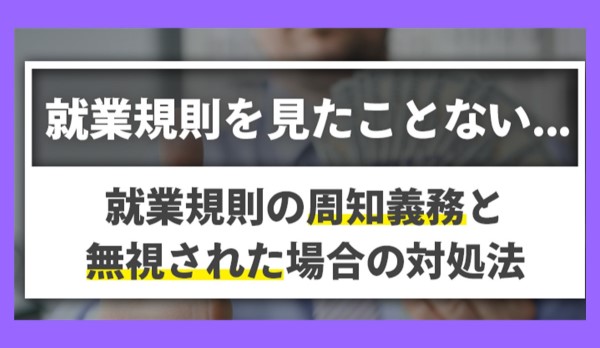
「そう言えば、自分の職場では就業規則を見たことがない……。これって、労働法上問題アリなんじゃない?」
そう疑問に思われたら、ぜひこの記事を読んで就業規則への理解を深めてください。
就業規則とは、「会社の定める従業員が守るべき規則」です。
例えば、労働時間・給与・休暇・退職・懲戒解雇等についてのルールが定められています。
実は就業規則はこれを定めたのであれば全ての労働者に周知させることが労働基準法106条で義務付けられています。
会社は一定のルールを設けるのであれば当然それを労働者に開示するべきですし、労働者としても知らなければルールを守れませんよね。
就業規則は会社の規則であるとともに、労使間の契約内容を構成するものですので、労働者と使用者間の様々なトラブルを解決する指針となります。
では、現在あなたがお勤めの会社で就業規則が周知されていない場合は、どう対処すればよいのでしょうか?
「ください」と言えば、必ず渡してもらえるものなのでしょうか?
交付を拒否された場合の対策についても、わかりやすく解説します。
目次
【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版
2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。
2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。
人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。
- 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい
- 社労士が監修した正確な情報を知りたい
- HR関連の法改正を把握しておきたい
という方はぜひご確認ください!
人事×ChatGPTの具体的な活用術術を紹介!
ChatGPTをはじめとする生成AIを業務に取り入れることで、業務時間の圧縮や業務量の削減が期待されます。今回は、人事の方が今日から使えるChatGPT活用術として、実際に使えるプロンプトを交えた実践的なノウハウもご紹介します。
▷こんな方におすすめ!
- 人事業務の担当者の人手が足りず困っていて業務効率を上げたい
- ChatGPTに興味はあるけれど、どんなことに使えばよいか分からない
- 業務にChatGPTを取り入れたいが、イメージしているような回答が出てこない
▼当日の視聴予約はこちらから!▼
https://seminar.hrnote.jp/post/95
1|就業規則を見たことない労働者が知っておくべき3つのこと

1-1|就業規則は労働者への周知義務がある
冒頭で述べた通り、会社には就業規則を従業員に周知させる義務があります(労働基準法106条)。
これは事業者が社会(国)に対して負っている義務であり、違反すれば労基署による指導の対象となります(場合によっては刑事罰もあります。)
会社が労基法上の周知義務を果たしたと言える基準
労働基準法施行規則52条の2が、具体的な週知方法について以下の通り定めています。
【労働基準法】
第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
就業規則を設けた場合は、以上のような方法で周知を行なっていないと、労働基準法違反となってしまいます。
違反した事業者は30万以下の罰金になる可能性もある
この場合、所轄労働基準監督から指導・是正勧告を受ける可能性があるほか、事案が悪質な場合は30万円以下の罰金を科されることもあります(労働基準法120条)。
なお、就業規則の「周知」については、その効力に関係する以下のような法律もあります。
【労働契約法】
第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
これは、就業規則を「周知」した場合、規則の内容が労働契約の内容を構成する旨定める条文です。ここでいう「周知」は、上記労働基準法による「周知」とは意味が異なります。
すなわち、この「周知」は就業規則が法的効力を発揮するための要件であり、具体的な方法は問わず、労働者が就業規則の内容を知ろうと思えばいつでも知り得る状態においた場合に「周知」があるとされます。
したがって、労働基準法に基づく「周知」がされていなくても、労働者が就業規則の内容を知ろうと思えばいつでも知ることができる状態にあったのであれば、就業規則は法的効力を有するということです。
わかりにくい部分ですが、一応留意してください。
1-2|常時10人未満の労働者を雇用する会社なら無い可能性もある
労働基準法第89条には、「常時10人以上の労働者(※パート・アルバイト含む)を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定められています。
要するに、常時10人以上の労働者を使用している事業所は就業規則の作成・届出義務があるものの、そうでない事業所では就業規則を作成・届出する義務がないということです。
そのため、あなたが現在お勤めの事業所にいる常勤従業員(パート・アルバイト含む)が10人未満である場合には、会社はその事業所で就業規則を定める必要がないということです。
なお、この規程は常時10人未満の事業場で就業規則を定めてはいけないという意味ではありませんので、そのような事業場が自主的に就業規則を作成することは可能ですし、作成している事業場もたくさんあります。
1-3|就業規則で定められていることは?
会社によって就業規則の内容は異なりますが、いくつか共通するポイントはあります。
例えば、労働基準法89条は、以下の内容を必ず就業規則に入れることを義務付けており、就業規則には通常これらの事項が記載されています。
- 始終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
- 退職・解雇に関する事項
また、会社が就業規則に盛り込むことができる範囲に特段限定はありませんので、会社が必要と考えるのであればその他の労働条件についても必要に応じて定めることができます。
たとえば、
- 退職手当
- 最低賃金額
- 労働者の食費・作業用品等の負担
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償及び業務外の傷病扶助
- 表彰及び制裁
などです。
以下では、主な項目について注意すべき点を確認していきましょう。
賃金
賃金については就業規則の中に規定されている場合と、賃金規程・給与規程といった別規程に整理されて規定されている場合があります。
賃金については、基本給、各種手当、時間外・休日・深夜労働(残業)の割増賃金、退職金などが記載されています。
なお、退職金は設けるか設けないかは会社の自由であり、必ず規定があるものではありません(退職金の規定がないということは、退職金制度が存在しないということです。)。
休日・休暇
所定休日、有給休暇・慶弔休暇・育児・介護休暇など休日・休暇に関する規定も、要チェックです。
なお、休日については「毎週1日以上、または4週4日以上」、有給休暇は「入社後6ヶ月経過してからの付与」が、それぞれ労働基準法第35条、第39条で義務付けられています。
退職
退職に関する事項には、退職や解雇の事由が定められます。特に解雇については、会社による普通解雇に理由があるかないかを判断するためのとっかかりになりますので、重要です。
ハラスメント
セクハラ・パワハラ・マタハラなどのハラスメントの規定を置くかどうかは任意です。
もっとも、セクハラやパワハラについては、法律上、一定の体制整備が求められており、就業規則でハラスメントについて定めている会社は多いです。
【弁護士解説】誰も知らない見たことない就業規則の法的効力はあるのか?
会社からは就業規則があるという説明を受けているが、実際には見たことがないということも多いでしょう。
2-1|知ろうと思えば知れる状態であったかどうかが重要
例えば、人事が保管・管理しているけれでも見せてもらったことはないとか、イントラネット上には就業規則データがアップロードされているが、アクセスしたことがないなどです。
イントラネット(英語: Intranet)は、組織内におけるプライベートネットワークで、インターネットの機器やプロトコルを利用してコスト削減と利便性の向上を図りつつ、企業内の情報をその中で扱うために必要な防護等の措置が講じられたものである。
引用元:Wikipedhia
上記のケースが労基法違反となるかどうかは別として、就業規則の効力という観点からすれば「従業員が知ろうと思えば知り得る状態であったかどうか」が判断基準となります。
2-2|知れる環境があっても閲覧方法が周知されていない場合
他方、就業規則を人事が保管・管理しているらしいという噂はあっても、会社から明確な説明がされたことはなく、かつ閲覧の手続・方法も特に説明されていない。
という場合であれば、従業員は知ろうと思ってもこれを知ることができない可能性もあるため、「周知」がなく、効力を有しないという評価はあり得ます。
2-3|「最低基準効」と「直律効」
ところで就業規則には法律により特別かつ強力な効力が認められています。それは、「最低基準効」と「直律効」というものです。
「最低基準効」とは
就業規則に定める条件に達しない労働条件を定める労使間の合意を無効とするという強力なものです。
したがって、労使間で賃金を就業規則(賃金規程)で定める手当の一部を支給しないという合意をしたとしても、そのような合意は絶対的に無効です。
「直律効」とは
最低基準効により無効となった労働条件部分を就業規則が直接補完するというものです。
したがって、上記のような賃金合意をしても、最低基準効によりその合意が無効となり、かつ直律効により就業規則(賃金規程)どおりの手当支給を受けられることになります。
3|就業規則の周知を怠るのは違反となる可能性大|開示を求めても応じないなら労基署に相談
上記のとおり、労働基準法(労働基準法施行規則)では、事業主が社会的に義務付けられている、就業規則の「周知」方法を具体的に定めています。
そのため、その方法に従わない周知は全て法令違反となり、労基署による指導の対象となったり、場合によっては刑事責任を問われたりします。
会社で就業規則を設けている場合、その周知方法が上記法令に照らして問題がないかは一応確認しておきましょう。
まとめ
就業規則の周知は、労働基準法上、事業主の義務です。
この義務としての「周知」をしているかどうかが就業規則の効力に直接影響することはありませんが、これをしていないと行政・司法による一定のペナルティを受ける可能性があります。
就業規則は、労使間の労働条件その他待遇についての基本事項を定める従業な書類です。
もし、事業場で就業規則が作成されているのであれば、一度くらいは目を通しておいて損はないでしょう。
梅澤 康二氏 :アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
--------------------
▼無料ダウンロードはこちら▼
https://hrnote.jp/document/?did=148030
ChatGPTで変わる人事業務【実践編】
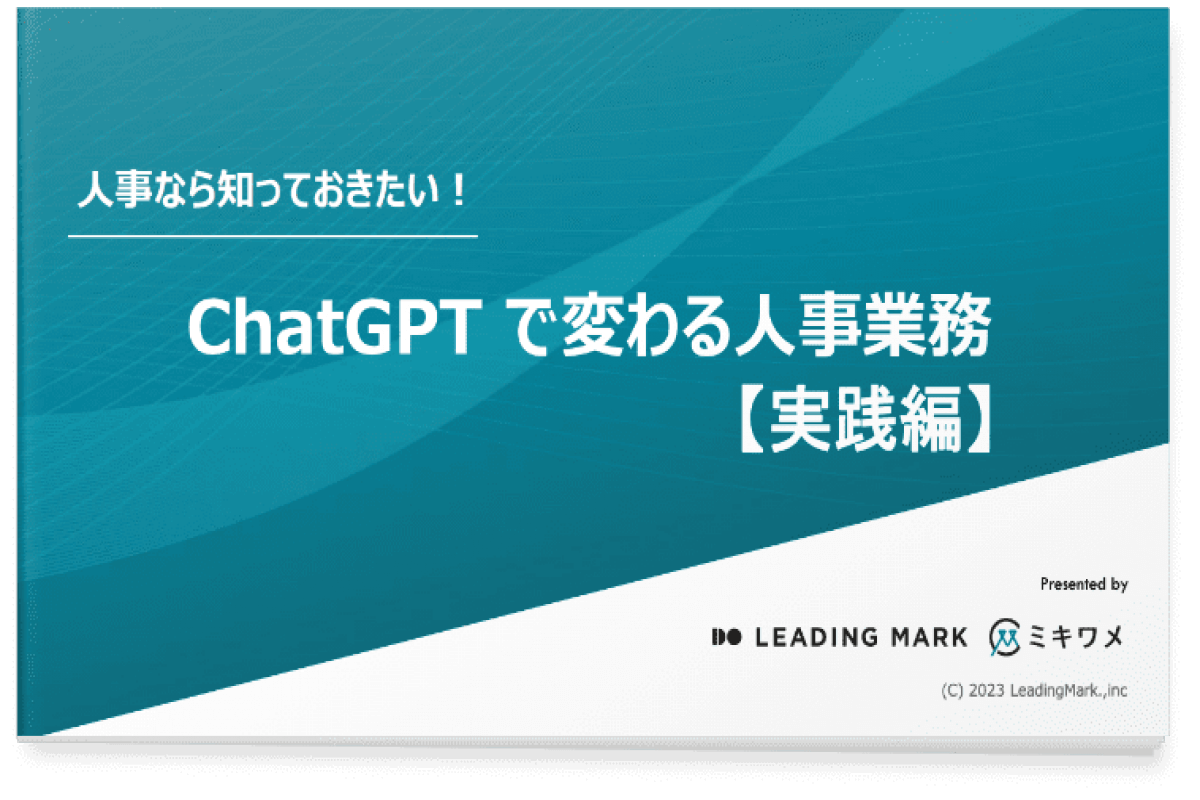 昨今のHR領域では、いかにAI・データの活用をおこなえるかが課題となっており、ChatGPTの登場により、ますます注目度が高まりました。
昨今のHR領域では、いかにAI・データの活用をおこなえるかが課題となっており、ChatGPTの登場により、ますます注目度が高まりました。
一方でChatGPTを業務に取り入れていきたいと考えている方の中には、
- ChatGPTではどのような業務に取り入れられるのかわからない
- 興味はあるものの、具体的にどの場面で活用できるのかわからない
などと考える方がいるのではないでしょうか。
本資料では、「ChatGPTの導入によって人事業務にどのような変化がでるのか」についてわかりやすく解説しています。
人事業務×ChatGPT活用について知りたい方は、ぜひご確認ください!