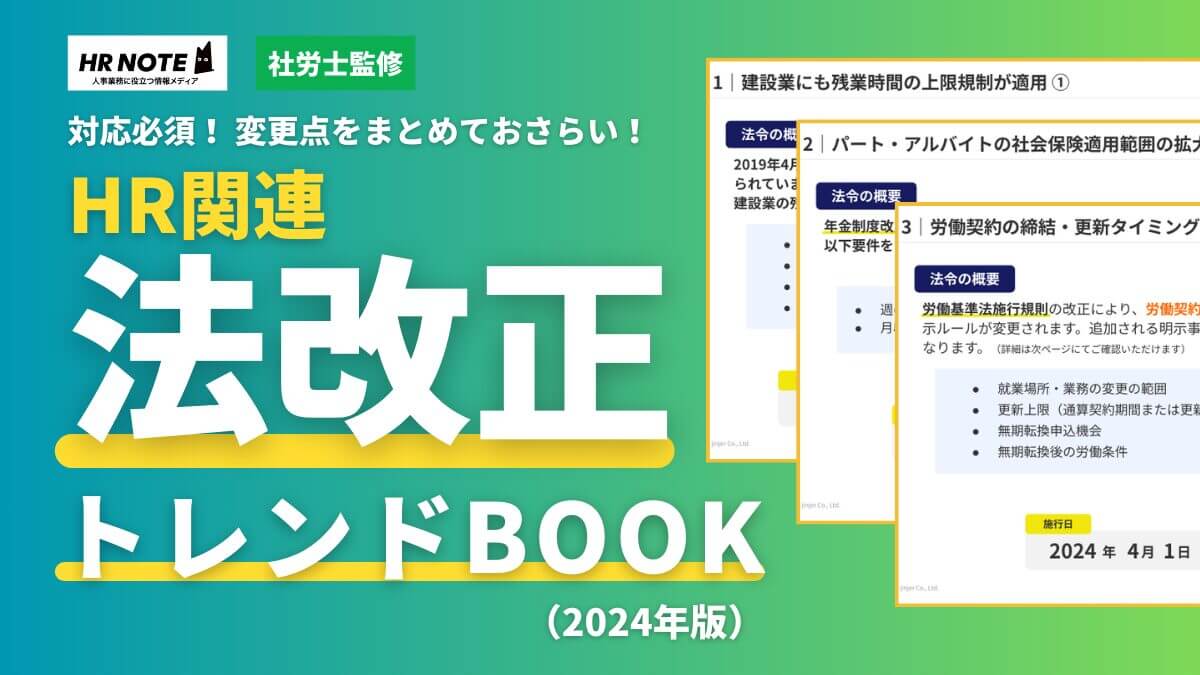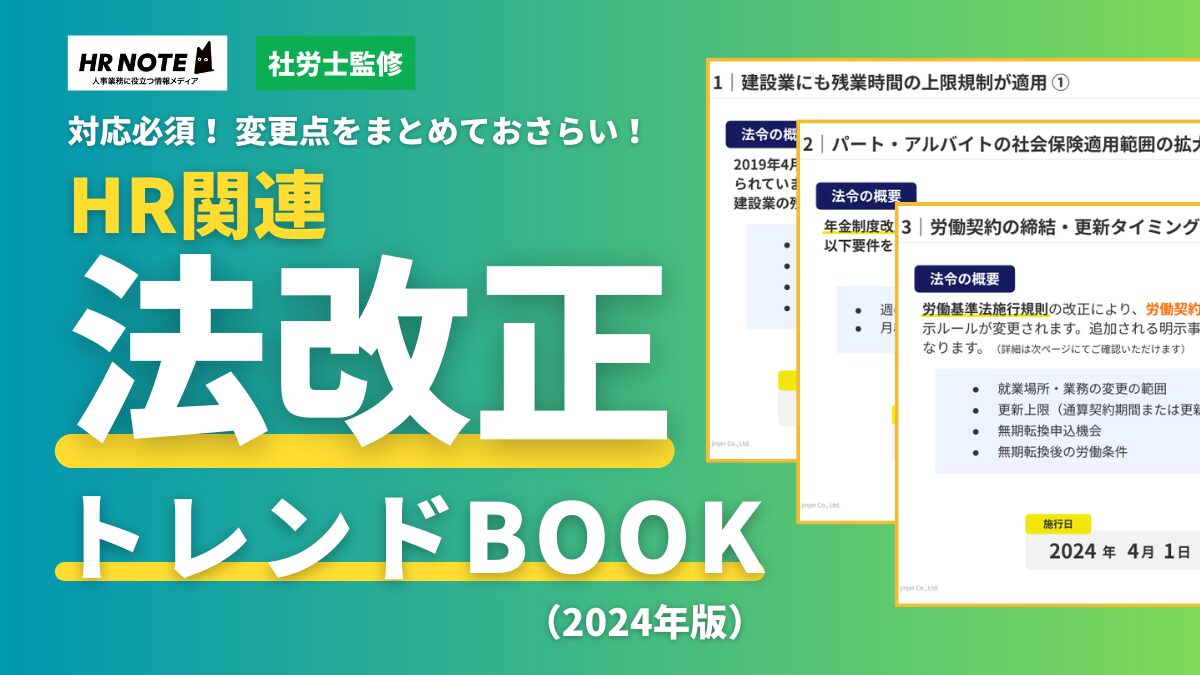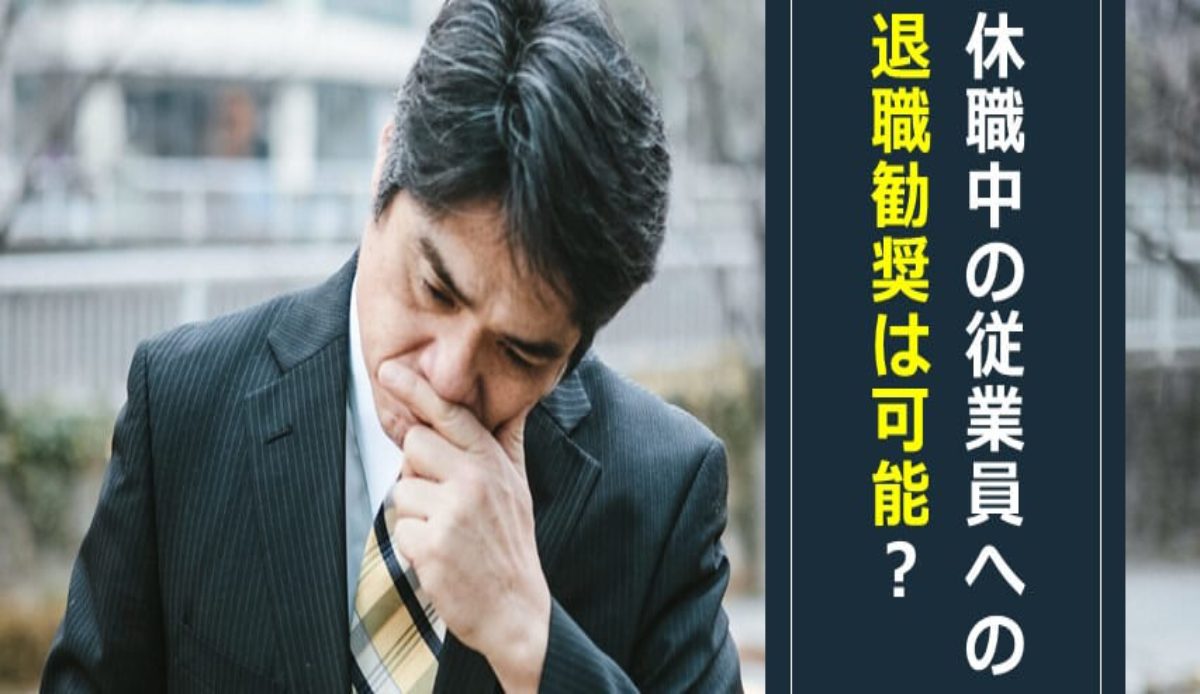
休職中の従業員への退職勧奨は基本的に難しく、無茶な退職勧奨は「不当解雇」などの法的リスクを負うことになります。ただし、不可能というわけではありません。
この記事では、休職中の従業員に対し、退職勧奨を行う際、どのような点に気を付ければいいのか、具体的な流れとともにご紹介します。
目次
【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版
2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。
2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。
人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。
- 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい
- 社労士が監修した正確な情報を知りたい
- HR関連の法改正を把握しておきたい
という方はぜひご確認ください!
休職中の従業員に退職勧奨を行うのは可能?
まずは休職中の従業員に対する退職勧奨の適法性等について説明します。
休職中の従業員への退職勧奨自体は可能
結論から申し上げると、休職中の従業員に対して退職勧奨を行うこと自体は可能です。
しかし、休職中の従業員は心身の故障により精神的に脆弱になっている可能性もありますし、通常は休業もやむを得ない理由によるものであり、好きで休んでいるわけではありません。
そのため、退職勧奨を行う際はこれらを踏まえて一定の配慮が必要になると思われます。
このような配慮を欠く退職勧奨行為は、退職強要であるとして違法と評価される可能性がありますので、注意しましょう。
例えば、うつ病で休職中の従業員について考えてみますと、当該従業員は病気の影響で精神的に不安定な場合が多いです。
そのような中、突然、明確な理由もなく退職勧奨をされれば、絶望してしまって病状が悪化するかもしれません。最悪の場合はこれが引き金となり自殺してしまうということも十分考えられます。
この場合、会社は安全配慮義務違反を理由として損害賠償責任を負う可能性があります。したがって、うつ病のような重大な精神疾患にかかっている従業員については、少なくとも休職期間が満了するまでは退職勧奨を行うべきでないと思われます。
他方、休職期間が満了しても復職が難しそうという場合に、自然退職扱いとする前段階で退職勧奨を行うことはあり得ると思われます。
休職中の従業員を解雇するのは基本的に難しい
休職期間中の解雇は基本的に難しいでしょう。休職は解雇を猶予するための制度であるため、当該猶予期間中に解雇することは背理といえます。
休職期間中に解雇した場合、労働契約法16条に違反する解雇として、効力が否定される可能性は高いと思われます。
<労働契約法16条>
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
もっとも、休職期間中に治療に専念すべきところ遊び呆けているとか、復職が可能であるのにこれをしないで休み続けているというケースは別です。ただ、この場合もまずは復職の命令を出して、休職期間を終了させた上で処理するべきと思われます。
いずれの場合も、休職期間満了時に復職できないときは、退職となる旨定められているのが通常ですので、そのような処理となります。
退職勧奨の具体的な流れ
基本的に退職勧奨は下図のような流れで進みます。

勧奨を行うこと自体は違法ではありませんが、手順や回数などの配慮を怠ると、法的リスクが高まることを認識してください。適切な手順で退職勧奨を行うことが、会社を守ることにつながります。
1:退職勧奨の方針を決定する
まず、対象となる従業員に退職勧奨を行う具体的理由を明確にします。
重要なのは、具体的かつ客観的な理由を明らかにすることです。経営者個人の主観的な思いや抽象的理由で退職勧奨をしても従業員は納得出来ないでしょうし、場合によっては不合理な退職勧奨(退職強要)として違法と評価される可能性があります。
実務的には、対象社員について問題と認める事実、問題と評価する理由、会社に対する影響等について整理しておくのが良いかと思われます。
2:従業員との面談を実施する
退職勧奨を行う際には、ほかの従業員に知られないよう、時間帯や場所に配慮して面談を行いましょう。
退職を求められるという事実は不名誉な事柄であるため、当然、他の人に知られたくない情報です。この点について配慮してあげることは極めて常識的な事柄といえます。
3:従業員に退職して欲しい旨冷静に伝える
従業員との面談では、会社側で検討した具体的理由を説明し、従業員側の意向や状況を聴取した上で、退職を求めます。
単に口頭で説明をしただけでは従業員が納得できないということも十分ありえますので、会社が退職を求める理由やこれを裏付ける資料等を書面で提示してあげると納得感を得やすくなります。
間違っても、従業員に対して高圧的な姿勢を取ってはいけません。
退職勧奨はあくまで任意での退職を求めるものに過ぎませんので、この点も十分に説明した上で、冷静に対応してください。従業員から反発されて感情的な対応をされても、こちらが感情的になってしまうことは厳禁です。
昨今はスマートフォンで誰でもいつでも録音を取ることが可能です。そのため、退職勧奨の面談の際は従業員が録音をしていることを想定する必要があります。このような録音を阻止することはできませんので、録音されていることを前提に終始冷静に対応する必要があるでしょう。
4:退職勧奨についての回答期限を従業員へ伝える
退職勧奨は従業員の任意退職を求める行為です。そのため、従業員からすれば「じっくり検討したい」と考えるのは当然です。そのため、従業員が即時同意してくれればよいですが、「少し考えたい」という場合は適切な検討期間を与えましょう。
従業員が「検討したい」と要望しているのに、「この場で返事をせよ」と迫る行為は、「退職強要」と評価される可能性が高く、仮にその時に同意を取れても後日同意の効力が争われやすいです。
この場合の適切な検討期間はケースバイケースです。実務的には1週間程度としているケースが多いように思われますが、状況によって変わりますのであくまで目安と考えてください。
5:退職時期や金銭面の処遇についても伝える
従業員に退職勧奨に応じてもらう方法の一つとして、退職に一定のプレミアムを付けるということは実務上よくあります。
例えば、退職勧奨に応じて退職をする場合、会社都合退職とすること、退職まで有給休暇を与えること、退職時の有給休暇を買い取ること、退職にあたり特別退職金として支給することなどが挙げられます。
このような提案をする場合、言った言わないという争いを避けるためにも、書面やメールで退職条件を明確にすることを推奨します。
6:退職を書面で明確にする
退職勧奨の結果、従業員が退職に合意した場合には、必ず書面で合意内容を明確にしましょう。
何も書面を作成しないと、後日、従業員から退職の意思はなかったなど反論される可能性は十分にありますし、この場合、会社が当該従業員の退職を立証することは困難です。
退職勧奨の仕上げとして、退職日、退職条件等を明確にする書面作成は必須です。
退職勧奨を行う際の注意点!
上記で記載した内容とも重複しますが、退職勧奨を行う際の注意点を説明します。
退職勧奨時の話し方に注意する
退職勧奨を進めるにあたっては、発言内容や話し方に注意してください。内容や話し方が高圧的であったり、一方的であったりする場合、退職勧奨が違法な退職強要と評価される可能性があります。
会社側は感情的にならず、冷静に落ち着いて話をする必要があります。従業員が感情的になっていたり、挑発的な言動を取ったりしてもこれにつられてはいけません。
退職を目的とした配置転換などはしてはならない
退職勧奨とは少し違いますが、従業員を退職に追い込むために合理性のない配置転換を行うことは違法な嫌がらせと評価される可能性があります。
会社は従業員の配置や職務を変更する権利はありますが、退職に追い込むために閑職に追い込んだり、不必要な人事異動を濫発したりすることは「権利濫用」として許されませんので、注意してください。
退職勧奨の態様にも注意
退職勧奨を執拗に繰り返す、多人数で臨んで退職を求める、従業員が拒否したのに勧奨を繰り返す、長時間拘束しながら退職を求めるなどといった行為は違法な退職強要と評価される可能性があります。
退職勧奨は、適切な時間、場所、人数でこれを実施する必要があります。

まとめ
これまでもお伝えしてきた通り、退職勧奨には法的なリスクがつきものです。
適切な手順で退職勧奨を行うためには、ぜひ企業労務問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
中川浩秀 (東京弁護士会所属)
ゼロからイチを始めようとする起業家のさまざまな悩みに対応。自身の起業経験を活かし、スタートアップ、ベンチャーの業界に精通した柔軟な対応が可能。
--------------------
▼無料ダウンロードはこちら▼
https://hrnote.jp/document/?did=148030
ChatGPTで変わる人事業務【実践編】
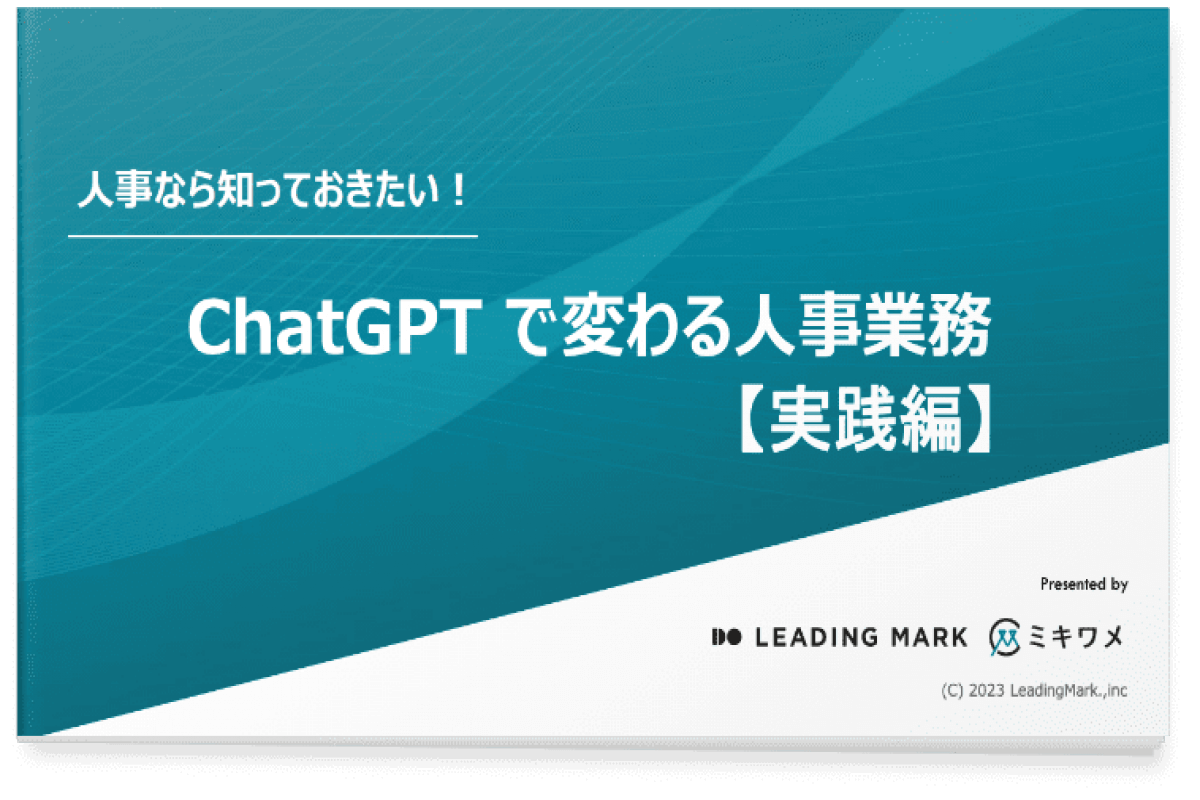 昨今のHR領域では、いかにAI・データの活用をおこなえるかが課題となっており、ChatGPTの登場により、ますます注目度が高まりました。
昨今のHR領域では、いかにAI・データの活用をおこなえるかが課題となっており、ChatGPTの登場により、ますます注目度が高まりました。
一方でChatGPTを業務に取り入れていきたいと考えている方の中には、
- ChatGPTではどのような業務に取り入れられるのかわからない
- 興味はあるものの、具体的にどの場面で活用できるのかわからない
などと考える方がいるのではないでしょうか。
本資料では、「ChatGPTの導入によって人事業務にどのような変化がでるのか」についてわかりやすく解説しています。
人事業務×ChatGPT活用について知りたい方は、ぜひご確認ください!