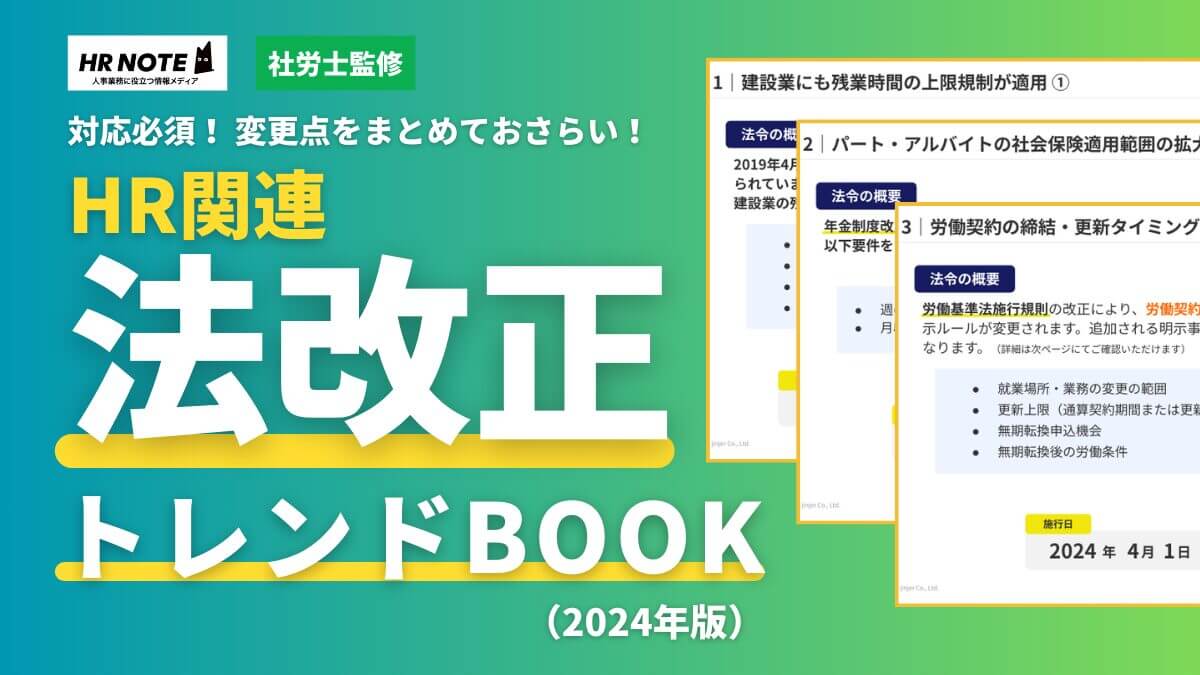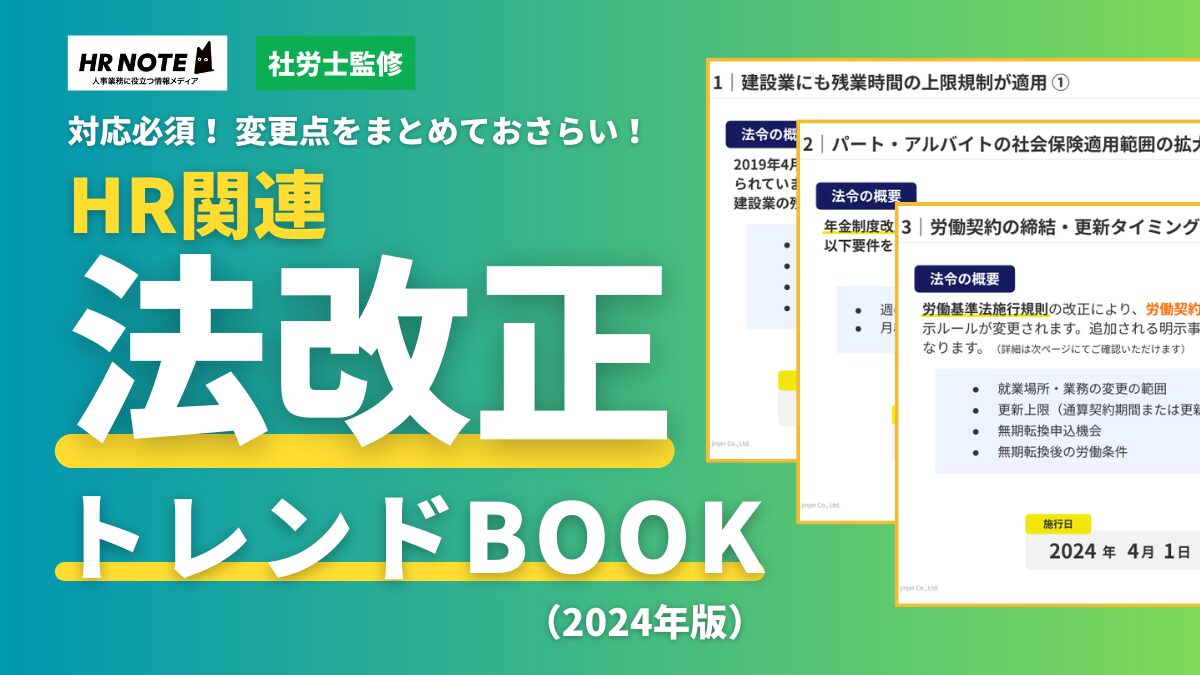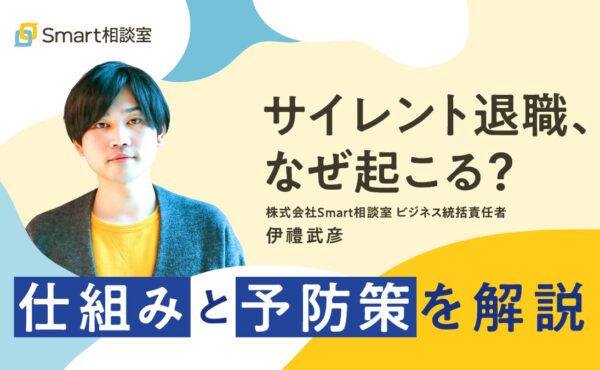付加金(ふかきん)とは、残業代等を支払わない悪質な会社に対する一種の制裁措置のことで、労働者が裁判手続で割増賃金等を請求した場合、裁判所の判断でペナルティとして「付加金」の追加支払いを命じられることがあります。
この記事では、付加金について簡単に解説します。
目次
【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版
2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。
2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。
人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。
- 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい
- 社労士が監修した正確な情報を知りたい
- HR関連の法改正を把握しておきたい
という方はぜひご確認ください!
付加金の支払われるケース
付加金は法律上の要件を満たした場合に支払われます。どのような要件を満たした場合に支払われるのか確認していきましょう。
労基法で定められた賃金等の未払いがあること
付加金は、労基法で定められた賃金等の未払いがある場合に請求が可能です。
具体的には労働基準法第114条が以下のように定めています。
(付加金の支払)
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
引用元:労働基準法第114条
条文では、第20条、第26条、第37条、第39条第9項の規定に違反した場合に、付加金の支払いを命じることができるとされています。
各条項が定める支払いは以下の通りです。
- 解雇予告手当(20条)
- 休業手当(26条)
- 割増賃金(37条)
- 有給休暇に対する対価(39条)
上記の未払いがあった場合に限り、労働者は裁判所に対して付加金の支払いを命じるように求めることができます。
なお、通常の賃金未払いについては、付加金の請求根拠とはならないので注意してください。
【関連記事】
裁判所が付加金の支払いを命じること
労働者が裁判所に求めたとしても、裁判所が必ず付加金の支払いを命じるわけではありません。
裁判所が付加金の支払いを命じるのは、企業による未払いが付加金による制裁が必要なほど、悪質なものと認められた場合に限られます。
例えば、割増賃金を例に取ると、未払いの金額、期間、理由、その他諸般の事情を総合考慮した上で、悪質と判断された場合に相応の付加金の支払いを命じることになります。
他方、諸般の事情から未払いが悪質とまでは言えない場合には、割増賃金の支払いは命じても、付加金の支払いを命じないということもあり得るわけです。
付加金で支払われる金額
裁判所が付加金の支払いを命じる場合、未払いの割増賃金等の認定額を上限に、裁判所が妥当な金額を決定します。
つまりは、裁判所が最大限の付加金を認めた場合、労働者が受け取れる金額が未払い額の2倍となるというわけです。
例えば、割増賃金の未払額が100万と裁判所が認め、これについて付加金の支払いを命じる場合、裁判所は100万円を上限として妥当な金額を決定することになります。
付加金の支払われるケースは限定的
割増賃金等に未払いがある場合でも、実際に付加金が支払われたという事例を聞くことは稀ではないでしょうか。
確かに付加金の支払いまでされるケースは限定的です。その理由を簡単に解説します。
訴訟手続が必要であるから
付加金の支払いが命じられるのは、労働者が訴訟手続で請求し、裁判所が判決でこれを認めた場合に限ります。
そのため、割増賃金等の未払いが、
- 話し合いで解決する場合
- 労働審判で解決する場合
- 訴訟上の和解で解決する場合
には、付加金の支払いはされません。
そして、労働事件の多くはこのような訴訟以外の処理により解決終了しています。これが理由の一つです。
【紛争処理制度ごとの利用件数】
| 紛争調整委員会によるあっせん | 5,021件 |
| 労働審判 | 3,369件 |
| 労働訴訟 | 3,526件 |
【労働に関する訴え】
| 総数 | 2,463件 |
| 判決 | 519件 |
| 和解 | 1,597件 |
| その他 | 347件 |
控訴審で弁済すると付加金の支払いは不要となる
日本の裁判では三審制が採用されており、1つの事件につき3回まで(原審、控訴審、上告審)裁判が受けられます。
控訴審までは希望すれば誰でも手続を進めることが可能(上告審については受理されることが稀です)。
そして、付加金については、原審で支払いを命じられたとしても、控訴審で一定の精算をすることで、支払い義務を消滅させることができます。
例えば、原審の裁判所が割増賃金と共に付加金の支払いを命じる判決を出したとしましょう。
この場合、支払いを命じられた企業は控訴することができ、それにより原審の判断は仮執行宣言が付されているものを除き効力を失います。
そして控訴審の判断前に、原審が認めた割増賃金の未払い分全額を弁済すると、控訴審は割増賃金の未払いの事実が存在しないため、付加金の支払いを命じることができなくなるのです。
つまりは、企業側は、たとえ第一審の判決で付加金の支払いが命じられたとしても、控訴して未払い金を清算すれば、控訴審では付加金を支払うよう命じられることがなくなり、結果的に支払い義務を免れるのです。
このように付加金の支払い義務は簡単に回避することができることも、理由の一つと言えるでしょう。
付加金請求を行う意味
裁判所は付加金の支払いについて簡単には命じず、しかも命じられても企業側は支払いを簡単に回避できます。
となると、付加金を請求する意味がないのでは?と感じる人もいるかもしれません。
しかし、付加金の支払いを命じられるということは、企業の賃金等の未払いが悪質であると裁判所に認定されたことを意味します。
そうなれば、企業の印象・評判にキズがつきかねないため、一定のプレッシャーになり得ます。
また、仮に付加金の支払いを命じられた場合、企業がこれを回避するためには、控訴審で割増賃金等に未払があるとの原審判断を覆すか、原審の認定した未払分を任意で弁済するしかありません。
前者のハードルが極めて高いことから、通常は後者の対応を行うケースが多いでしょう。
労働者は強制執行しなくても、未払いについて満足を得ることができるので、解決が迅速です。
したがって、付加金制度にはやはり一定の意義があるといえます。
付加金の支払いが命じられた具体的事例
最後に、付加金の支払いが認められた事例をいくつか紹介します。
未払いの残業代・付加金を含め500万円以上の支払いが命じられた事例
年俸制で働いていた男性医師が、病院を運営する法人に対して、未払い残業代計725万円を請求。
1審、2審では医師側の請求が認められなかったが、最高裁で判断が一転、審理を高等裁判所に差し戻していた。
差し戻し控訴審では、最高裁判決を踏まえ、付加金を含め計546万円の支払いが命じられました。
参考:
医師の残業代、年俸に含まず、500万円支払い命じる 東京高裁差し戻し審
未払い残業代と付加金合わせて約180万円の支払いが命じられた事例
警備業の男性が、宿直での仮眠も労働時間にあたるとし、未払い残業代などの支払いを勤務会社に求めた事例。
勤務は24時間で、4時間30分の仮眠時間と30分の休憩時間が設けられていた。
しかし、休憩・仮眠時間のあいだも、対応できるような状態を保つ必要があった。
そのような状況においては、休憩・仮眠時間も業務から解放されているとは言えないため、ほぼ原告の請求通り、未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう命じた。
参考:
2020年4月以降に割増賃金等の消滅時効が3年となる可能性がある
現在、労基法上の賃金等の消滅時効期間は2年であり、付加金もこの2年間の未払いについて請求するべきものとされています。
しかし、2020年4月に改正民法が施行されることに伴い、賃金等の消滅時効期間が2年から3年に伸長される可能性があります。
より詳しく説明すると、今回施行される改正民法によって、債権の消滅時効期間が以下のとおり統一されます。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(主観的起算点)
②権利を行使することができる時から10年間(客観的起算点)
このような改正に伴い、賃金の消滅時効期間も見直されます。
上記に合わせるという議論もあったようですが、当面は2年から3年に消滅時効期間を伸長する方向で調整中のようです。
この点は現時点ではまだ確定したものではないため、今後の政府対応を注視する必要があるでしょう。
まとめ
付加金についてはよく知らない、初めて知ったという方がほとんどだったかと思います。
今回説明したのは、あくまで付加金制度の基本的な事柄です。
実際に付加金を請求するには、元となる未払いの割増賃金等の正確な金額、回収の可否などをまずは検討しなくてはなりません。
また、付加金が支払われるのは、裁判所が判決で命じた場合のみです。必然的に裁判で争う形になるため、解決に長い時間がかかります。
そのため、できることなら弁護士の力を借りることをおすすめします。
梅澤 康二氏 :アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
--------------------
▼無料ダウンロードはこちら▼
https://hrnote.jp/document/?did=148030